ヨーロッパ最高峰レース、パリ・ロンシャンの「凱旋門賞(Prix de l’Arc de Triomphe)」。
この芝2400メートルの舞台は、日本馬にとって“世界との対話”であり、長年にわたる挑戦と挫折の歴史でもあります。
負けても立ち上がり、何度でも挑むその姿には、多くのドラマと感動が詰まっています。


凱旋門賞とは
フランス・パリのロンシャン競馬場で毎年10月に行われる芝2400mの100年以上の歴史を誇る世界最高峰レース。
欧州の三冠馬や各国の強豪が集う“世界一のレース”と称され、日本では「凱旋門賞制覇=世界制覇」の象徴とされています。
凱旋門賞に挑戦した日本馬・着順の一覧
| 年 | 馬名 | 着順 | 騎手 |
| 2024年 | シンエンペラー | 12着 | 坂井瑠星 |
| 2023年 | スルーセブンシーズ | 4着 | C.ルメール |
| 2022年 | タイトルホルダー | 11着 | 横山和生 |
| ステイフーリッシュ | 14着 | C.ルメール | |
| ディープボンド | 18着 | 川田将雅 | |
| ドウデュース | 19着 | 武豊 | |
| 2021年 | クロノジェネシス | 7着 | O.マーフィー |
| ディープボンド | 14着 | M.バルザローナ | |
| 2020年 | ディアドラ | 8着 | J.スペンサー |
| 2019年 | キセキ | 7着 | C.スミヨン |
| ブラストワンピース | 11着 | 川田将雅 | |
| フィエールマン | 12着 | C.ルメール | |
| 2018年 | クリンチャー | 17着 | 武豊 |
| 2017年 | サトノダイヤモンド | 15着 | C.ルメール |
| サトノノブレス | 16着 | 川田将雅 | |
| 2016年 | マカヒキ | 14着 | C.ルメール |
| 2014年 | ハープスター | 6着 | 川田将雅 |
| ジャスタウェイ | 8着 | 福永祐一 | |
| ゴールドシップ | 14着 | 横山典弘 | |
| 2013年 | オルフェーヴル | 2着 | C.スミヨン |
| キズナ | 4着 | 武豊 | |
| 2012年 | オルフェーヴル | 2着 | C.スミヨン |
| アヴェンティーノ | 17着 | A.クラストゥス | |
| 2011年 | ヒルノダムール | 10着 | 藤田伸二 |
| ナカヤマフェスタ | 11着 | 蛯名正義 | |
| 2010年 | ナカヤマフェスタ | 2着 | 蛯名正義 |
| ヴィクトワールピサ | 7着 | 武豊 | |
| 2008年 | メイショウサムソン | 10着 | 武豊 |
| 2006年 | ディープインパクト | 失格 | 武豊 |
| 2004年 | タップダンスシチー | 17着 | 佐藤哲三 |
| 2002年 | マンハッタンカフェ | 13着 | 蛯名正義 |
| 1999年 | エルコンドルパサー | 2着 | 蛯名正義 |
| 1986年 | シリウスシンボリ | 14着 | M.フィリッペロン |
| 1972年 | メジロムサシ | 18着 | 野平祐二 |
| 1969年 | スピードシンボリ | 着外 | 野平祐二 |
日本馬、凱旋門賞への夢物語 ― 名馬たちの挑戦録
エルコンドルパサー(1999年)
「あと100メートル、日本競馬の夢が叶うはずだった。」
日本調教馬として初めて“欧州滞在”で凱旋門賞を本気で狙った革命児。
海外GⅠ・サンクルー大賞を制し、満を持して迎えた本番。
モンジューとの一騎打ちは、まるでサムライと騎士の決闘のようだった。
最後の100メートル、夢は指先からすり抜けたが、フランスでは「サムライホース」として今も語り継がれている。
彼の2着が、日本の競馬を“世界レベル”へ押し上げたことに疑いはない。
ディープインパクト(2006年)
「世界が注目した、悲しき天才。」
天才・武豊を背に、“完璧”という言葉が似合う無敗の三冠馬。
日本中の期待を背負い、世界1番人気で凱旋門賞に挑んだ。
しかし、後にまさかの失格処分――。
“世界の頂点”を目前に夢が打ち砕かれたが、それでもディープは世界に「日本競馬の美しさ」を知らしめた。
その走りは、今もなお語り継がれる“永遠の伝説”。
ナカヤマフェスタ(2010年)
「欧州を驚かせた、無名の挑戦者。」
気性の荒さで知られた“じゃじゃ馬”が、誰も予想しなかった快走を見せた。
現地の前哨戦・フォワ賞を勝ち、「ただの遠征馬」から「本物」へ。
本番ではブレーメンのような執念の走りでエルコンドル以来の2着。
静かな騎手・柴田善臣とともに、名もなき挑戦者が世界を驚かせた日だった。
オルフェーヴル(2012・2013年)
「完璧だったはずの走り。運命に選ばれなかった天才。」
新馬戦で池添謙一を振り落とした荒々しい若駒が、後に史上7頭目の三冠馬へ。
菊花賞では“手綱が切れそうな走り”で圧勝。
だが、その天才が本気を見せたのは、欧州の地だった。
2012年の凱旋門賞、残り100mで先頭独走。実況は叫んだ――
「日本馬が勝つ!」
しかし、ソレミアが外から差し切り2着。
翌年の再挑戦も、女傑トレヴの怪物的な末脚に屈した。
「世界一強くて、世界一運がなかった馬」。それがオルフェーヴルだった。
ハープスター(2014年)
「桜の女王、ヨーロッパを駆け抜ける。」
桜花賞では最後方から全馬を抜き去り、まるで風が走るような末脚で栄冠を掴んだ“桜の女王”。
ドバイや宝塚での挑戦を経て、満を持して凱旋門賞へ。
しかし、その年のロンシャンは極悪の馬場。
得意の切れ味が生かせず6着に終わる。
それでも海外メディアは称えた。
「彼女は小柄だが、心は誰よりも勇敢だった」。
日本牝馬の新しい扉を開いた、華と強さの象徴。
ゴールドシップ(2014年)
「愛すべき“暴君”が見た、最後の夢。」
宝塚記念ではまさかの大出遅れから怒涛の追い込みで勝利。
気まぐれで、破天荒で、それでも強かった芦毛の怪物。
凱旋門賞でもファンの期待を背負ったが、馬場と気性が噛み合わず完敗。
それでも「行くぞ!」と叫ぶ横山典弘の手綱に応えようとする姿は、ファンの涙を誘った。
“走る気まぐれ王”は、ロンシャンでも変わらず彼らしいままだった。
タイトルホルダー・ドウデュース(2022年)
「令和の夢、再び。」
黄金世代の2頭が挑んだ、令和の凱旋門賞。
タイトルホルダーは日本の最強ステイヤーとして、ドウデュースはダービー馬として。
だが、ロンシャンは豪雨。まるで日本馬を拒むかのような重馬場。
完敗だった。それでも拍手が起きた。
クロワデュノール(2025年)
「令和のダービー馬、再び世界へ。」
2025年、ついに再び“夢の扉”が開く。
日本ダービーを制し、欧州前哨戦でも好走。
エルコンドル、オルフェーヴルの後を追うように、静かにロンシャンへと向かう。
日本競馬が半世紀かけて築いた挑戦の系譜、その最新章が始まろうとしている。
なぜ日本馬は凱旋門賞で勝てていないのか? 主な要因
凱旋門賞において日本馬が“あと一歩”で負けてきた理由には、幾つか共通する課題があります。
- 馬場適性と馬場変化
ヨーロッパの芝は日本とは構造が異なることが多く、湿り・重馬場などの変化に対応しきれない場合がある。 - 距離・ペース
2400mという距離、そして長丁場のレース運びは日本国内の平均ペースとは異なる。終盤の脚比べで差が出やすい。 - 輸送・長旅ストレス
日本からパリへの長距離輸送、気候変化、時差や環境の適応などが馬体や仕上げに影響する。 - 重量・体格差
欧州馬は大型馬が多く、パワー面で優位を持つケースもある。日本馬は比較的軽量なタイプが多く、レースの流れで押し切られやすい。 - 仕上げ・調整戦略
ヨーロッパ進出前の前哨戦選びや調整、現地慣れなど、戦術・戦略面での経験不足も影響。
「勝利への道筋」が進化している今
最近では、日本馬挑戦の戦略そのものが進化しつつあります:
- 現地重賞レースを事前に使う試験的遠征
凱旋門賞直前の「フォワ賞(Prix Foy)」などを使うのが定番になっており、日本の主要挑戦馬たちもこの流れを踏襲しています。 - 馬体・軽量化の追求
過去の経験から、軽量で仕上げた馬ほど有利とされ、それを意識した飼育・育成が注目されています。 - 欧州適応型育成・血統研究
欧州芝適性を持つ血統を重視する動きが強まっており、遠征馬の選定基準も変化しています。 - 現地滞在と調整
長期現地滞在して馬を順応させる、現地ゲート試験や追い切りを重ねてフィットさせる戦術も増えています
なぜ「凱旋門賞制覇」は日本の悲願なのか?
日本競馬は戦後、欧州に追いつけ追い越せの精神で育ってきました。
その象徴が凱旋門賞。
“サムライホース”たちが挑み続けるその姿は、日本人の努力・挑戦・執念の象徴でもあります。
技術も血統も世界トップクラスになった今、
「次こそ日本馬が勝つ」と言われるたびに、毎年世界中のファンが注目します。
まとめ
- 日本馬の挑戦は、50年以上にわたる“未完の夢”。
- 何度もあと一歩まで迫りながら、運命に阻まれてきた。
- しかし、挑戦の積み重ねこそが日本競馬を世界レベルに押し上げてきた。
「勝てなくても、挑戦をやめない。」
その姿こそ、日本競馬の誇り。



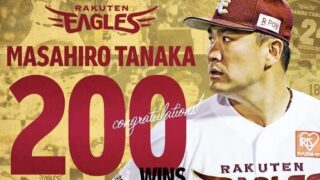




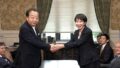
コメント