

まず「GDP(国内総生産)」とは、国内で1年間に生み出された“モノやサービスの価値の合計”のことです。
つまり、国の“経済力”を測るメインの物差し。
GDPが増える=みんなの給料や企業の売上が伸びている、GDPが減る=景気が冷えている、といった具合に、経済ニュースの中でよく登場します。
でも、ここで注意したいのが「名目」と「実質」の違いです。
名目GDPとは?──“そのままの値段”で見た経済の大きさ
名目GDPとは、
「その年の実際の物価(値段)」で計算したGDPのこと。
たとえば、2024年にリンゴが1個100円、1億個売れたら
名目GDPは100円 × 1億個 = 100億円です。
翌年、同じ1億個でもリンゴの値段が120円になったら、名目GDPは 120億円になります。
でも──
「売れた量」は同じなのに、値段が上がっただけでGDPも増えたように見える。
これが名目GDPの弱点です。
つまり名目GDPは、“値上がり分(インフレ)”も含んでいるんです。
実質GDPとは?──“物価の影響を取り除いた”本当の成長
そこで登場するのが「実質GDP」。
これは、物価変動(インフレやデフレ)を差し引いたGDPのこと。
言い換えれば、「モノやサービスの“量”がどれだけ増えたか」を見る指標です。
さっきの例でいえば、リンゴの値段が100円→120円に上がっても、
売れた量が同じなら実質GDPは変わりません。
つまり、実質GDPは「見かけの値上がり」を除いた“本当の成長”を示します。
名目と実質の関係を一言で言うと?
🧮 名目GDP = 実質GDP × 物価指数(デフレーター)
この式が示すように、
名目GDPは「価格も数量も含めた合計」、
実質GDPは「数量の変化だけ」を見るものです。
なので、物価が上がると名目GDPは伸びやすくなり、
逆にデフレ(物価下落)のときは伸びにくく見えます。
なぜ政府は「名目GDP」を重視し始めたのか?
最近の日本政府(特に高市政権)は、「名目GDP」を重視する姿勢を強めています。
理由はシンプルで、名目GDPが増える=税収が増える=財政が動かしやすくなるからです。
さらに、円安やインフレで名目GDPが自然に増えれば、
「政府債務のGDP比」が下がって見える効果もあります。
つまり、見た目上の“財政健全化”が進んでいるように見える。
このため最近の経済ニュースでは、「名目GDP成長率」が注目されるのです。
名目GDPと実質GDP、どちらが大事?
結論から言うと──
どちらも重要。目的によって使い分けが必要です。
| 見たいこと | 使うGDP | 例 |
|---|---|---|
| 経済の“体感的”な大きさ(税収・債務比など) | 名目GDP | 政府・財務省の分析 |
| 実際の“成長力”や生産性 | 実質GDP | 日銀や内閣府の景気分析 |
たとえば、「経済が拡大した」と言っても、
それが“値段が上がっただけ”なら生活は豊かになっていません。
逆に、物価が安定していても生産が増えていれば、実質的には成長しています。
まとめ:名目と実質を見比べるのが、ニュースを読むコツ
- 名目GDP → 値段込みの“見かけの成長”
- 実質GDP → 物価を除いた“本当の成長”
どちらが正しい、というより、
両方をセットで見ることで経済の本当の姿が見えるのです。
次にニュースで「名目GDPが過去最高」と出たら、
「でも実質はどうなの?」と一歩踏み込んで考えてみてください。
その視点こそが、“経済を読む力”です。
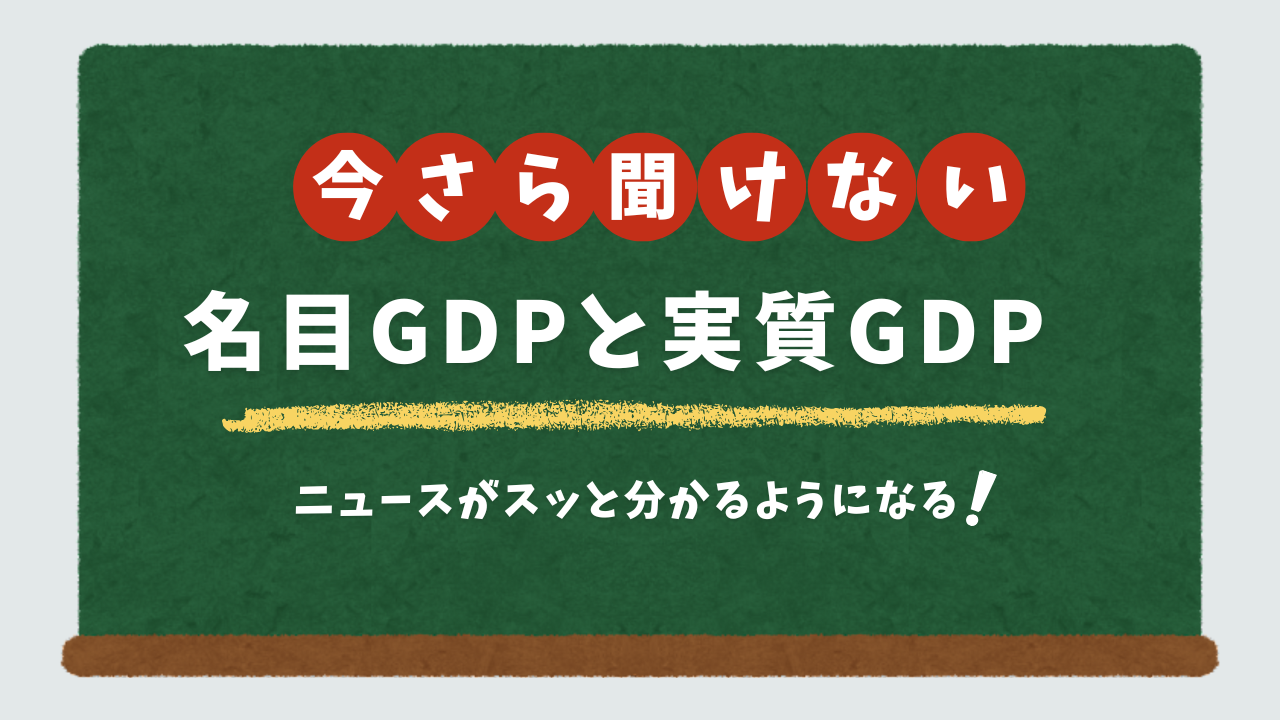




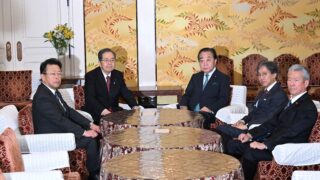

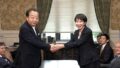

コメント