2025年7月20日に投開票される第27回参議院議員通常選挙では、全国で激しい選挙戦が展開されています。
しかし、「参議院と衆議院の違い」や「比例代表と選挙区制の違い」など、選挙制度について実はよく知らないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、参議院選挙の基本制度をわかりやすく解説します。
“なんとなく”ではなく、納得して一票を投じたいという方に向けた選挙ガイドです。


【参議院と衆議院の違い】
日本の国会は、憲法第42条で「衆議院」と「参議院」の2つからなる「二院制」を採用しています。二院制には以下のような意味があります。
- 民意を多角的に反映できる
- 一方の暴走を抑える「抑制と均衡」機能
- 慎重な審議が可能になる
参議院議員の任期は6年で、衆議院のような「解散」はありません。そのため、3年ごとに半数(124議席)が改選されます。これに対し、衆議院議員の任期は4年で、解散もあるため「総選挙」として一度に全議席を争います。
衆議院は任期が短く(4年)、解散もあるため、民意の反映が強いとされ、重要な場面で最終決定権を持つしくみで、衆議院の優越が以下の場合認められています。
① 法律案の議決(憲法第59条)
・両院で異なる議決 → 衆議院が再可決すれば成立(出席議員の3分の2以上)
② 予算の議決(憲法第60条)
・衆議院が審議 → 参議院が30日以内に議決しなければ、衆議院の議決が国会の議決になる
③ 条約の承認(憲法第61条)
・衆議院が先議 → 参議院が30日以内に議決しなければ、衆議院の議決が国会の議決になる
④ 内閣総理大臣の指名(憲法第67条)
・両院で異なる人を指名 → 衆議院の指名が優先される
改選議席数(2022年に当選した議席が今回改選)
改選議席数が最も多いのは 自民党(52席)
続いて 立憲民主党(22席)、公明党(14席)、共産党(7席)が多数を占めます。
| 政党名 | 改選議席数 |
|---|---|
| 自民党 | 52 |
| 公明党 | 14 |
| 立憲民主党 | 22 |
| 日本維新の会 | 5 |
| 日本共産党 | 7 |
| 国民民主党 | 4 |
| れいわ新選組 | 2 |
| 社会民主党 | 1 |
| 参政党 | 0 |
| 無所属 | 10 |
【参議院選挙の仕組み:選挙区制と比例代表制】
参議院の選挙制度は「選挙区制」と「比例代表制」の2つが併用され、有権者はそれぞれに投票します。
- 選挙区制
都道府県単位(鳥取・島根、徳島・高知は合区)の選挙で、候補者名を書いて投票し、得票数の多い順に当選します。 - 比例代表制(非拘束名簿式)
全国単位で、政党名か候補者名のいずれかを投票。政党が得た総得票に応じて議席が「ドント方式」で配分され、個人の得票数順で当選者が決まります。
※「特定枠」がある場合は、政党が優先した候補者がまず当選します。
- 各政党の得票数を「1、2、3、4…」と割る
- 割った結果(商)の大きい順に、議席を配分する
| 政党 | 得票数 | ÷1 | ÷2 | ÷3 |
|---|---|---|---|---|
| A党 | 100万票 | 100 | 50 | 33.3 |
| B党 | 60万票 | 60 | 30 | 20 |
| C党 | 40万票 | 40 | 20 | 13.3 |
→ 上から大きい値を選び、A党に多く、C党に少なく議席が割り当てられます。
【制度を知って納得の一票を】
参議院選挙は一見わかりにくい制度が多いように感じられますが、その仕組みには「多様な民意の反映」や「慎重な国政運営」といった目的があります。
どの政党・候補に投票するかだけでなく、その投票がどう国政に結びつくのかを理解することは、私たち有権者にとって重要な一歩です。
ぜひ、自分の未来を託す1票を考えてみましょう。


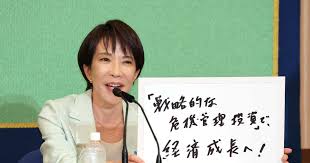
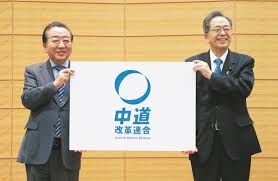

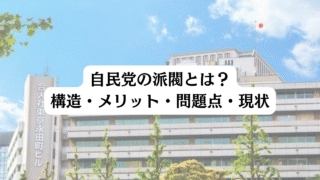



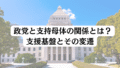
コメント