宅建試験の民法分野でつまずきやすいテーマのひとつが「代理制度」です。
「誰が何をした時に、その効果が誰に帰属するのか?」という構造を正しく理解すれば、得点源にもなり得ます。
今回は代理制度の基本を、3人の関係図をベースに、代理権・顕名・効果の帰属といったポイントを丁寧に整理していきましょう。
📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
代理制度とは?
代理とは、他人の行為によって自分が法的効果を受ける制度です。
通常は自分の契約行為で効果が自分に帰属しますが、代理では「他人の契約行為」で「本人に効果が帰属」します。
登場人物は3人!
- 本人:契約の効果を受ける人
- 代理人:本人の代わりに契約をする人
- 相手方:契約の相手となる第三者
代理の成立に必要な3要件
- 代理権があること
- 顕名をしていること(本人のための行為であると示す)
- 意思表示をしていること(契約の内容を伝える行為)
代理人が契約時に「これは本人のための行為です」と示すこと。
これをしないと、代理人自身が契約当事者とされてしまいます。
顕名がある場合の効果
・本人に効果が帰属します。
・たとえ代理人が第三者の利益のために行っていても、外見的に「本人のため」であれば有効。
顕名がないと?
・契約は代理人自身が当事者となり、本人には効果が及びません。
📝注意点:背信的な代理行為は、相手方がその事実を知っていたら無効になります。
代理権とは?
代理人が有効に代理行為を行うには「代理権」が必要です。
種類とポイント
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 任意代理 | 本人との契約により代理権が発生 |
| 法定代理 | 未成年や成年被後見人など法律上当然に発生 |
復任権(代理人が他人に任せる権利)とは?
代理人がさらに別の人(復代理人)を立てられるかどうかです。
| 種類 | 復任権 |
|---|---|
| 任意代理人 | 原則なし(例外:許諾・やむを得ない事由) |
| 法定代理人 | 原則あり |
※復代理人=代理人の代理ではなく「本人の代理人」!
任意代理の代理権が消えるタイミング
- 本人の死亡・破産・解除
- 代理人の死亡・破産・後見開始の審判
📝ポイント:未成年者でも代理人になれる。ただし、本人があとで「未成年だったから無効」とは言えません。
代理行為(代理人による意思表示)
代理人による意思表示が、本人の意思と同じように法的効果を生む行為のこと。
判断基準は「代理人」!
詐欺や錯誤などの「意思表示の瑕疵」がある場合は、代理人を基準に判断します。
たとえば、代理人が詐欺に遭って契約したら、その契約を取り消せるのは「本人」です。
例外ルール
- 本人が指示した内容で代理人が契約した場合、本人が知っていた事情は、代理人が知らなくても「知っていたもの」とされます。
- つまり、本人の「知らなかった」は通用しません。
まとめ:代理の基本は三角関係と3要件を押さえよう!
代理制度では、「誰が何をし、誰が効果を受けるのか?」を正しく理解することが最重要です。
以下のポイントを押さえて、出題されたら1点確保!
- 代理人に代理権があること
- 顕名していること(本人のために行う)
- 意思表示が適切であること
- 制限行為能力者でも代理人になれる(ただし効果は本人へ)
- 復任権・消滅事由・効果の帰属先も確実に整理
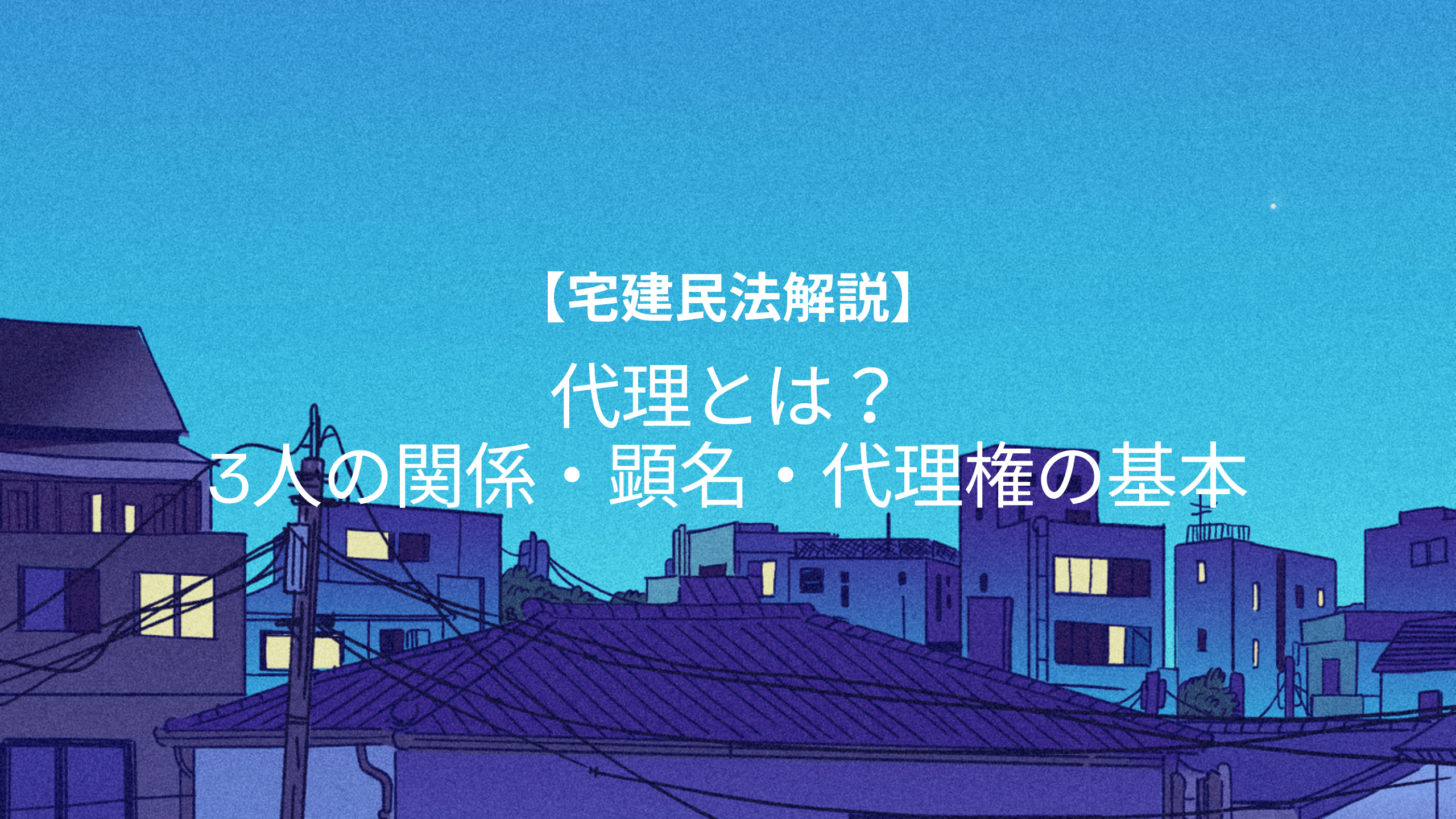

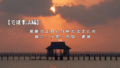


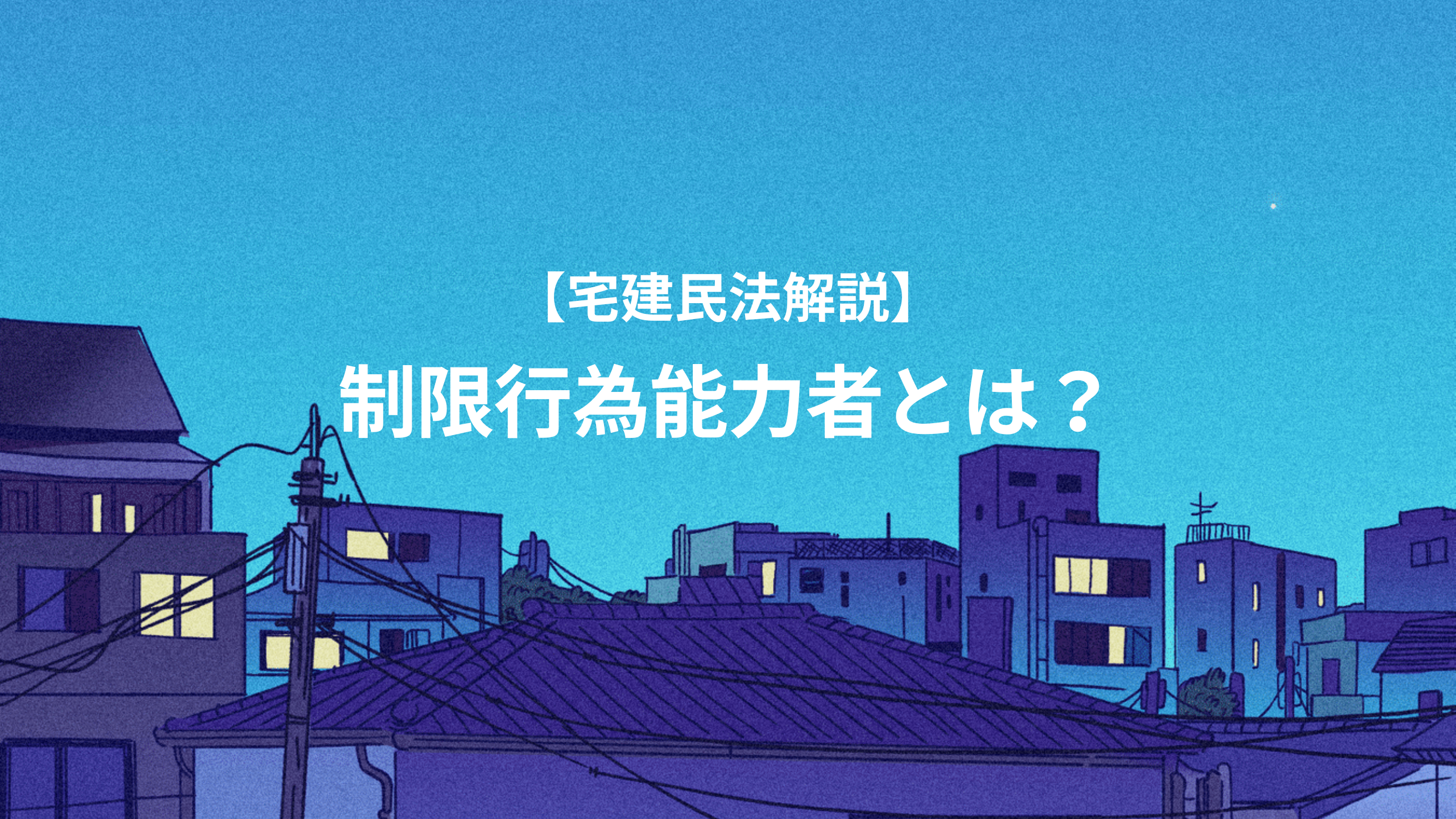



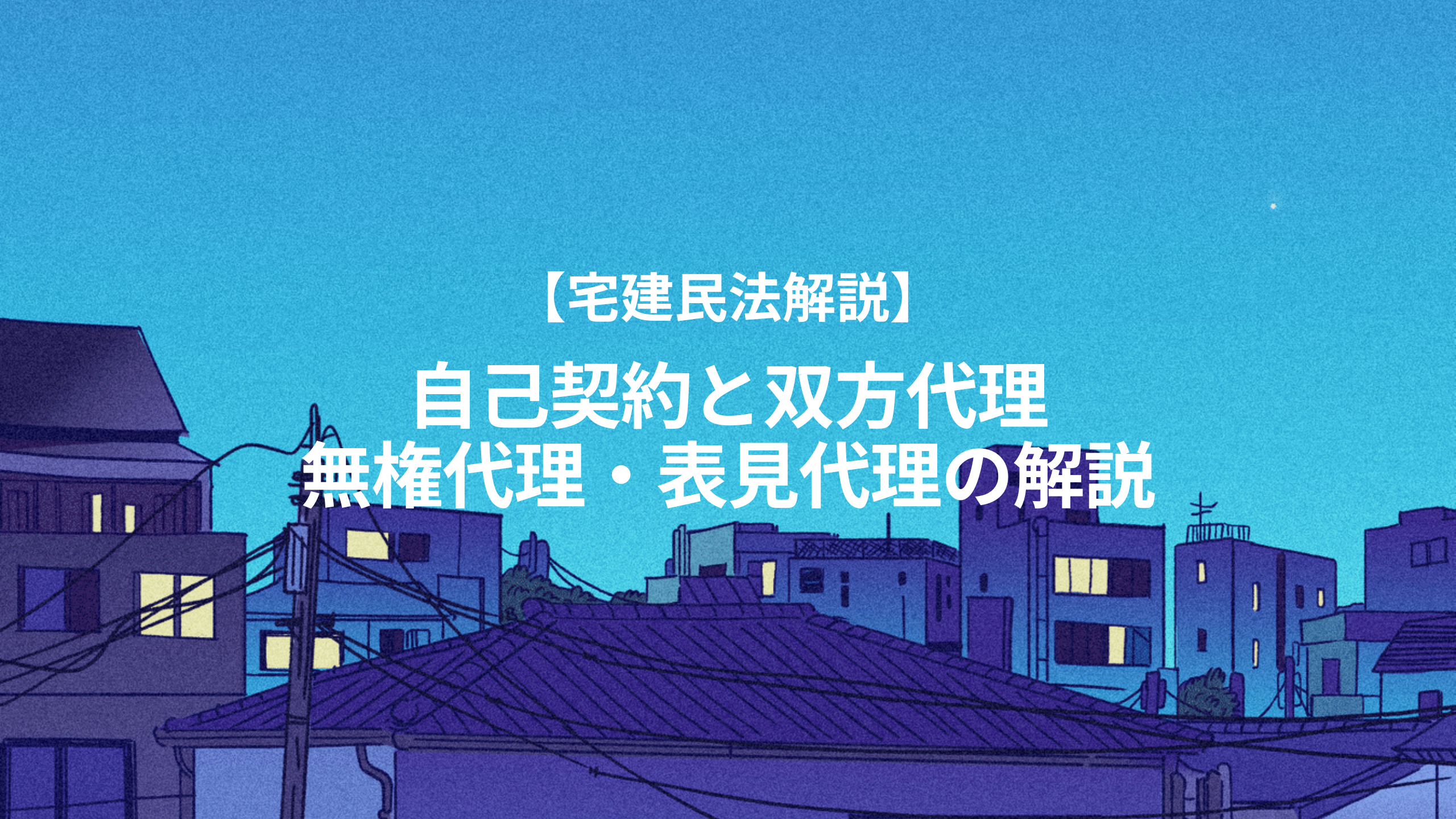


コメント