宅建試験で民法を学ぶ上で、契約の「意思表示」に問題があるとどうなるのか?という視点はとても重要です。
今回はその中でも「意思の不存在」に該当する3つのパターン——心裡留保・通謀虚偽表示・錯誤——について、それぞれの意味や契約への影響、第三者保護との関係性などをわかりやすく整理して解説します。
改正民法のポイントも含めて、しっかり理解しておきましょう。
📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
心裡留保(しんりりゅうほ)とは?
言葉では「契約します」や「売ります」と言いながらも、実は本心ではその気がない状態をいいます。たとえば、冗談で「100万円あげるよ」と言ったり、気乗りしないままサインをしたりと、いわば“冗談やポーズ”で示された意思表示のことです。
このように本心と違うことを言ったとしても、原則としてその契約は有効になります。つまり、「冗談だった」と後から言っても、相手が真に受けて契約を信じた場合は責任が生じる、ということです。なぜなら、民法では取引の安全を守るため、相手がその言葉を信じて行動した場合に契約の効果を認めているからです。
ただし、例外もあります。相手が、冗談だと知っていた(悪意)、または普通の注意をしていれば気づけたはず(重過失)の場合、その意思表示は無効とされます。つまり「そんなの冗談だって誰でもわかるでしょ」という場合は、契約は成り立たないとされるのです。
さらに、もしその契約に基づいて第三者が関わってきた場合(たとえば物を買い取ったり転売したりした人など)、その第三者が善意(=事情を知らなかった)であれば、「これは冗談だったから無効です」と主張することはできません。つまり、第三者との間では契約は有効とされます。
このように、心裡留保とは「本気でない意思表示」ですが、相手が信じた場合には有効になるという、言葉の重みに責任を持たせるルールです。契約における信用の保護が優先されていることを覚えておきましょう。
通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)とは?
当事者同士が示し合わせて、本当の意思ではない契約をわざと行うことをいいます。たとえば、AさんとBさんが売買契約を結んだように見せかけても、実際にはAは売る気がなく、Bも買う気がないというようなケースです。このような“見せかけの契約”は、当事者の合意があっても無効とされます。
ただし、問題になるのはこの契約に基づいて第三者が関わってきたときです。たとえば、何も知らないCさんがBからその物を買ってしまった場合、本来AとBの契約は無効ですが、Cさんが善意(=虚偽表示と知らなかった)であれば、契約は有効とされ、Cさんは守られます。AさんはCさんに「それは無効な契約だ」と言っても、物を取り戻すことはできません。
重要なのは、Cさんが注意を払っていれば気付けた(過失があった)場合でも、善意であれば保護されるという点です。つまり「知らなかった」だけで保護され、「うっかり気づかなかった」ことが責められることはありません。
さらにもう一歩進んで、CさんがDさんにその物を売った場合、少し複雑な話になります。
- Dさんが善意なら当然保護されます。
- しかしDさんが悪意(虚偽表示と知っていた)でも、Cさんが善意なら、やはりDさんは保護されます。
なぜ悪意のDさんまで守られるのかというと、Dさんの契約を無効にすると、善意のCさんが損をするからです。法律は、先に登場した善意の人(この場合はCさん)を守るために、やむを得ず後の悪意の人(Dさん)も保護するという立場を取っているのです。
このように、通謀虚偽表示においては、最初の契約は無効でも、第三者が善意であれば保護されるという点がポイントです。そして、「善意であれば過失があってもOK」「さらにその後の転売でも、元の買主が善意なら転売先も保護されることがある」という点を押さえておきましょう。宅建試験でも、意外とこのひねりのある論点が狙われます。
錯誤(さくご)とは?
「勘違い」によって間違った意思表示をしてしまうことをいいます。
たとえば、100万円で土地を売るつもりが、間違って10万円と書いてしまったり、建物付きだと思って契約したのに実は更地だった、というような場合です。
心裡留保や通謀虚偽表示との違いは、表意者自身がその勘違いに気づいていない点です。つまり、「真意ではないと知っていて表現した」のではなく、「本当にそうだと思って言ってしまった」ケースです。
錯誤による意思表示が取り消せるための2つの条件
- 重要な錯誤であること
契約の中でも特に大事な部分(=法律行為の目的・社会通念上重要な点)についての勘違いであること。 - 表意者に重大な過失がないこと
うっかりミス程度ならOKですが、注意すればすぐ気づくようなミス(=重大な過失)があると、原則として取消しはできません。
ただし、次のような場合には重大な過失があっても取消可能です:
- 相手方が錯誤を知っていた(悪意)か、重過失で知らなかった場合
- 相手方も同じ錯誤に陥っていた場合(双方錯誤)
錯誤と第三者の関係(保護の要件)
錯誤によって契約が取り消されると、次に出てくる「第三者」の利益が問題になります。
- 心裡留保や虚偽表示の場合:第三者は善意であれば保護される
- 錯誤の場合:第三者は善意かつ無過失でなければ保護されない
つまり、錯誤では表意者があまり悪くない(責められない)ため、その分第三者の側により高い注意義務が課されるのです。
改正民法のポイント
- 従来の「要素の錯誤」という言葉は使われなくなり、「取引上の社会通念に照らして重要なもの」という言い回しに変更。
- また、「動機の錯誤」(例:場所を間違えて申し込んだ等)も、法律行為の目的として重要であれば取消しが可能とされ、条文で明確に認められました。
意思の不存在|比較表(心裡留保・通謀虚偽表示・錯誤)
| 項目 | 心裡留保 | 通謀虚偽表示 | 錯誤 |
|---|---|---|---|
| 定義 | 本心と違う意思表示を1人で行う(冗談など) | 相手と通じてウソの意思表示をする | 勘違いや言い間違いなど、自分で気付いていない誤り |
| 効果(原則) | 原則 有効(冗談でも契約は成立) | 無効 | 取消可能 |
| 無効・取消の条件 | 相手が「冗談だと知っていた・気づけた」場合無効 | お互いに虚偽だと知っている場合は無効 | ・重要な錯誤であること ・表意者に重大な過失がないこと |
| 第三者保護 | 善意なら保護(過失は問わない) | 善意なら保護(過失は問わない) | 善意「かつ」無過失の第三者のみ保護 |
| ポイント | 自分だけが本気でない | 相手とグルで本気でない | 勘違いだから基本的に表意者を保護 |
まとめ:心裡留保・通謀虚偽表示・錯誤について理解しよう
契約においては、当事者の意思表示が正しくされていることが大前提です。しかし実際には、冗談だったり、通謀による偽装、あるいは単なる勘違いによって契約がなされることもあります。
本記事で扱った「心裡留保」「通謀虚偽表示」「錯誤」はいずれも、表面的には意思表示があるように見えて、内実が伴っていない「意思の不存在」に関わる重要な論点です。
それぞれの効果や第三者への影響は異なり、民法の理解と宅建試験の得点アップには不可欠な知識です。特に改正民法で明文化された錯誤の範囲や、第三者保護の条件などは要チェック。
基本をしっかり押さえて、応用問題にも対応できる理解を目指しましょう。
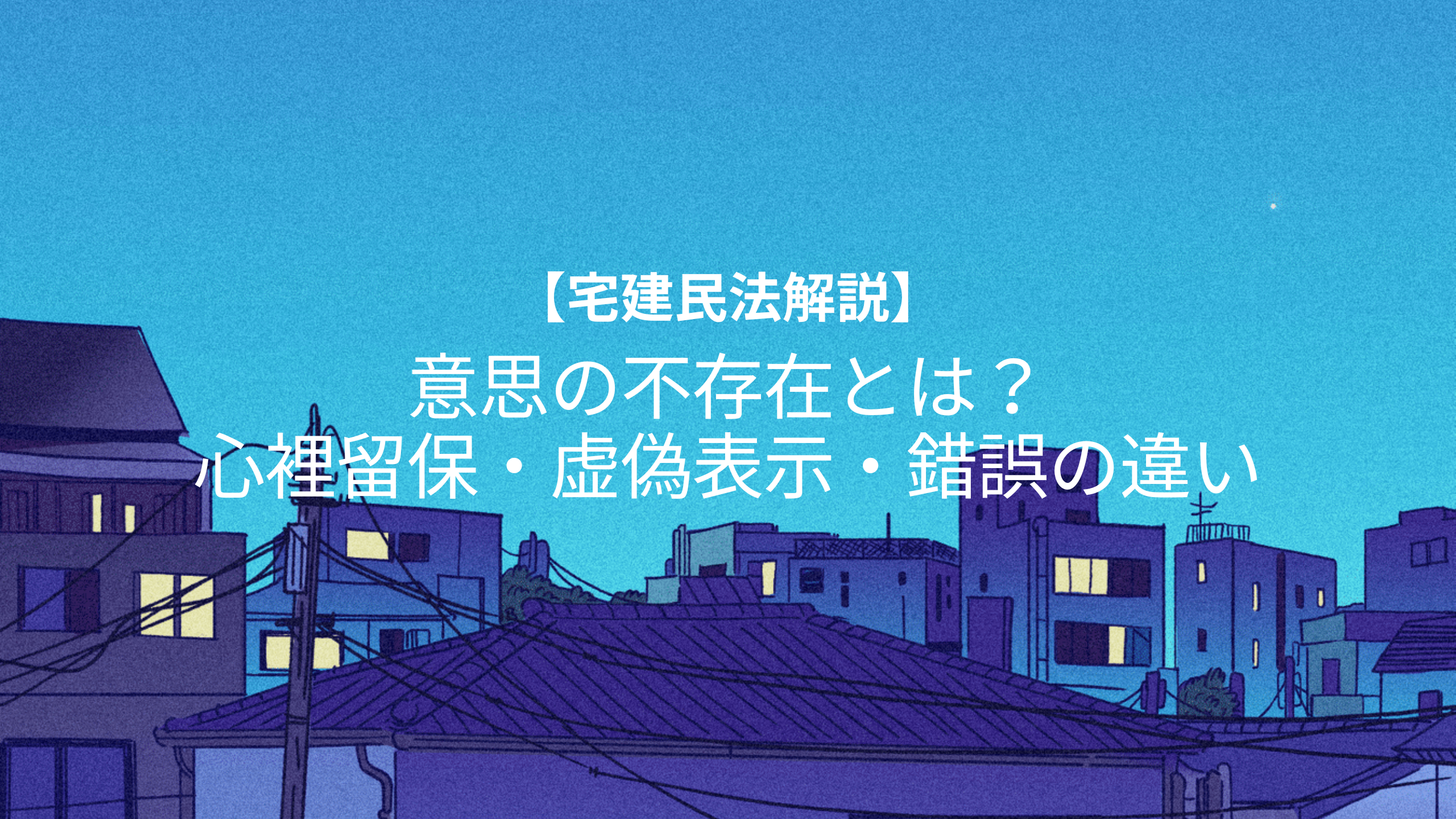

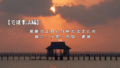


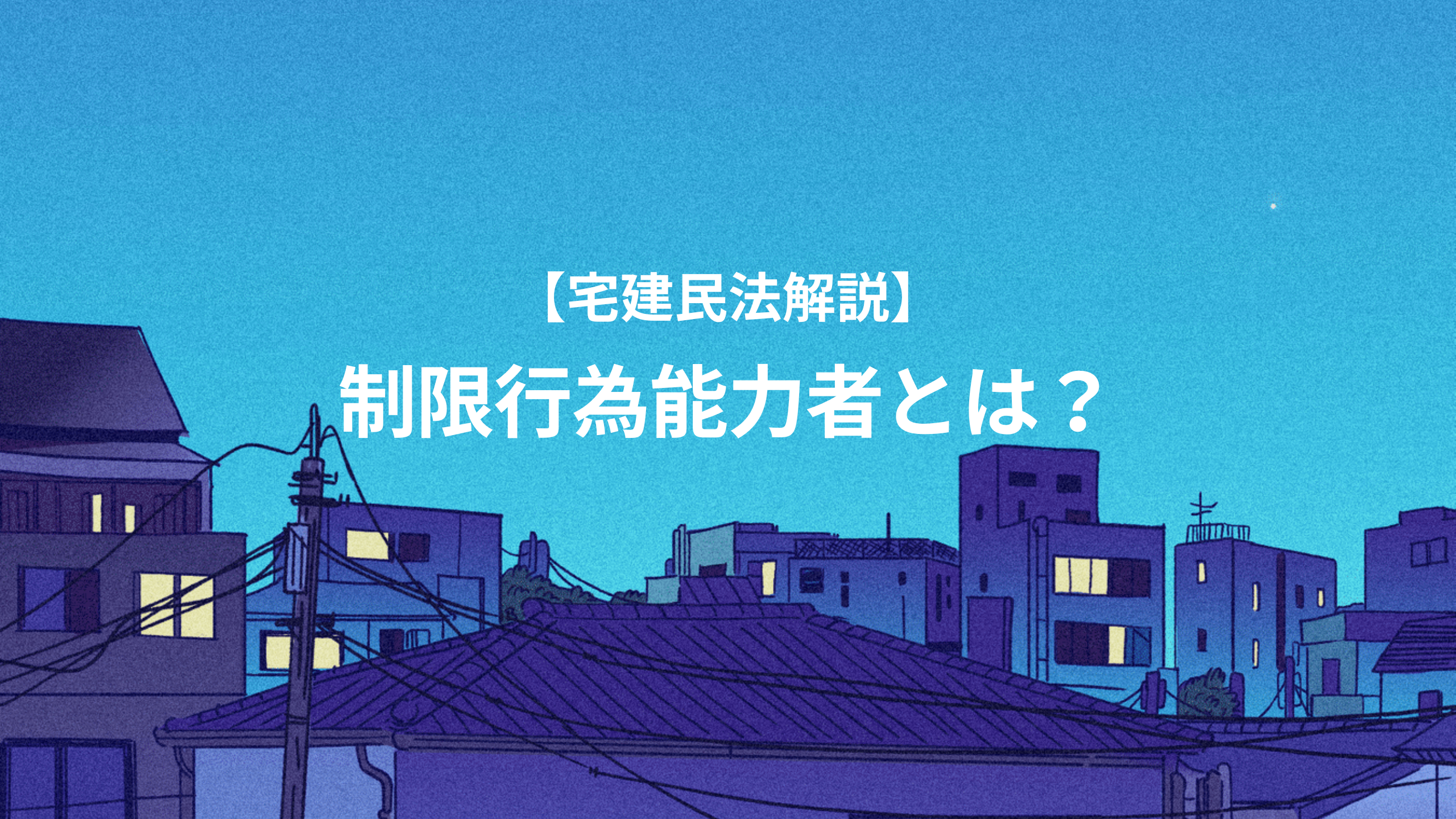


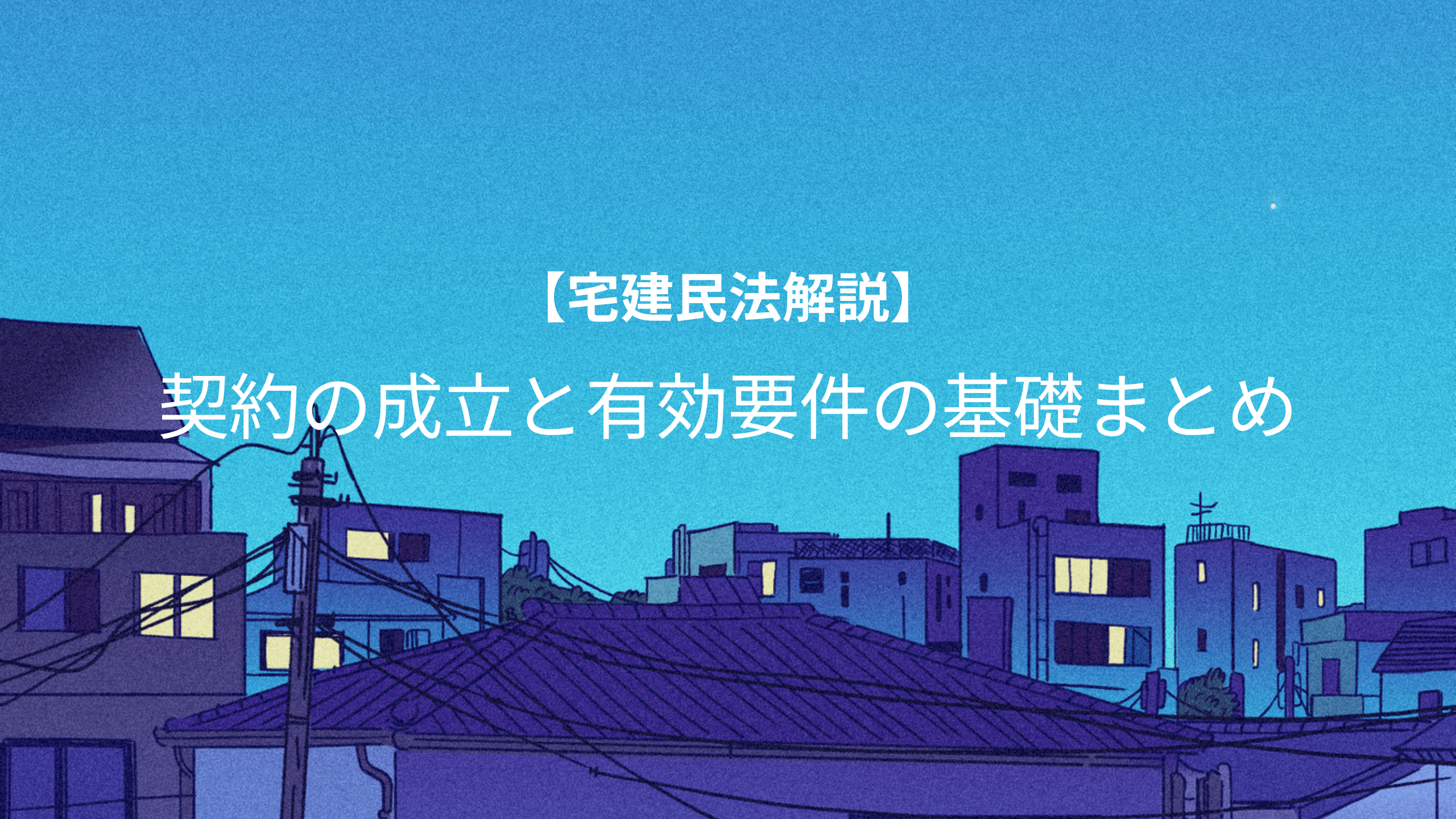
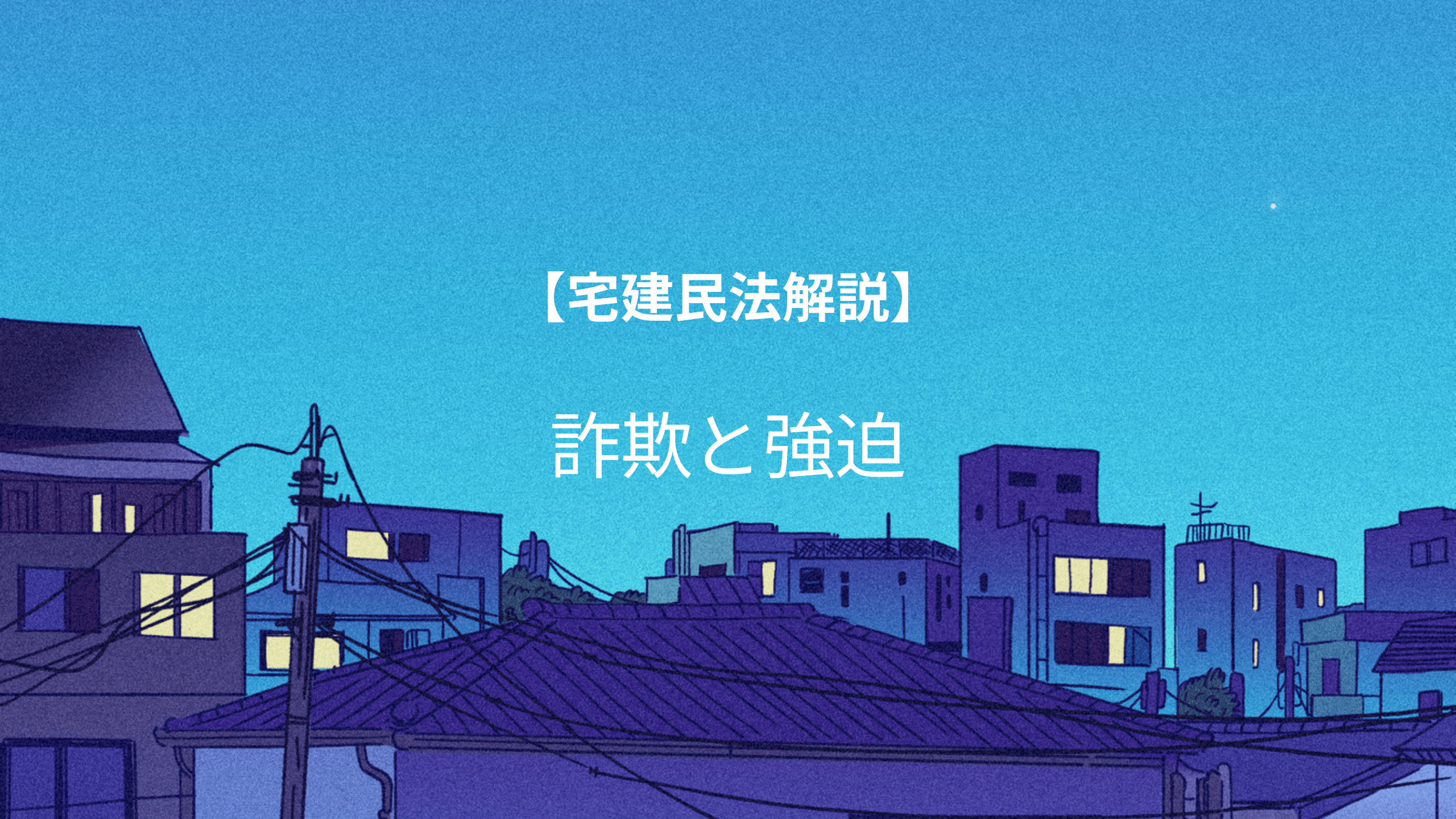
コメント