宅建業者が受け取れる報酬には、法律で上限(報酬限度額)が定められています。 計算ミスやひっかけを防ぐには、基本ルールと例外を整理して覚えるのが最重要です。
📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
¥3,300 (2025/06/19 14:22時点 | Amazon調べ)
報酬の基本ルール
- 自由な報酬設定は不可(上限あり)
- 依頼者に請求できるのは報酬のみ
- 経費請求NG(ただし特別広告費など依頼者が同意した場合はOK)
売買・交換の媒介・代理の報酬
基本計算式(課税事業者)
| 代金額の部分 | 計算率 |
|---|---|
| 200万円以下 | 5.5% |
| 200万円超~400万円以下 | 4.4% |
| 400万円超 | 3.3% |
📌 覚え方:3段階式 + 加算型
- 200万以下:5.5%
- 200万超400万以下:4.4%
- 400万超:3.3%
簡易計算式(合算表示)
- 400万超の場合:代金額×3.3%+66,000円
(免税事業者は×3.12%+62,400円)
重要なルール
| ケース | ルール |
|---|---|
| 買主・売主両方から媒介依頼を受けた場合 | 一方からの上限×2まで受領可 |
| 交換契約の媒介 | 価額差がある場合は高い方を基準に計算可 |
| 売買・交換の代理 | 媒介の上限×2まで受領可(ただし一方のみから) |
| 代理+媒介で双方から報酬受領 | 合計は代理報酬上限まで、一方ずつの制限も守ること |
貸借(賃貸)の媒介・代理の報酬
原則(課税事業者)
| 契約タイプ | 限度額(合計) |
|---|---|
| 媒介 | 借賃の1ヶ月分×1.1(免税:×1.04) |
| 代理 | 借賃の1ヶ月分×1.1(同上) |
居住用建物(特例あり)
| 条件 | 一方からの上限 |
|---|---|
| 承諾なし | 借賃の0.55ヶ月(免税:0.52) |
| 承諾あり | 借賃の1.1ヶ月以内なら柔軟に配分可 |
権利金がある場合(※居住用以外)
- 権利金が返還されない ⇒「売買代金」とみなして報酬計算可
- その報酬額と、借賃1ヶ月分×1.1の高い方を上限とする
📌 例:権利金2,000万円 ⇒ 2,000万×3.3%+66,000=726,000円
これを両当事者から受領可能 ⇒ 最大合計145万2,000円
よくあるひっかけ&注意点
| 落とし穴 | ポイント |
|---|---|
| 課税事業者/免税事業者で率が違う | 出題文に注目して見落とさない |
| 権利金が「返還される」場合 | 売買代金とみなして計算できない |
| 居住用建物の媒介 | 片方から多く取るには承諾が必要 |
| 双方代理の報酬合計 | 一方代理の上限を超えてはNG |
🎯 試験対策まとめ
| 分類 | ポイント |
|---|---|
| 売買・交換媒介 | 上限:3.3%+66,000円(400万超)/両方から受領可(×2) |
| 売買・交換代理 | 上限:媒介の×2(依頼者一方のみ) |
| 賃貸媒介 | 原則:1.1ヶ月分まで(承諾なければ0.55) |
| 賃貸代理 | 1.1ヶ月分まで(両者合計で) |
| 権利金 | 非居住用&返還なし → 売買代金扱いで計算 |
計算式・承諾の有無・免税/課税事業者の違いを整理すれば、得点源!
ひっかけ問題も多い分野なので、過去問で数値の感覚を掴んでおきましょう。
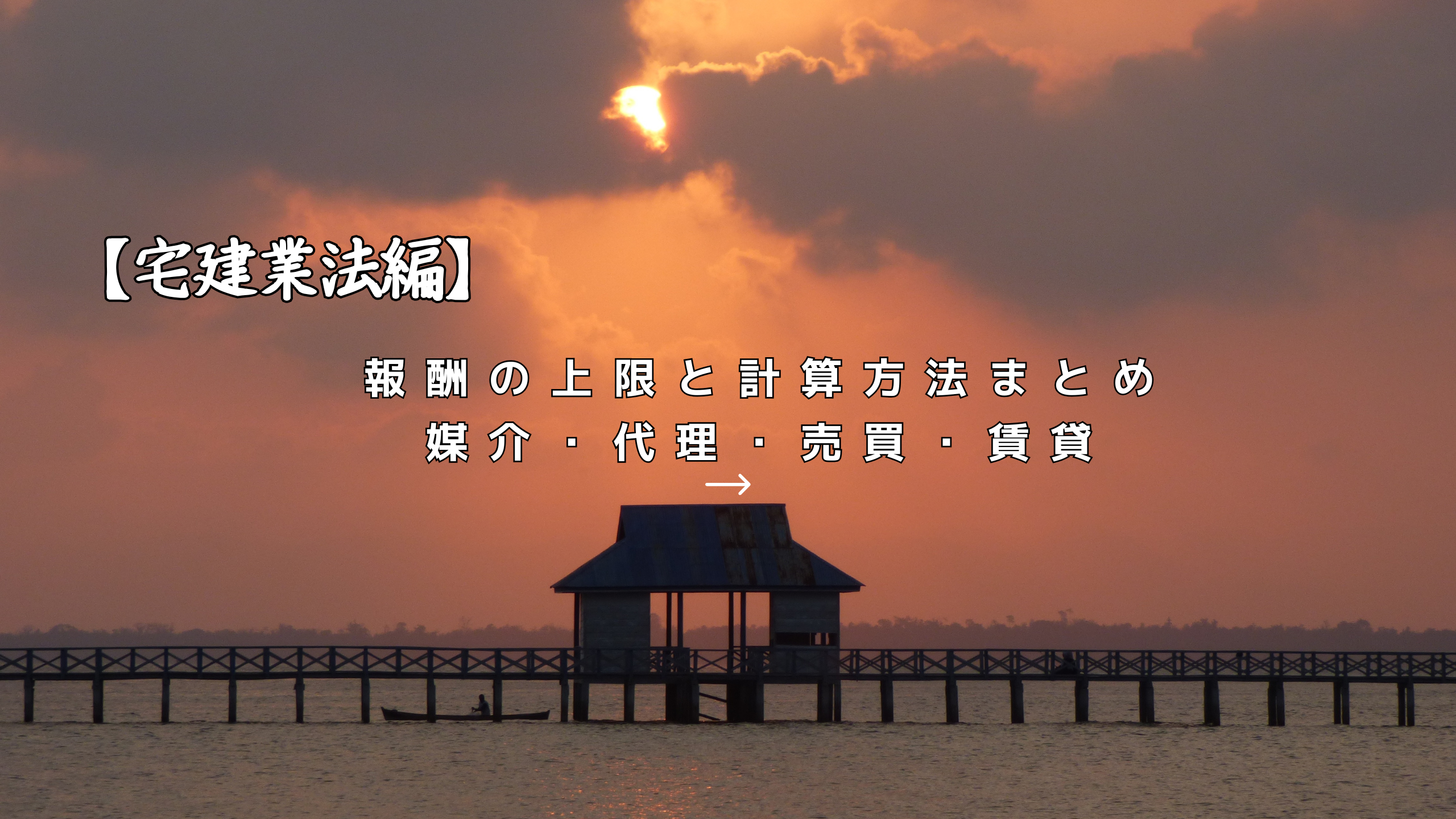

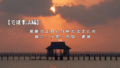


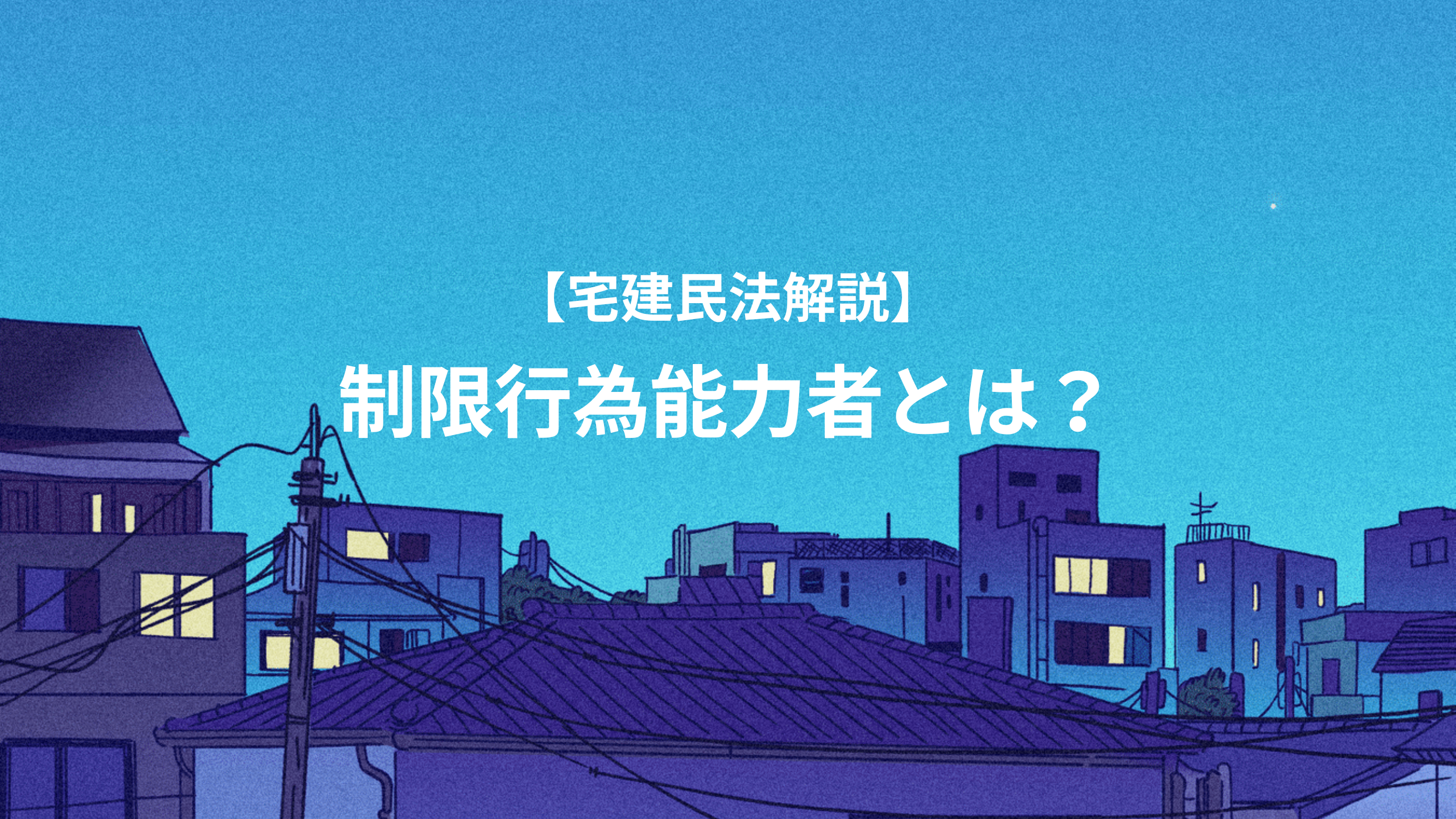






コメント