宅建試験では、民法の中でも「保証」に関する出題が頻繁に見られます。保証とは、債務者(主たる債務者)が約束を果たさないときに、代わりに責任を負う制度のこと。たとえば、アパートの賃貸借契約における「連帯保証人」など、実務でもよく登場する概念です。
保証契約はただの「お手伝い」ではなく、法律上の立派な契約。保証人にはどんな義務があるのか?連帯保証人との違いは?極度額の定めがないと無効になるって本当?こうした重要ポイントを押さえておくことが、合格への近道です。
この記事では、「保証」の基本から、連帯保証や保証契約の方式・要件、そして改正民法で強化された保証人保護ルールまで、試験に出やすいテーマを丁寧に解説していきます。
📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
保証債務とは
債務者が借金などの債務を履行しないとき、第三者である保証人が代わって債務を履行する制度です。保証人が負う債務を「保証債務」と呼びます。保証は主たる債務に従属する性質を持っており、法律上の制限や効力も試験で頻出です。
保証債務の成立
保証債務は、債権者と保証人の契約によって成立します。
主たる債務者の承諾は不要で、契約当事者は債権者と保証人のみです。
保証契約は、書面で行うことが民法で定められています。
保証人となるための要件
原則、誰でも保証人になれますが、債務者に保証人を立てる義務がある場合は以下の条件が必要です:
- 行為能力者であること
- 弁済資力を有すること
契約締結後に条件を満たさなくなっても、契約時点で要件を満たしていれば契約自体は有効です。
保証債務の性質
保証債務には3つの重要な性質があります。
附従性
- 主たる債務が成立しないと保証債務も成立しない
- 主たる債務が消滅すると保証債務も消滅
- 主たる債務の内容に保証債務も従う
随伴性
- 債権が譲渡されると、保証債務も新しい債権者に移る
補充性
- 保証債務は、主たる債務者が履行しないときの補完的義務
- 保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」がある
保証債務の注意点
- 主たる債務者が破産や行方不明なら催告の抗弁権は使えない
- 債権者が主たる債務者と保証人に同時に請求した場合も抗弁できない
- 弁済資力は全額でなく一部あればOK
連帯保証とは
連帯保証とは、通常の保証と違い、主たる債務者とまったく同じように責任を負う保証のことです。つまり、債権者(お金を貸した側)は、債務者本人に請求する前に、いきなり連帯保証人に全額請求することができます。
たとえば、AさんがBさんからお金を借りるとき、Cさんが連帯保証人になった場合、BさんはAさんに請求せずに、Cさんにいきなり全額を請求することができるのです。
連帯保証契約の特徴
- 契約で「連帯して保証する」旨の明記が必要
⇒ 文言がないと通常の保証とみなされる - 債権者は連帯保証人に直接請求可能
⇒ 支払い督促や裁判も、債務者を飛ばしてできる - 債務者が破産しても連帯保証人の責任は残る
⇒ 主債務が消えるわけではない
連帯保証人になるリスク
連帯保証人になると、以下のようなリスクが生じます:
- 債務者が逃げたり支払不能になった場合、自分が全額支払うことになる
- 相続人も連帯保証人の義務を引き継ぐ可能性がある(限定承認・相続放棄しない限り)
- 一度連帯保証契約をすると、原則として解除できない
したがって、安易に連帯保証人になるのは非常に危険です。試験ではこの“重い責任”の理解が問われます。
保証と連帯保証の共通点
- 契約当事者は債権者と連帯保証人
- 附従性・随伴性がある
- 保証人の資格要件も同じ
保証と連帯保証の違い
| 項目 | 保証 | 連帯保証 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | あり | なし |
| 検索の抗弁権 | あり | なし |
| 分別の利益 | あり(共同保証のみ) | なし |
| 責任の重さ | 軽い(補助的) | 重い(主たる債務者と同等) |
| 強制執行の可否 | 主たる債務者への請求後 | いきなり保証人へ可能 |
連帯保証人に生じた効力と主債務者への影響
以下の事由が発生すると、主たる債務にも効力が及びます。
- 弁済(債務の履行)
- 更改(契約の切替)
- 相殺(債権と債務の打消し)
- 混同(同一人物が債権者と債務者)
一方、連帯保証人の承認だけでは主たる債務の時効には影響しませんが、主たる債務者の承認は連帯保証人にも時効更新などの効力が及びます。
まとめ
保証債務は主たる債務に従属する補完的な制度で、保証人には抗弁権が認められます。一方、連帯保証は主たる債務者と同等の責任を負うため、より重大な法的責任を伴います。宅建試験では両者の違いや法的性質の理解が重要です。
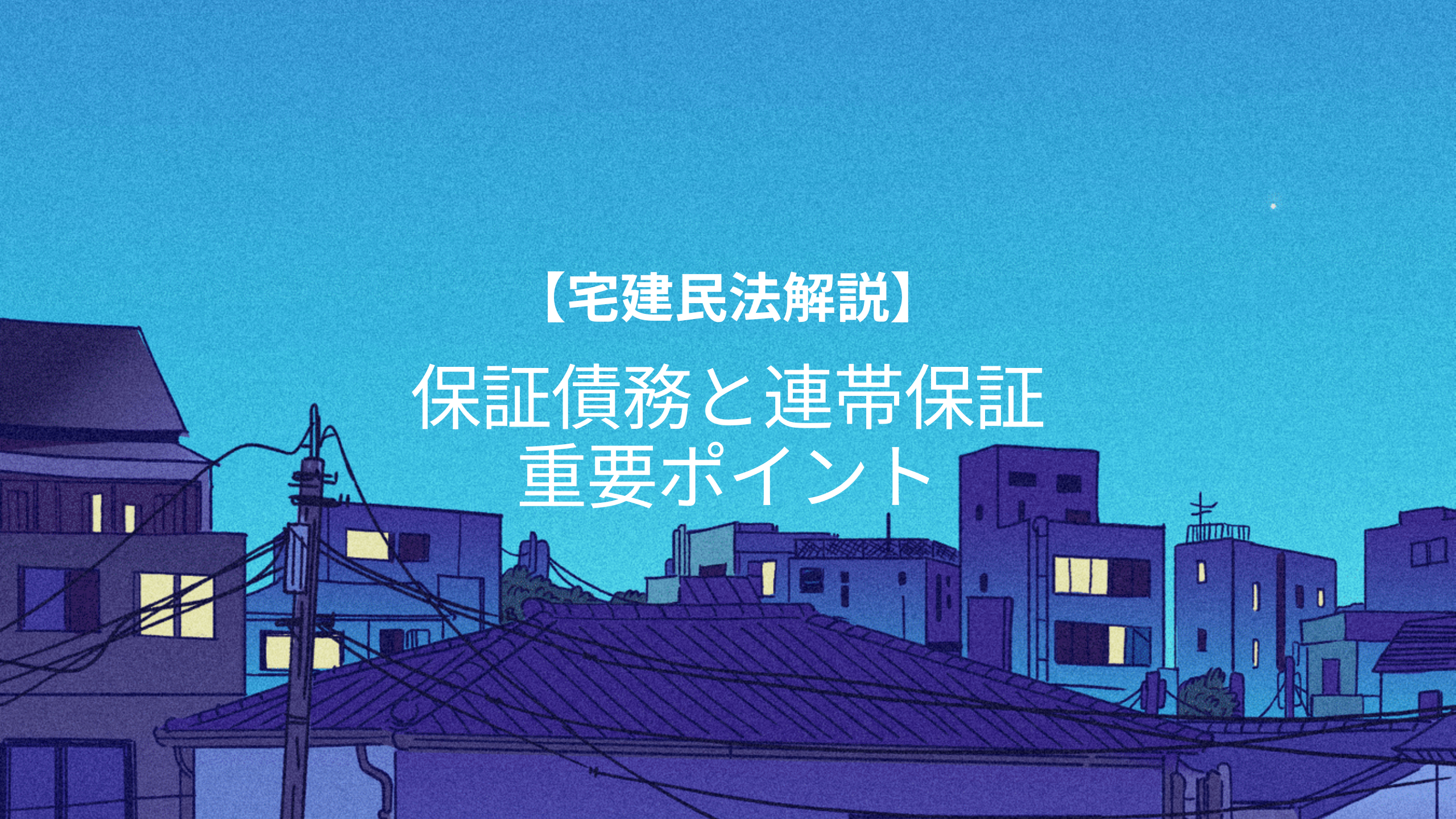

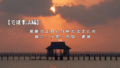


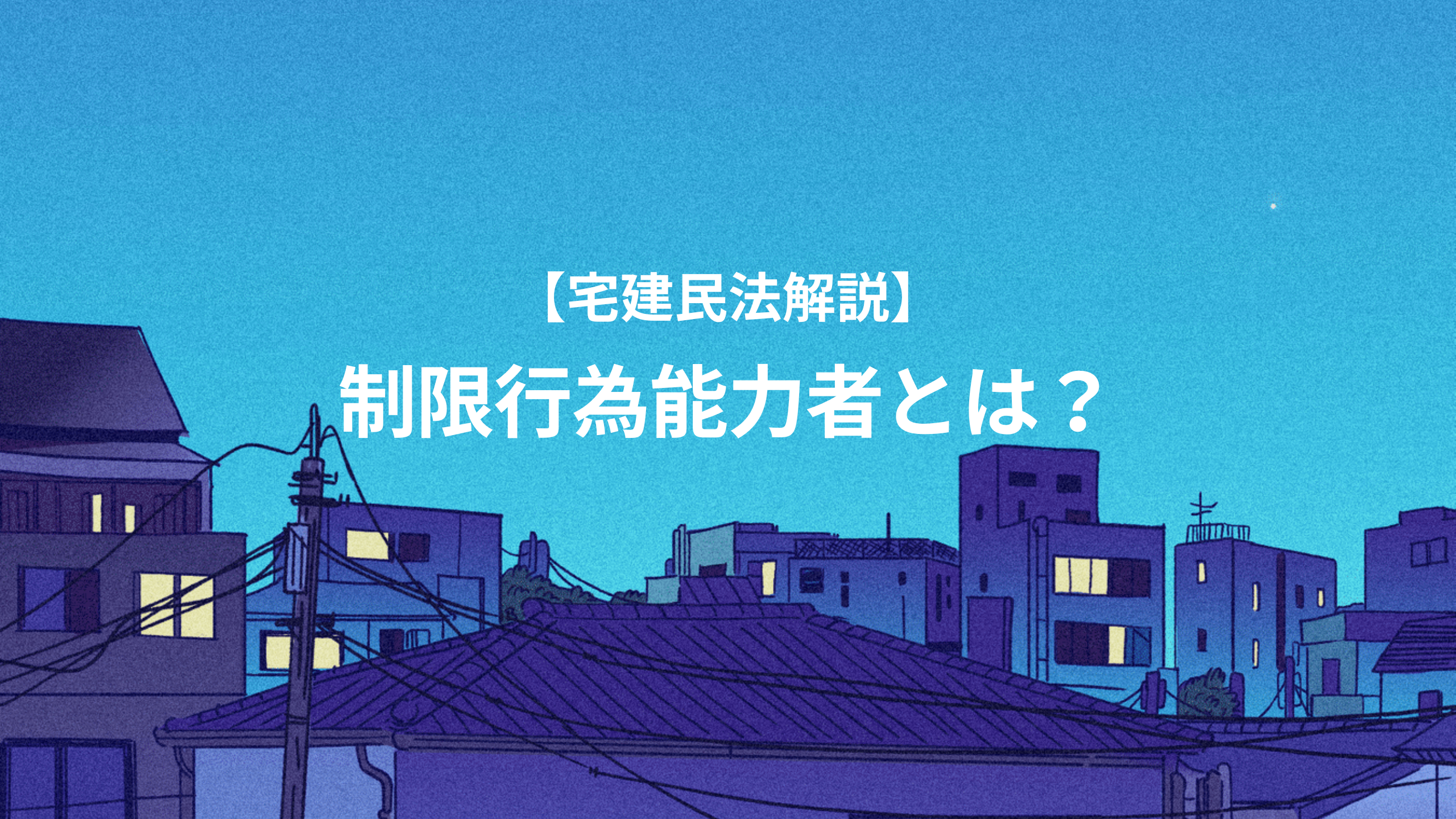


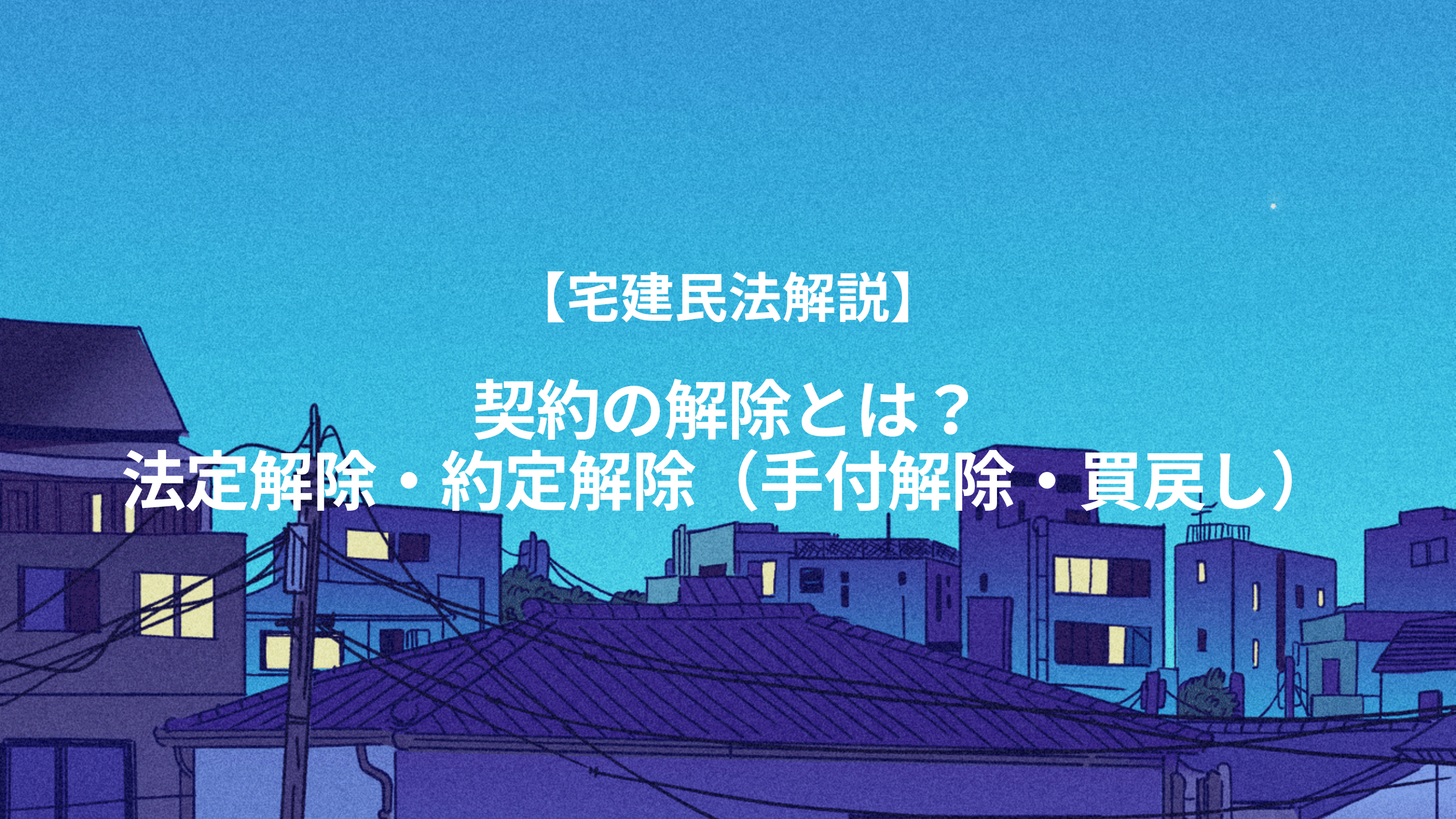

コメント