債務不履行とは、契約などによって生じた義務を果たさないことを指します。宅建試験では、債務不履行の3つの類型(履行遅滞・履行不能・不完全履行)や、それに伴う損害賠償請求、契約解除の可否について出題されます。
この記事では、それぞれのポイントをわかりやすく整理し、試験対策として役立つ知識を解説します。
📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
債務不履行とは
債務不履行とは、契約などに基づく義務(債務)を、正しく履行しないことを指します。
たとえば、売買契約で代金を払わない、引き渡しが遅れるなどが該当します。宅建試験では、債務不履行の種類や、それに基づく損害賠償の要件、解除の可否などが問われます。しっかり理解しておくことが重要です。
債務不履行には大きく分けて以下の3つのパターンがあります。
履行遅滞
債務者が、履行期を過ぎても義務を果たさない場合です。例えば、「8月1日までに商品を届ける」と約束したのに、期日を過ぎても届かないといったケースが該当します。債権者は損害賠償請求や契約解除が可能になります。
履行不能
債務の履行が物理的・法律的に不可能になった状態を指します。例えば、売却予定の建物が火災で焼失してしまった場合など、もはや履行そのものが不可能になると、履行不能として損害賠償の対象となります。
不完全履行
一応は債務を履行しているものの、その内容が契約の条件を満たしていない場合です。たとえば、傷がある商品を引き渡した、工事が設計図通りでなかった場合などがこれにあたります。
債務不履行に基づく損害賠償
債務不履行が認められると、原則として債権者は債務者に対して損害賠償を請求できます。ただし、債務者に「故意または過失」があることが前提となります。
つまり、注意を払っていれば防げたのに履行できなかった、という状況でなければなりません。
不可抗力(天災や戦争など)での不履行は免責される場合があります。
契約の解除と債務不履行
債務不履行が発生した場合、債権者は契約を解除することができます。ただし、相当の期間を定めて履行を催告してもなお履行されないときに限られます(催告解除)。
ただし、履行が不能な場合や契約の目的が達成できないほどの不履行があった場合は、催告なしで解除(無催告解除)も可能です。
債務不履行と過失責任の原則
民法では「債務不履行が債務者の過失によるものであれば責任を負う」とされています。これを「過失責任主義」と言います。
つまり、債務者に過失(注意義務違反)がなければ原則として責任は問われません。この点は試験でも頻出なので押さえておきましょう。
まとめ:債務不履行のパターンを覚えよう
債務不履行とは、契約上の義務を果たせない状態を指し、履行遅滞・履行不能・不完全履行の3類型があります。債務者に過失があれば損害賠償や契約解除が可能です。
宅建試験では、解除の条件や損害賠償の可否などが問われるため、各パターンと要件を整理して理解しておきましょう。
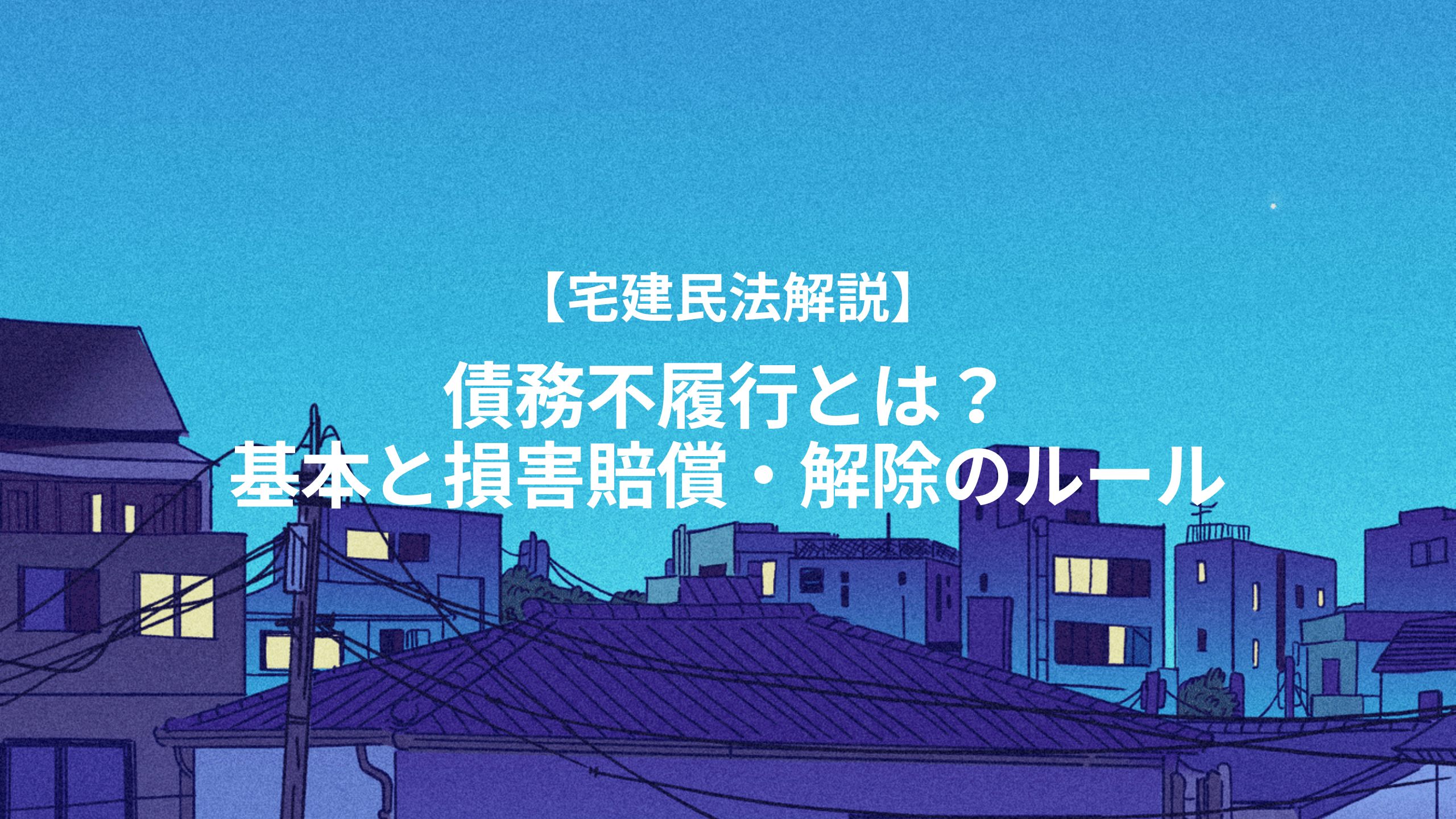

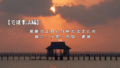


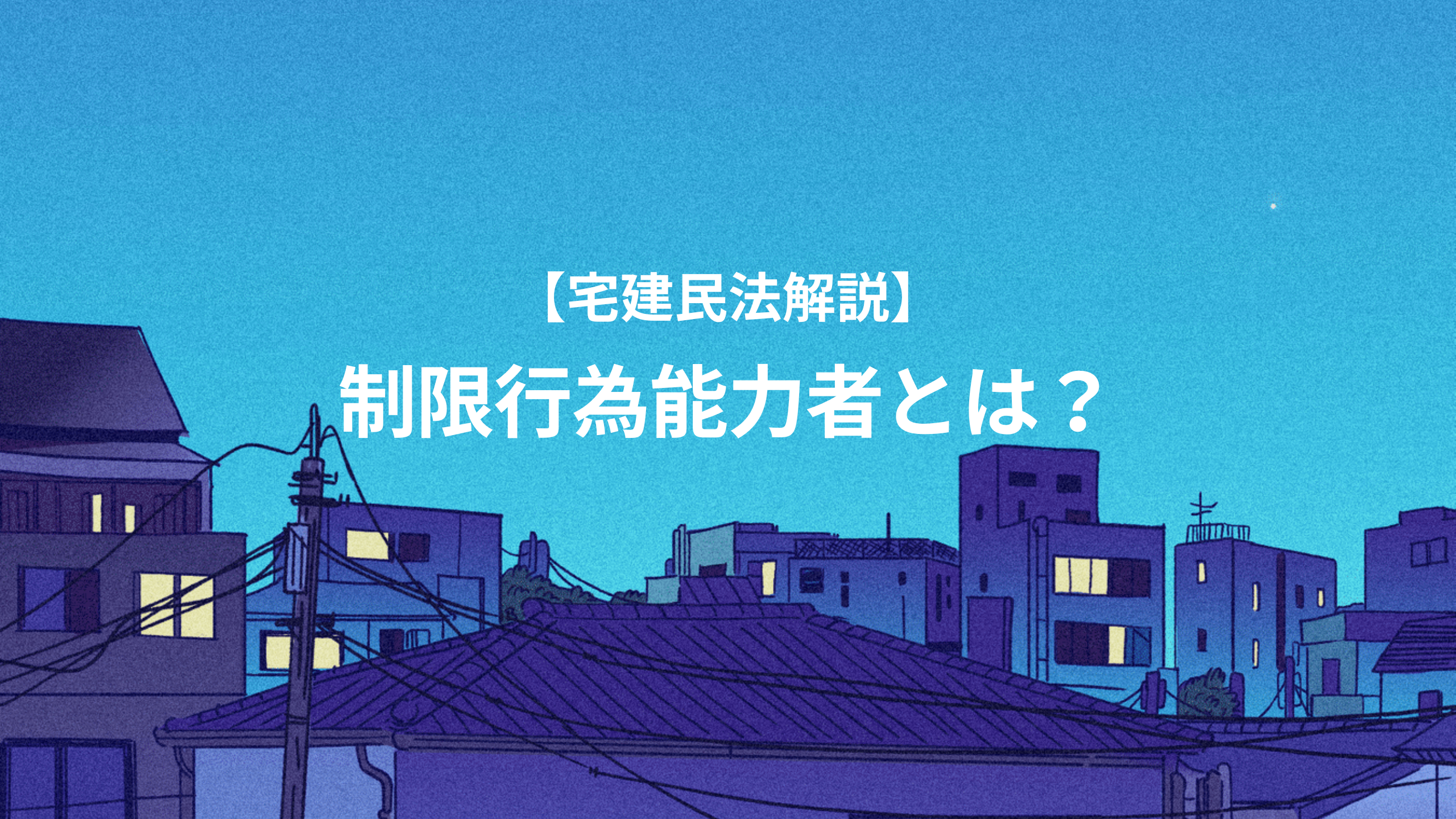


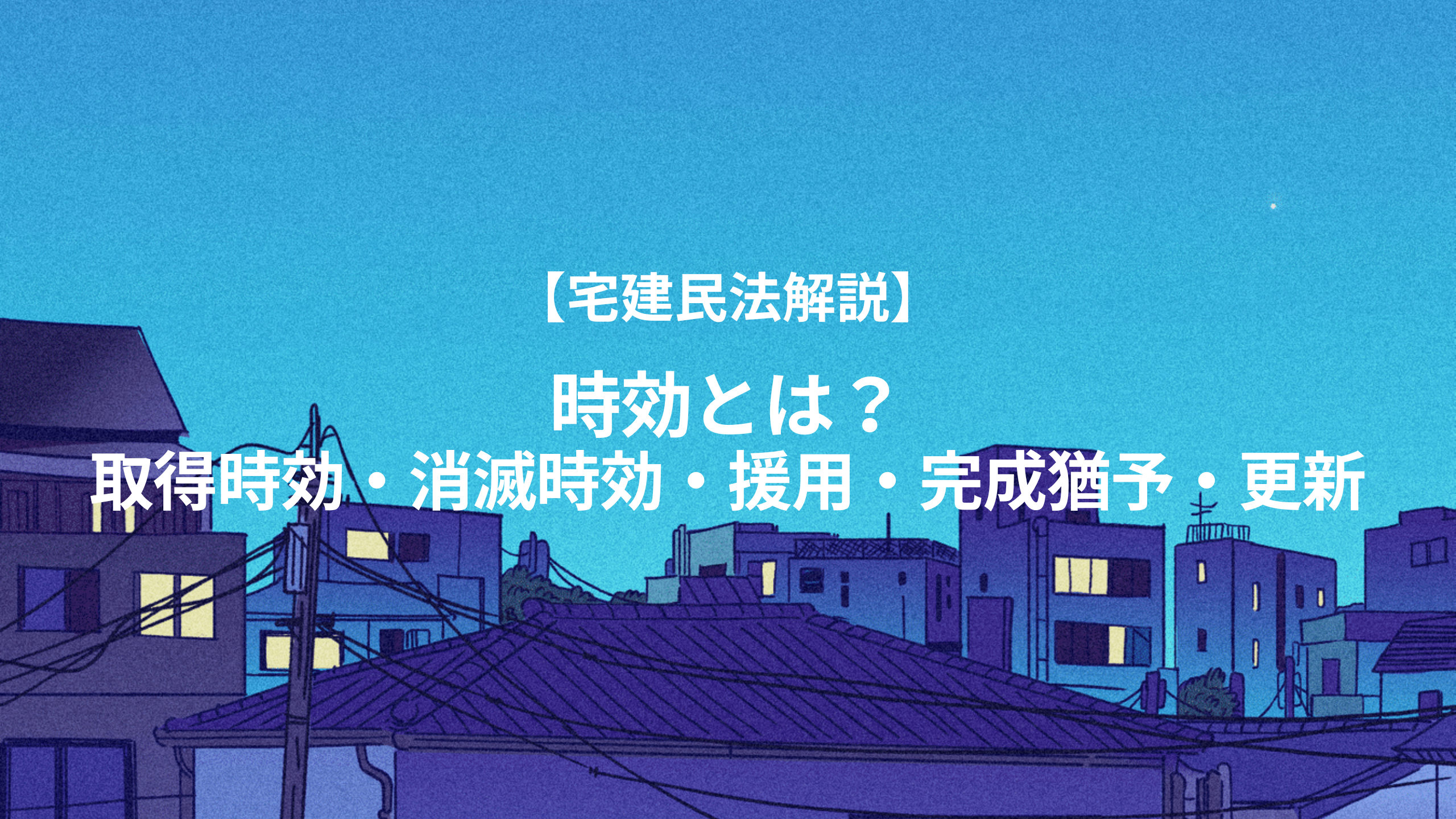
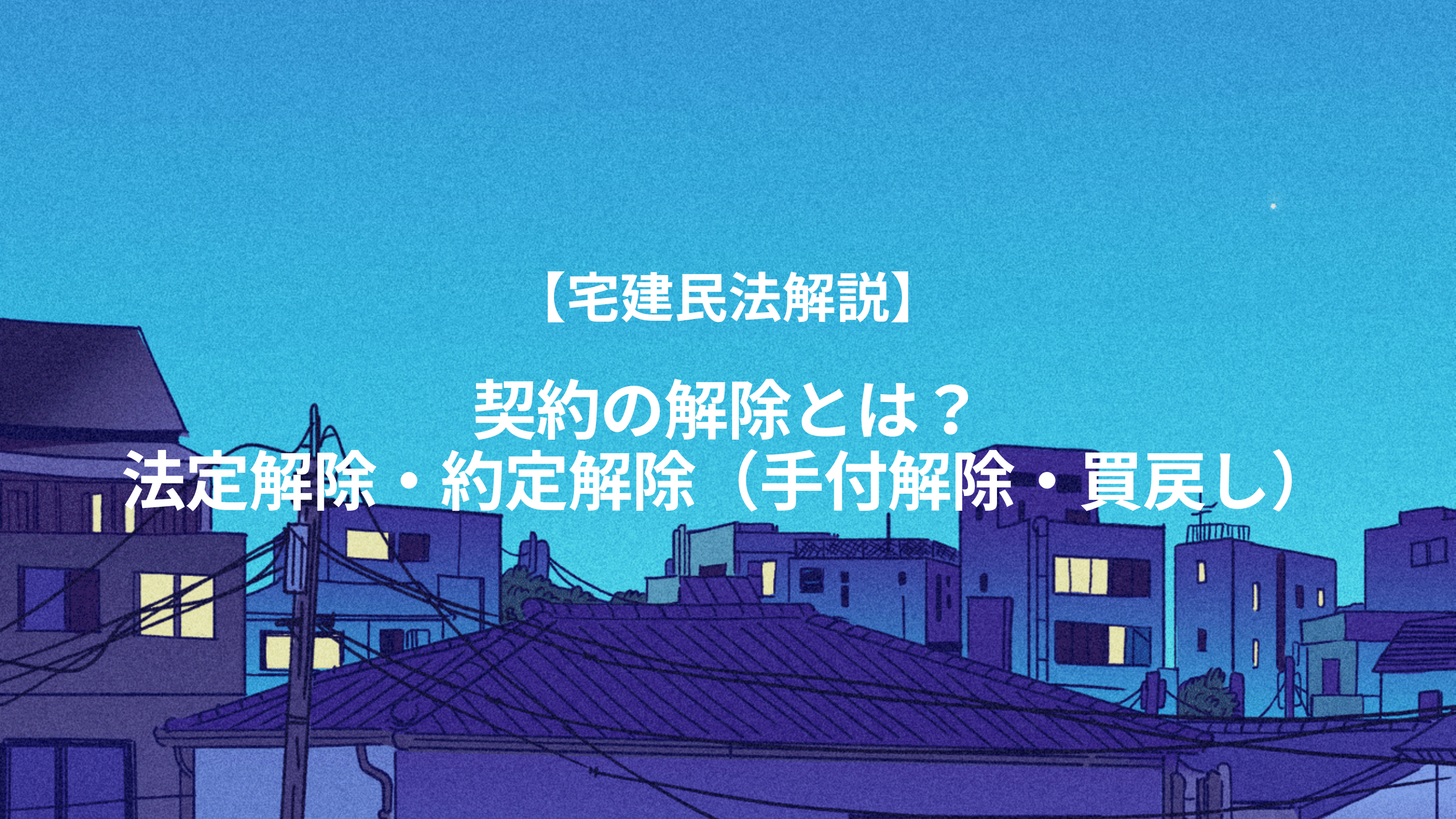
コメント