宅建試験では、「時効」が頻出テーマのひとつです。時効には、他人の物でも一定の条件を満たせば自分のものになる取得時効と、一定期間行使されなかった権利が消える消滅時効があります。本記事では、両者の違いを明確にしながら、「起算点」「援用」「完成猶予・更新」など重要ポイントをわかりやすく解説します。
📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
時効とは?
時効とは、一定の時間が経過することで権利関係に変化を与える法律制度です。
時効には次の2種類があります:
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 取得時効 | 他人の物を長期間占有することで所有権などを取得できる制度 |
| 消滅時効 | 債権などを一定期間行使しないことで権利が消滅する制度 |
取得時効の要件と期間
他人の土地でも、長年きちんと占有すれば自分のものになる――それが取得時効です。
<成立要件>
- 所有の意思があること(借り物ではダメ)
- 平穏(争いがない)かつ公然(隠れていない)に占有すること
- 他人の権利であること
<占有期間>
| 状況 | 期間 |
|---|---|
| 善意かつ無過失 | 10年 |
| 悪意または有過失 | 20年 |
<対象となる権利>
所有権、地上権、永小作権、賃借権、継続的かつ外形的にわかる地役権など
消滅時効の起算点と期間
消滅時効は、権利を行使しないまま時間が過ぎると、その権利が消える制度です。ポイントは「いつから数え始めるか(起算点)」と「何年か(期間)」です。
<起算点の例>
| 債権の種類 | 起算点 |
|---|---|
| 期限付き債権 | 期限到来時 |
| 条件付き債権 | 条件成就時 |
| 期限なし債権 | 債権発生時 |
| 債務不履行に基づく損害賠償 | 請求可能時から |
<時効期間の例>
| 権利の種類 | 期間 |
|---|---|
| 一般債権 | 知った時から5年 or 行使可能時から10年 |
| 人身損害賠償 | 20年 |
| 地上権などの財産権 | 20年 |
| 確定判決に基づく債権 | 10年 |
| 所有権 | 消滅しない(例外) |
時効の完成猶予と更新
時効期間は放っておくと進行しますが、以下の事情があると一時的に止まったり(完成猶予)、リセットされたり(更新)します。
| 類型 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 完成猶予 | 時効の進行を一時的に停止 | 裁判の提起、催告(6か月)など |
| 更新 | 時効が振り出しに戻る(再スタート) | 債務の承認(返済・利息の支払い・口頭の認め)など |
※取得時効では、占有の喪失が更新の対象になります。
時効の援用と放棄
時効は成立しても自動では効力を発揮しません。関係者が「援用」して初めて効果が生まれます。
<用語整理>
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 援用 | 「時効が完成した」と主張して権利を取得・消滅させること |
| 放棄 | 援用しない選択。※時効完成前の放棄は無効 |
<援用できる人>
- 債務者本人
- 保証人
- 物上保証人
- 抵当不動産の取得者 など
<効果>
援用すると、時効完成は「起算日にさかのぼって」効力を発揮します(例:10年前に消滅したことになる)。
まとめ:取得時効と消滅時効の違いを理解する
宅建試験では、取得時効と消滅時効の違い、起算点と時効期間、そして援用・更新・猶予のルールが繰り返し問われます。とくに「誰が援用できるのか」「どんな行為が更新・猶予になるのか」など具体例をおさえておくことが合格のカギになります。
比較表:取得時効と消滅時効の違いまとめ
| 比較項目 | 取得時効 | 消滅時効 |
|---|---|---|
| 効果 | 権利を取得できる | 権利が消滅する |
| 対象 | 他人の物(不動産など) | 債権(請求権など) |
| 要件 | 平穏・公然・所有の意思による占有 | 一定期間権利を行使しない |
| 期間 | 善意無過失10年/悪意20年 | 権利ごとに異なる(5年・10年・20年など) |
| 援用 | 必要 | 必要 |
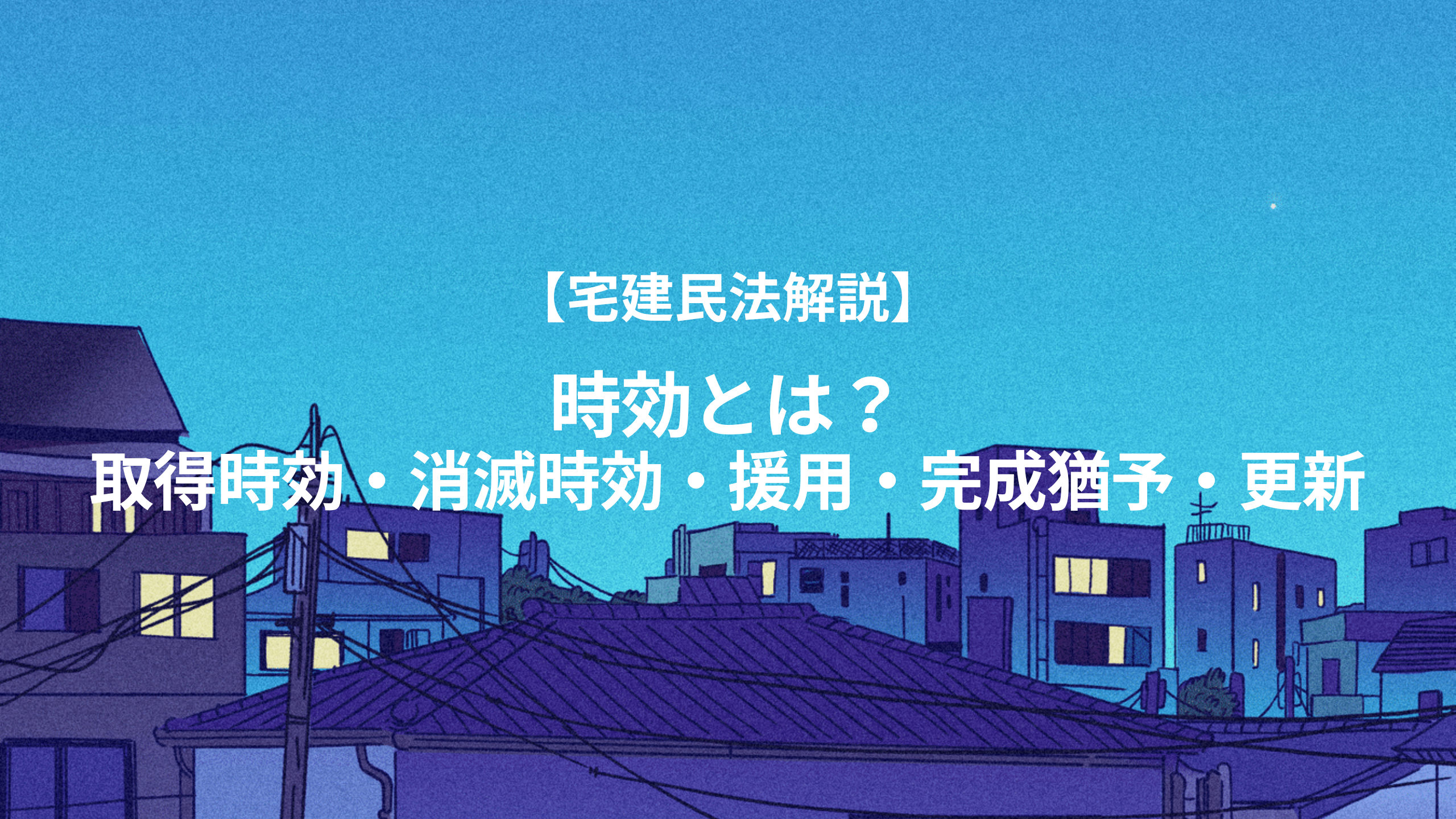

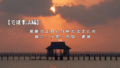


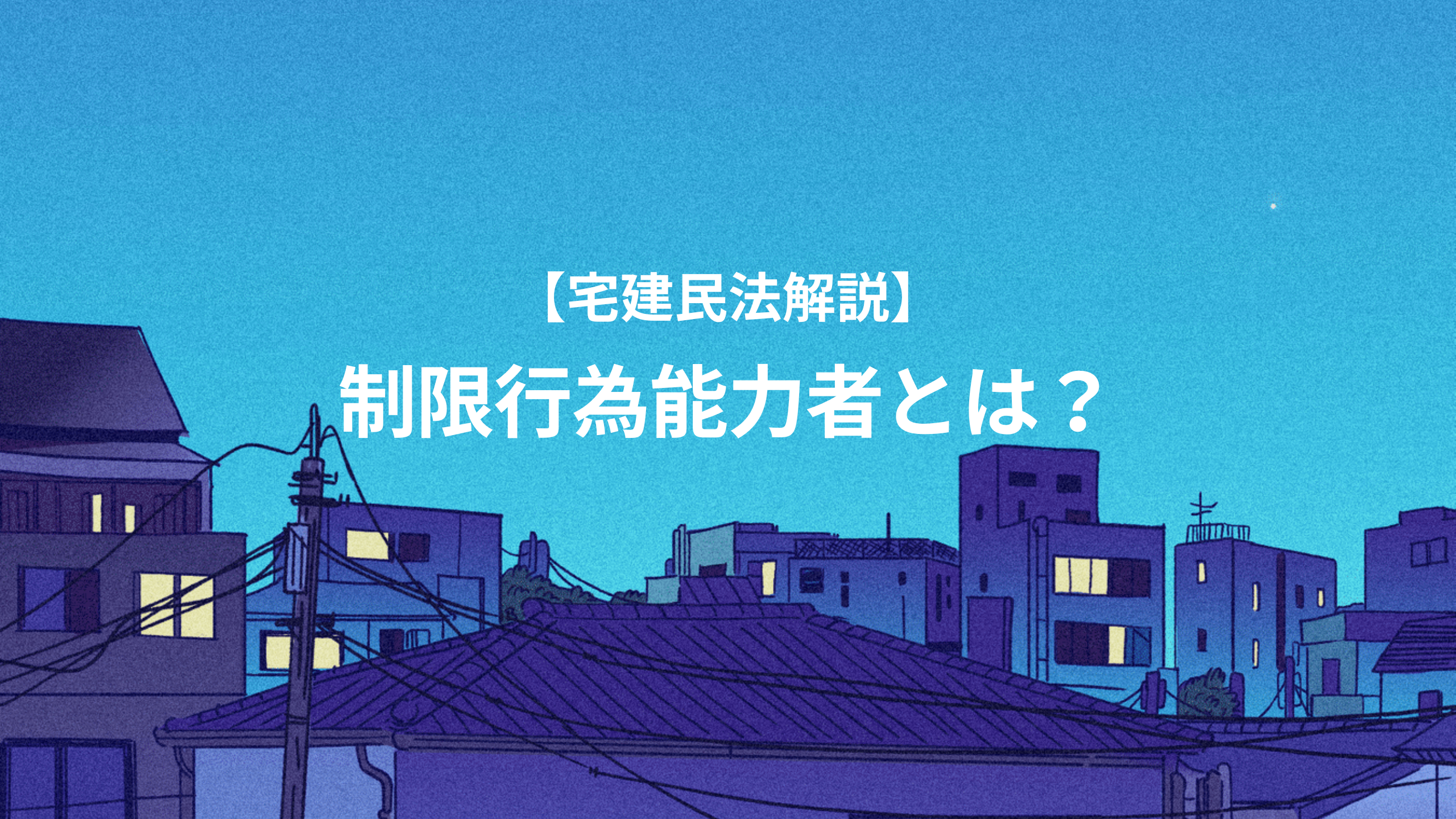


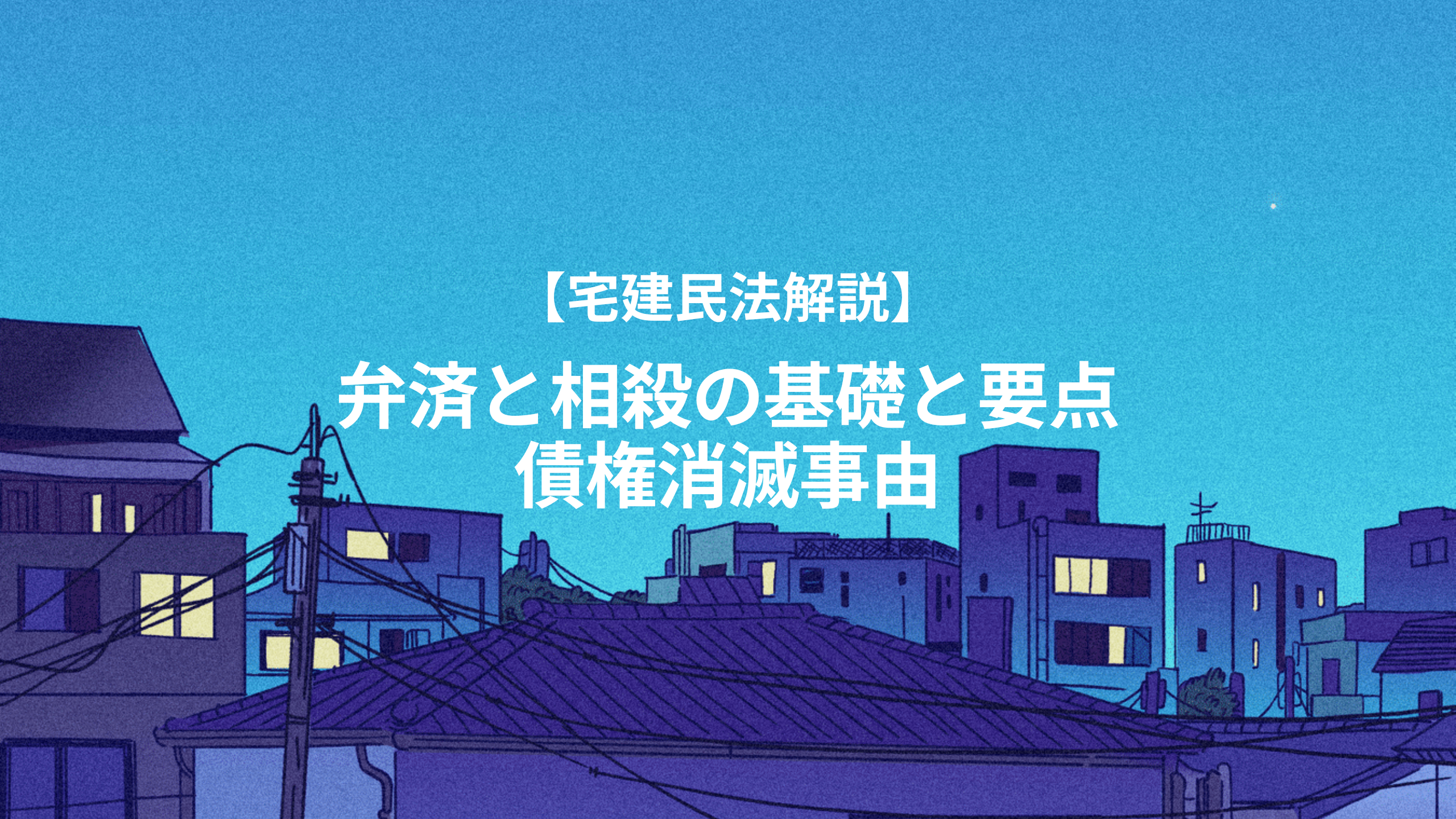
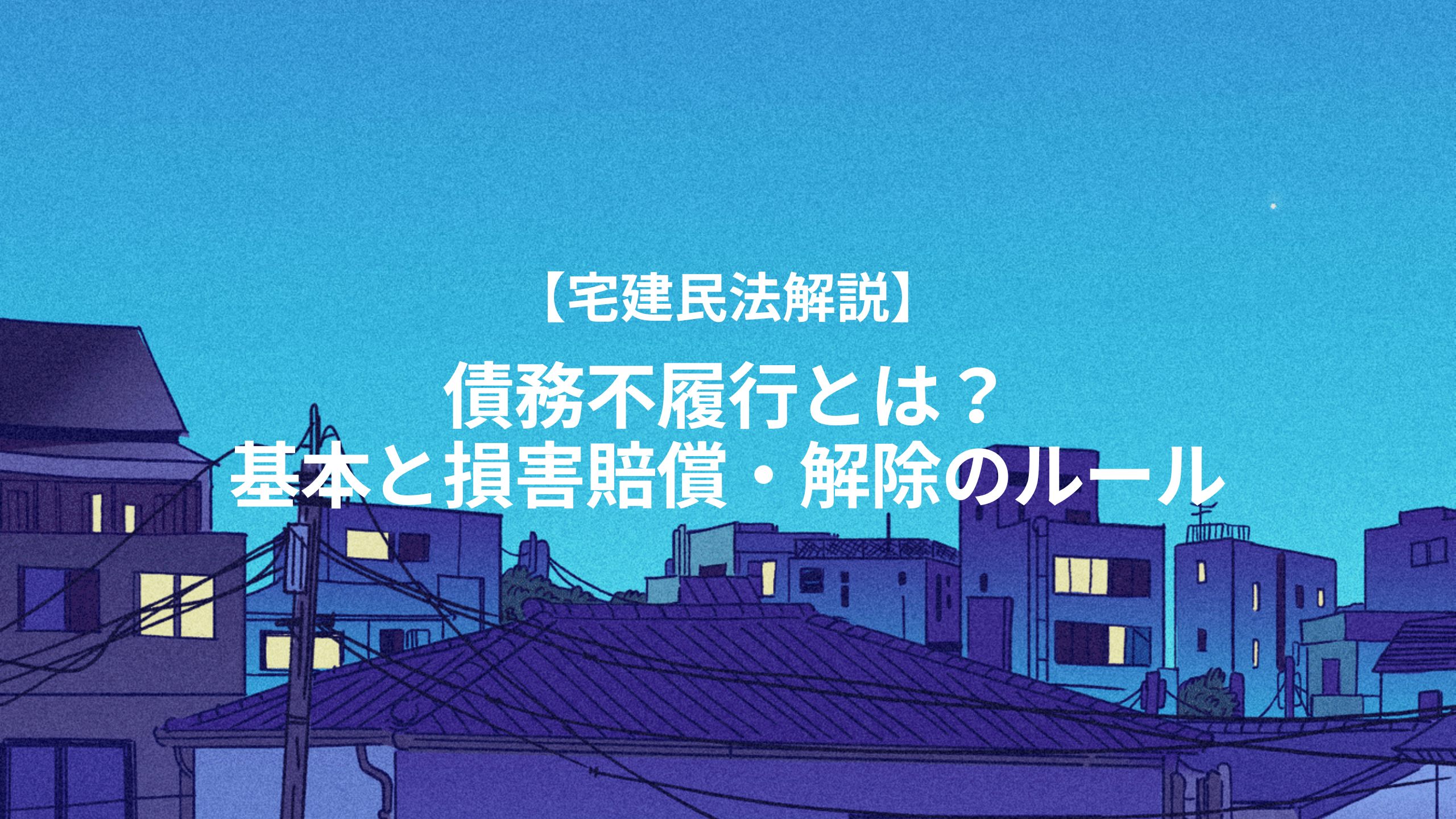
コメント