債権とは、お金の支払いや物の引渡しなどを求める権利です。しかしこの権利も、何らかの理由によって消滅します。
たとえば「契約の取消」や「時効」などもその一つですが、最も典型的で重要な消滅事由が、「債務者が債務を履行すること」、つまり 弁済(べんさい) です。
民法ではこのほかに「代物弁済」「相殺」「更改」「免除」「混同」なども債権消滅事由とされていますが、宅建試験では「弁済」と「相殺」が特に頻出・重要です。
📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
弁済とは?
弁済とは、債務者が契約や法律に基づいて、債務を履行し、債権を消滅させる行為のことです。
たとえば「借金を返済する」「商品代金を支払う」といった行為が弁済です。
弁済の成立要件(誰が・誰に・何を・いつ・どこで・どうやって)
弁済が有効に成立するには、次の要件を満たしている必要があります:
- 弁済すべき者が(債務者・代理人・第三者)
- 弁済を受ける正当な者に対して(債権者または受領権者)
- 契約や法律で定められた債務を
- 定められた時期に
- 定められた方法で
- 定められた場所で行うこと
弁済できる人
● 債務者本人
● 債務者の代理人
→債務者の同意があれば代理人でも可能。
● 第三者
→第三者でも弁済できますが、以下の条件があります。
- 債務の性質が第三者の弁済を許すものであること
→ 個人のスキルや信用に基づく債務(例:著名人による講演など)は本人しか弁済できない。 - 当事者が第三者弁済を禁止していないこと
→ 債権者または債務者が「第三者はダメ」と意思表示していれば不可。
📌 例外:正当な利害関係を持つ第三者(例:抵当不動産の第三取得者、物上保証人など)は、債務者の意思に反しても弁済可能です。
弁済を受ける者
- 原則:債権者本人
- 例外:債権者の代理人や、受領権者と認められる第三者
👉 もし債権者でない人物に弁済してしまった場合は、原則として無効。
ただし、次の条件を満たすときは有効になります:
- その者が「債権者のように見える外観」を有していた(例:権利証・実印を所持していた)
- 債務者が善意かつ過失がない(=知らずに弁済してしまった)
弁済の場所
- 特定物:債権発生時にその物が存在した場所
(例:○月○日収穫の米など) - 不特定物や金銭債務:債権者の現住所
※民法改正により、特定物でも一定の条件下で現状引渡しが可能となりました。
弁済の時期
- 原則:契約や法律によって定められる
- 売買契約では、目的物の引渡時に代金の支払い義務も生じる(=同時履行)
取引慣習などにより時間の指定がある場合は、その時間内に弁済・請求する必要があります。
弁済の提供(実際に履行しようとする意思表示)
- 現実の提供:実際に金銭や物品を持参して債権者に提示
- 口頭の提供(例外):
債権者が受領を拒んだ場合や、債権者の行動が必要な場合は、口頭でも有効。
👉 弁済の提供を行うことで、債務不履行の責任は回避されます。
相殺とは?
相殺とは、互いに債権・債務を持っている当事者が、一方の意思表示によって債権と債務を差し引き消滅させる制度です。
例:
AがBに100万円貸していて、BもAに80万円貸している場合、Aが相殺の意思を示せば、AはBへの返済義務を80万円分免れ、残り20万円の債権が残ります。
- A → B:100万円(自働債権)
- B → A:80万円(受働債権)
→ Aは20万円の債権者に。
相殺の成立要件(=「相殺適状」)
- 有効に成立している2つの債権があること
- 時効完成後の債権でも、相殺適状にあったときなら相殺可能。
- ただし、時効消滅した後にその債権を譲り受けても相殺は不可。
- 同種の目的物であること
(例:金銭債権同士) - 両債権が弁済期にあること
- 受働債権については期限の利益を放棄すればOK
- 相殺が許される債権であること
- ❌ 不法行為に基づく損害賠償債権(受働債権として)
- ❌ 生命・身体の侵害による債権(受働債権として)
- ❌ 同時履行の抗弁権がある債権(自働債権として)
- ❌ 差押え後に取得した債権(受働債権として)
相殺の方法と効果
- 方法:一方当事者の意思表示により成立(相手の同意不要)
- 条件や期限のついた相殺は不可
- 効果:債権と債務は対等額で消滅
→ 相殺適状になった時点に遡って効力発生!
まとめ:弁済と相殺の違いをしっかりと理解する
弁済と相殺は、いずれも債務を消滅させる手段ですが、弁済は「実際に支払う」、相殺は「相手への支払いを自分の債権と相殺して済ませる」という違いがあります。試験でも実務でも頻出の論点なので、条件や成立の要件を整理して理解しておきましょう。
| 項目 | 弁済 | 相殺 |
|---|---|---|
| 基本概念 | 債務を履行して債権を消滅させる行為 | 債権と債務を差し引き消滅させる意思表示 |
| 行為主体 | 債務者・代理人・第三者(条件付き) | 債権者自身による一方的意思表示 |
| 相手方 | 正当な債権者または外観的受領権者 | 相手方の同意不要 |
| 要件 | 正しい相手・時期・方法などで履行 | 両債権が成立・弁済期・同種など |
| 効果 | 債務の履行により債権が消滅 | 差額を残し、債権債務が消滅(遡及効あり) |
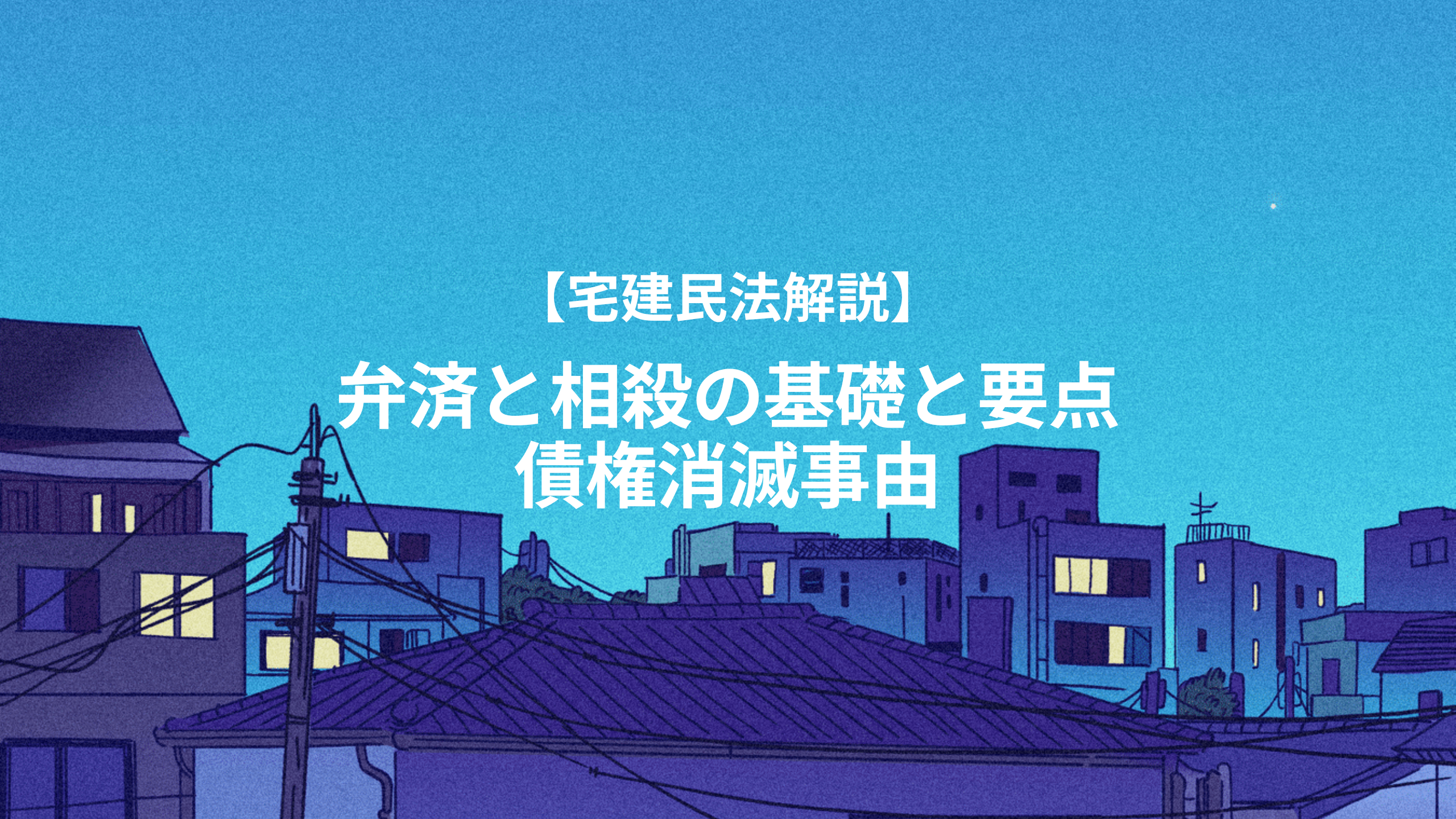

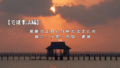


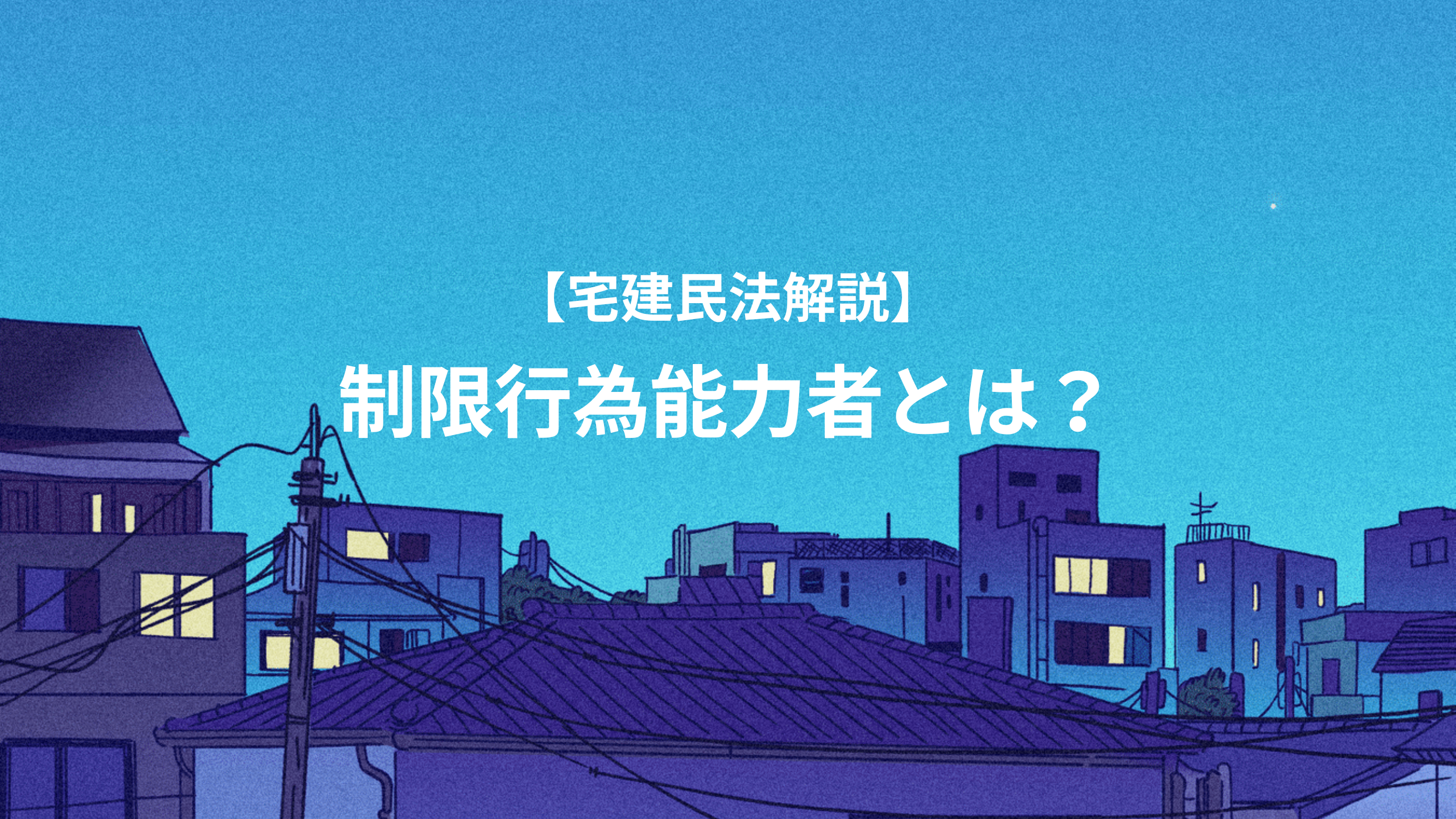


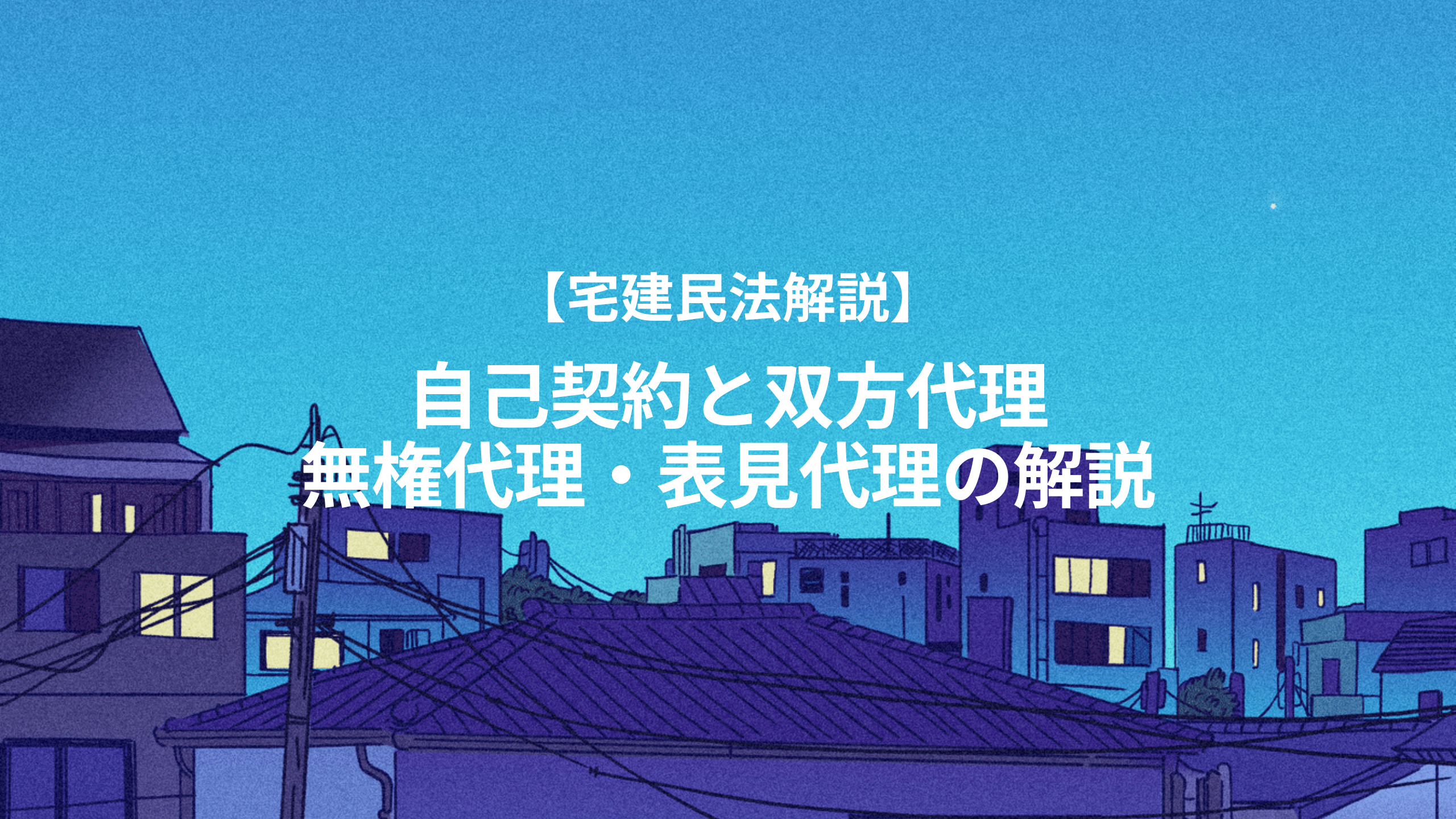
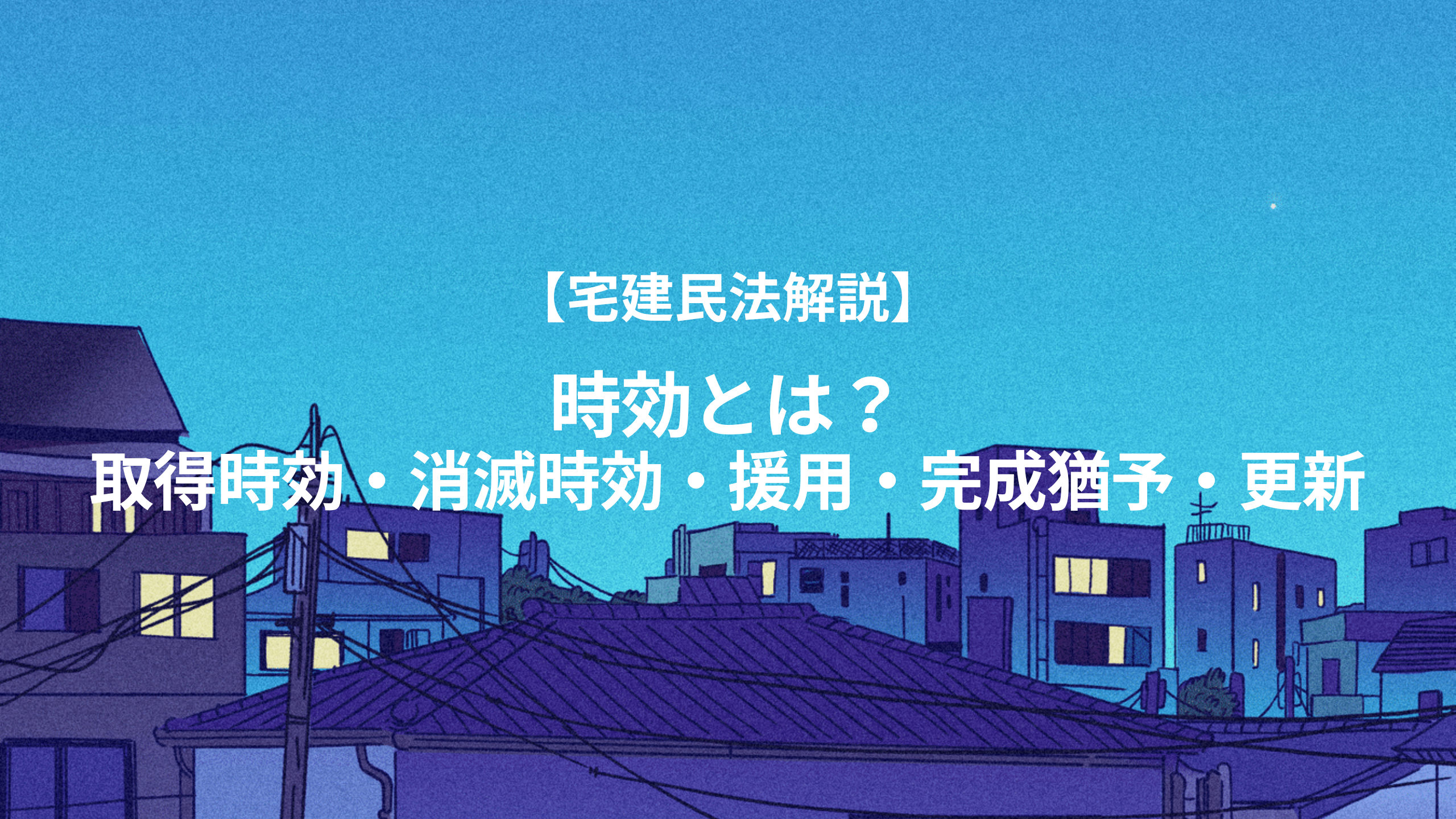
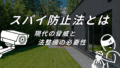
コメント