第一次世界大戦(1914~1918年)は、ヨーロッパを中心に世界各国を巻き込んだ人類初の“世界規模の戦争”でした。その背景には帝国主義の対立や同盟関係があり、最終的に数千万人の死傷者を出しました。本記事では、戦争の原因から経過、終結、そしてその後の世界への影響までをわかりやすく整理します。
第一次世界大戦 発生の背景
19世紀末から20世紀初頭、ヨーロッパ列強は 帝国主義の競争 を激化させていました。アフリカ分割やアジア進出など、植民地獲得競争が繰り広げられた背景には、工業化による 資源確保と市場拡大の欲求 がありました。
特に工業力で急成長した ドイツ帝国 は、1871年の統一以降、製鉄や化学工業、軍事力で急速に力をつけ、イギリスやフランスに追いつき追い越そうとしました。
そのため、イギリスとは海軍力で、フランスとは領土問題(アルザス=ロレーヌ地方)で、それぞれ対立を深めていきました。
一方、ヨーロッパ南東部の バルカン半島 は「ヨーロッパの火薬庫」と呼ばれていました。この地域はオスマン帝国の支配下にありましたが、19世紀以降に帝国の力が弱まると、セルビア・ブルガリアなどのスラヴ系民族が次々に独立を模索し、民族主義運動が高揚しました。
さらに、スラヴ民族の保護を掲げる ロシア と、バルカン支配を維持したい オーストリア=ハンガリー帝国 が対立。民族独立運動に大国同士の思惑が絡み、地域の緊張は常に爆発寸前の状態にありました。
同盟体制の形成
19世紀後半、ヨーロッパは複雑な同盟関係によって二大陣営に分かれていきました。
- 三国同盟(1882年)
ドイツ・オーストリア=ハンガリー・イタリアが結成。- ドイツはフランスに対抗するために、地理的にフランスを挟み込めるオーストリアとイタリアを取り込みました。
- オーストリア=ハンガリーは、民族運動の高まりで不安定なバルカンを抑えるために、強国ドイツの支援を必要としました。
- イタリアは領土拡張の野心を持ち、列強の一角に食い込むために同盟に加わりました(ただし利害対立も多く、最終的には第一次世界大戦中に離脱)。
- 三国協商(1907年)
イギリス・フランス・ロシアが協力体制を構築。- フランスは、普仏戦争で奪われたアルザス=ロレーヌ地方をドイツから取り戻したい思惑がありました。
- ロシアはスラヴ民族の保護を掲げ、バルカン半島への影響力拡大を狙っていました。
- イギリスは「栄光ある孤立」と呼ばれる中立政策を長く維持していましたが、ドイツの海軍力増強と植民地進出に脅威を感じ、フランス・ロシアと協力するようになりました。
こうしてヨーロッパは「三国同盟」と「三国協商」という二大陣営に分かれ、戦争の土台が築かれました。
一方、日本は 日英同盟(1902年) を通じて、イギリス側に接近。第一次世界大戦では連合国側(イギリス・フランス・ロシア)として参戦し、アジア・太平洋でドイツ領を占領するなど、自国の勢力拡大に利用しました。
勃発のきっかけ ― サラエボ事件
1914年6月28日、オーストリア皇太子 フランツ・フェルディナント が、ボスニアの州都サラエボで暗殺されました。犯人はセルビア系青年 ガヴリロ・プリンツィプ で、秘密結社「黒手組」と関係があるとされる人物でした。
全セルビア人の統一を目的とした民族主義的な秘密組織。1911年、セルビアの現状に不満をもつ軍人を中心にして結成された。37条に及ぶ規約があり秘密保持のため、入会に際しては謎めいた儀式があった。
なぜ彼が皇太子を狙ったのか?背景には、以下の要因があります。
- ボスニア・ヘルツェゴビナは本来オスマン帝国領でしたが、1908年にオーストリアが併合。これに対し、同じスラヴ民族であるセルビアは「自分たちの民族を奪われた」と強く反発していました。
- セルビアは「大セルビア主義」と呼ばれる民族統一の理想を掲げ、オーストリアの支配に抵抗していました。
- フェルディナント皇太子は帝国内でスラヴ民族に自治を認める考えを持っていましたが、逆にこれは「セルビアの独立や統一を妨げる」と考える過激派にとって脅威だったのです。
つまり、プリンツィプによる暗殺は「民族解放」を掲げるセルビアの過激な民族主義運動の一環であり、オーストリアの覇権に対する反発が直接的な動機でした。
この事件をきっかけにオーストリアはセルビアへ宣戦布告し、同盟関係が次々に連鎖的に発動。第一次世界大戦へと発展しました。
戦争の経過
西部戦線(フランス・ドイツ間)
開戦当初、ドイツは「シュリーフェン計画」に基づき、フランスを短期で撃破しようとしました。ベルギーに侵攻し、パリへ迫りますが、1914年の マルヌの戦い でフランス軍に阻止されます。以降はフランス北部に塹壕が張り巡らされ、数百キロにわたる 塹壕戦(トレンチ・ウォーフェア) が展開。戦線はほとんど動かず、「消耗戦」と呼ばれる膠着状態が続きました。この中で 機関銃・毒ガス・戦車・航空機 などの新兵器が投入され、兵士たちは過酷な環境で大量に犠牲となりました。
東部戦線(ドイツ・オーストリア vs ロシア)
西部戦線と比べて戦線が広大だったため、より機動的な戦闘が展開。1914年の タンネンベルクの戦い ではドイツ軍がロシア軍を大敗させ、以降ロシアは劣勢に立たされます。戦争が長引く中で、ロシア国内では食糧不足や戦死者の増大によって社会不安が高まり、やがて革命へとつながっていきます。
海上戦
イギリスは 海上封鎖 によりドイツを経済的に追い詰めました。これに対抗してドイツは Uボート(潜水艦)作戦 を展開し、商船や客船を無差別に攻撃。1915年にはアメリカ人も乗っていた客船 ルシタニア号 が撃沈され、国際世論に衝撃を与えました。さらに1917年、ドイツは「無制限潜水艦作戦」を再開し、アメリカとの対立が決定的になります。
アメリカ参戦とロシア革命
1917年4月:アメリカはついに連合国側で参戦。これにより、物資・兵力ともに連合国が大きく優位に立ちました。一方ロシアでは、戦争の長期化による食糧不足や兵士の疲弊から、政権に不満が爆発。
- 二月革命(1917年3月):皇帝ニコライ2世が退位し、ロマノフ王朝が崩壊。臨時政府が成立します。
- 十月革命(1917年11月):レーニン率いるボリシェヴィキ(共産党)が政権を掌握し、世界初の社会主義国家を樹立。
ロシアは戦争継続を拒否し、1918年3月にドイツと ブレスト=リトフスク条約 を結び、戦線から離脱しました。
終結
ロシアが離脱したことで、ドイツは東部戦線の兵力を西部戦線へ集中させ、1918年春季攻勢 を仕掛けました。
しかし、アメリカ軍の参戦により連合国軍の兵力は逆に優勢となり、ドイツ軍は次第に後退。国内では食糧不足と戦争疲弊で革命運動が広がり、皇帝ヴィルヘルム2世は退位して亡命。
ドイツは共和制へ移行します。1918年11月11日午前11時、フランスのコンピエーニュで休戦協定が結ばれ、第一次世界大戦はついに終結しました。
戦後の講和とヴェルサイユ条約・国際連盟
第一次世界大戦は1918年11月11日にドイツが降伏し、終結を迎えました。戦後の秩序を定めるために1919年、フランスのヴェルサイユ宮殿で講和会議が開かれます。ここで締結された「ヴェルサイユ条約」は、敗戦国ドイツに対し厳しい条件を課しました。
ドイツは 領土の割譲(アルザス=ロレーヌをフランスへ返還など)、 軍備の大幅制限、 多額の賠償金の支払い を命じられ、国民の間に強い不満が残りました。これが後にナチス台頭や第二次世界大戦の原因の一つとなります。
一方、アメリカ大統領ウィルソンが提唱した「十四か条の平和原則」に基づき、国際的な平和維持機関として 国際連盟 が設立されました。国際紛争を話し合いで解決しようとする初めての試みでしたが、アメリカ自身が不参加であったことや、制裁力の弱さから限界を抱えていました。
まとめ
第一次世界大戦後の講和は、平和を維持する理想を掲げながらも、敗戦国ドイツに過酷な条件を課したことで深い不満を残しました。国際連盟は平和を守る新しい枠組みとして期待されたものの、強制力や参加国の不十分さから限界がありました。こうした「平和を目指したが不完全な体制」が、ドイツの反発や経済的困難を招き、最終的に第2次世界大戦への道を開いていくこととなったのです。




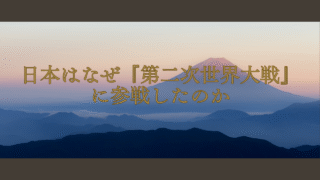

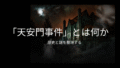

コメント