第二次世界大戦は人類史上最大の戦争であり、日本もその渦中に深く関わりました。
本記事では「なぜ日本は戦争へと突き進んだのか?」という問いを軸に、満州事変から真珠湾攻撃までの流れを時系列で追います。
単なる偶発的な事件ではなく、経済不安、軍部の台頭、外交の失敗、資源確保の焦りが重なった結果、日本は自ら破滅への道を選んでいったのです。
満州事変(1931年)
満州とは現在の中国東北地方(遼寧省・吉林省・黒竜江省)を指し、広大な土地と豊富な資源(石炭・鉄鉱石・大豆など)を抱えていました。近代以降、日本にとって満州は「生命線」と呼ばれ、経済・軍事の両面で大きな意味を持っていました。
1931年9月18日、南満州鉄道の線路が爆破される「柳条湖事件」が発生します。これは関東軍(日本の駐留軍)が自作自演した工作でした。日本軍はこれを口実にただちに満州全域へ侵攻し、中国軍を排除。翌年には「満州国」を建国させました。
背景には1929年の世界恐慌による打撃があります。恐慌前、日本は主に生糸輸出を中心に外貨を獲得し、植民地の朝鮮や台湾から食料や資源を得ていました。しかし恐慌によって輸出が激減し、経済は深刻な打撃を受けます。軍部や財界は新たな資源確保先として満州に目を向け、侵略を正当化していきました。
国際社会はこれを侵略と非難し、国際連盟は「リットン調査団」を派遣。報告書は日本軍の行動を不当と認定しました。日本はこれに反発し、1933年に国際連盟を脱退します。当時、国際連盟はアメリカ不参加・大国間の利害対立により実効力が弱く、日本の脱退を止められませんでした。この出来事は、日本の国際的孤立を決定づけ、軍部主導の対外政策を一層強化する転機となったのです。
盧溝橋事件と日中戦争(1937年)
1937年7月7日、北京郊外の盧溝橋で、日本軍と中国国民党軍(蒋介石率いる国民政府軍)の間に小規模な武力衝突が発生しました。これは日本軍が夜間演習中に兵士の点呼をとった際、「一名行方不明」と誤認したことから周囲を捜索し、中国側と対立したことが発端でした。本来であれば外交交渉で収められるはずの事件でしたが、現地の日本軍部隊が強硬な対応を取り、やがて戦闘が拡大。日中両国は全面戦争へ突入しました。
戦争は短期決戦を想定していた日本にとって予想外の展開を見せます。中国は広大な国土を背景に徹底抗戦し、戦線は長期化。日本は上海・南京などを攻略しましたが、戦争終結の見通しは立ちませんでした。この過程で、1937年12月の南京攻略後、日本軍による大規模な虐殺・暴行事件が発生しました(南京事件)。数万~数十万人規模の民間人・捕虜が犠牲になったとされ、国際的非難を浴びる大惨事となりました。
国際社会の動きも日本に不利でした。アメリカやイギリスは、反ファシズムの立場と中国市場の利害を背景に蒋介石の国民政府を支援しました。特にアメリカは義勇パイロット部隊「フライング・タイガース」を派遣するなど、中国への軍事・経済的援助を拡大しました。これは日本とアメリカとの対立を深める大きな契機となります。
なお、日本とイギリスはかつて「日英同盟」(1902年締結)によって友好関係を保っていました。しかし第一次世界大戦後、ワシントン会議(1921–22年)の「四カ国条約」により日英同盟は破棄されます。その後、イギリスは中国市場を重視して蒋介石を支持し、日本との関係は徐々に悪化していきました。
こうして日中戦争は、日本にとって国際的孤立を決定づける戦争となり、やがて経済制裁・資源封鎖を招き、太平洋戦争へとつながっていったのです。
世界情勢と日本の選択(1939〜1941年)
1939年9月、ドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が勃発しました。ヒトラー率いるナチス・ドイツは「東方生存圏(レーベンスラウム)」の拡大を掲げ、東ヨーロッパの支配を目指していました。ポーランドはその最初の標的とされ、ソ連との密約(独ソ不可侵条約)に基づいて分割占領されます。この侵攻によりイギリスとフランスが対独宣戦し、戦争はヨーロッパ全土へ拡大しました。
この戦局を背景に、日本は1940年に日独伊三国同盟を締結します。ドイツの快進撃に勢いを感じた日本は、ヒトラーの軍事力と、ムッソリーニ率いるイタリアのファシズム体制に連携し、国際的孤立から脱却しようとしたのです。三国同盟は「どれかが第三国から攻撃を受けた場合、他が支援する」という内容でしたが、当時の狙いはアメリカへの牽制が大きな目的でした。
一方、アメリカは日本の中国侵略と南方進出を強く警戒し、経済制裁を強化します。特に1941年の石油・鉄・ゴムなどの禁輸は、日本にとって致命的な打撃でした。さらに、アメリカ・イギリス・中国・オランダが結束して日本を経済的に包囲する「ABCD包囲網」が形成され、日本は資源確保か外交妥協かの二択を迫られました。最終的に軍部は「南方資源地帯の確保」を優先し、外交的妥協の道は狭まっていきます。こうして日本は、戦争への道を一層深く進んでいったのです。
真珠湾攻撃と太平洋戦争の始まり(1941年12月)
日本は戦争回避のためにアメリカとの交渉を続けましたが、溝は埋まりませんでした。アメリカは1941年11月に「ハル・ノート」と呼ばれる対日最終案を提示し、日本の中国からの全面撤退や仏印からの撤兵を要求しました。これを日本政府と軍部は「最後通牒」だと受け止め、「受け入れれば満州や中国での権益をすべて失う」と判断します。
そこで日本は外交交渉の決裂を確認し、武力による現状打破を選択しました。その標的に選ばれたのがハワイの真珠湾でした。ここにはアメリカ太平洋艦隊の主力が停泊しており、奇襲でこれを無力化すればアメリカの反撃を遅らせ、その間に南方の資源地帯(インドネシア・マレーシア・フィリピンなど)を確保できると考えたのです。
1941年12月8日未明(日本時間)、日本海軍は真珠湾を奇襲攻撃し、多数の戦艦を撃沈・大破させました。この作戦は一時的には大成功を収めましたが、航空母艦や補給施設を破壊できなかったことが後に大きな誤算となります。そして何より、この攻撃によってアメリカは直ちに参戦を決意。日本の狙いであった「短期決戦で米国の戦意を挫く」という戦略は失敗に終わり、逆に日米の国力差が浮き彫りとなり、日本は長期的に不利な戦争へ追い込まれることになったのです。
日本の立場と戦争の帰結
日本は「自存自衛」を掲げ、資源不足を打破するために南方資源地帯(インドネシア・マレーシアなど)への進出を試みました。しかしこれはアメリカやイギリスとの対立をさらに深め、制裁強化を招いて悪循環を生み出しました。国内では統制経済の下で食糧や物資が欠乏し、人々の生活は困窮を極めます。学徒出陣や徴兵により多くの若者が戦場へ送られ、東京・大阪・名古屋・横浜など主要都市は度重なる空襲により壊滅的な被害を受けました。
1945年8月、広島と長崎に原子爆弾が投下され、さらにソ連が参戦すると、もはや抗戦は不可能となり、日本はポツダム宣言を受け入れ無条件降伏を決断します。敗戦後、日本はGHQ(連合国軍総司令部)の占領下に置かれ、軍国主義からの脱却と民主化改革が進められました。
憲法改正によって戦争放棄を掲げ、教育や土地改革、女性参政権の導入など大きな社会変革が行われます。その後、日本はアメリカの援助(特に朝鮮戦争による特需)を背景に経済復興を果たし、戦後の高度経済成長へとつながっていきました。
まとめ
日本が第二次世界大戦に参戦した背景には、資源確保の切実な必要性、軍部の台頭、国際的孤立といった要因が重なっていました。戦争は偶然の産物ではなく、一連の政治的・軍事的選択の積み重ねの結果であり、その結末は国家と国民に壊滅的な打撃を与えました。
ただし「勝てば官軍、負ければ賊軍」という言葉が示すように、歴史の評価は勝者によって決定づけられる面も否めません。日本がすべてにおいて悪だけを行ったわけではなく、反省すべき点は参戦国すべてに存在します。重要なのは一国のみを断罪することではなく、歴史を俯瞰して学び、外交の失敗や軍事依存の危険性を現代にどう生かすかを考えることです。




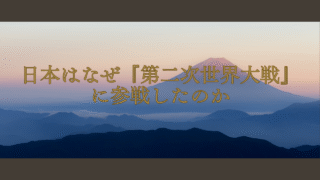



コメント