宅建試験の法令上の制限の中でも、超頻出で得点源なのが「国土利用計画法の事後届出制」です。
市街化区域での土地取引に必要な届出とは何か?どのくらいの面積から対象になるのか?覚えるべき数字や例外、罰則などを、宅建初学者でも理解できるように整理しました。
「試験直前にこれだけ見れば安心!」という状態を目指して、基本から一気にまとめていきます。
📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
¥3,300 (2025/06/19 14:22時点 | Amazon調べ)
事後届出制とは何か?
国土利用計画法の中で、宅建試験で最も重要なのが「事後届出制」です。
これは以下のような制度です。
- 対象区域:一般区域
- 対象者:権利取得者(買主)
- 手続き:契約後2週間以内に都道府県知事へ届出
- 目的:合理的かつ計画的な土地利用を確保するため
届出が必要な3つの要件
事後届出制が必要となる取引には、以下の3つの要素が揃う必要があります。
一団の土地に関する権利
- 隣接する複数の土地でも、一体として計画的に取引されたと判断されれば対象
- 判断の基準は「物理的・計画的な一体性」
- 判断の基準は 権利取得者(買主)
- 面積の合算で規模を超える場合も該当
事後届出を要する面積要件とは以下の通りです。
| 区域 | 届出が必要な面積 |
|---|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 |
| その他の都市計画区域 | 5,000㎡以上 |
| 都市計画区域外(準都市含む) | 10,000㎡以上 |
※すべて「以上」なので、ピッタリの面積でも対象になります。
対価を得て
- 無償の相続・贈与・遺贈などは対象外
- 一方で、代物弁済・予約完結権の譲渡・譲渡担保などは対象になる
- 地上権・賃借権の設定も、一時金などの対価があれば対象
移転・設定する契約
- 契約により権利を「取得」することが必要
- 契約でない一方的行為(例:予約完結権の行使)は対象外
- 予約や条件付き契約は、契約日や予約日が届出期限の起算日になる
届出の流れと注意点
- 届出義務者:権利取得者
- 提出期限:契約締結後2週間以内(市町村経由 or 指定都市へ直接)
- 審査対象:土地の「利用目的」のみ(価格は審査されない)
- 知事の対応:
- 助言(義務なし)
- 勧告(必要があれば、土地利用審査会の意見を聴いたうえで)
罰則や公表
- 届出しなかった → 6か月以下の懲役 or 100万円以下の罰金
- 勧告を無視した → 契約は有効/罰則なし/ただし公表の可能性あり
- 助言を無視しても → 公表はされない
事後届出が不要となる例外(よく問われる)
以下の場合は、面積要件等に該当しても届出は不要です。
- 国や地方公共団体が契約当事者の場合
- 民事調停に基づき土地取引が行われた場合
- 農地法3条の許可を要する取引(農地取得の場合)
まとめ:事後届出制は国土利用法の重要ポイント
事後届出制は、宅建試験で「最重要」と言ってもいいテーマです。市街化区域での取引なら2,000㎡以上、市街化調整区域などでは5,000㎡以上など、区域別に数字を正確に押さえることが合格のカギ。
また、「契約かどうか」「対価の有無」「誰が届け出るのか」など、条件のパターン整理が大切です。例外や罰則の有無なども一緒に確認し、「出題されたらラッキー」と思える得点源にしましょう!
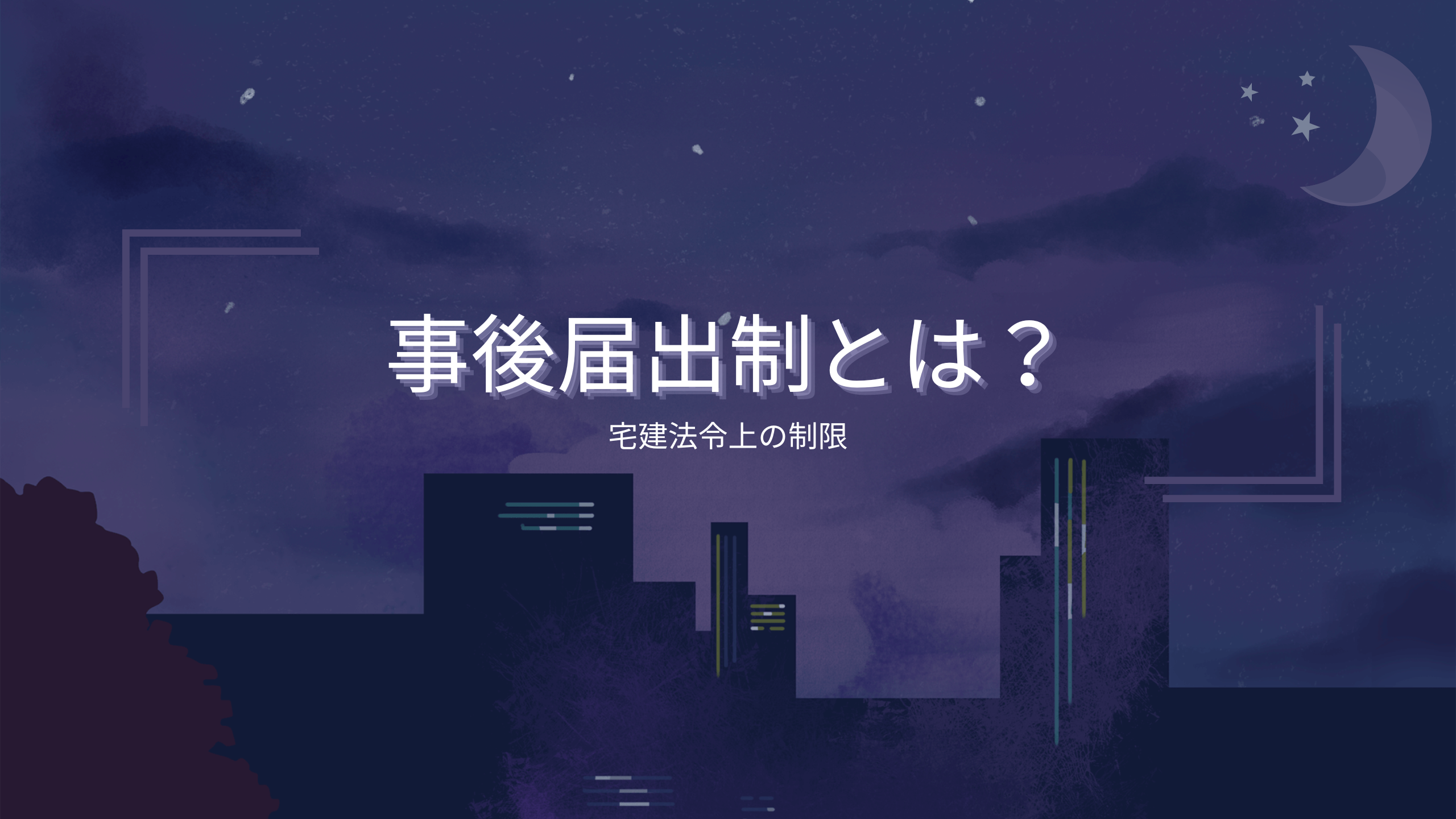

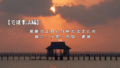


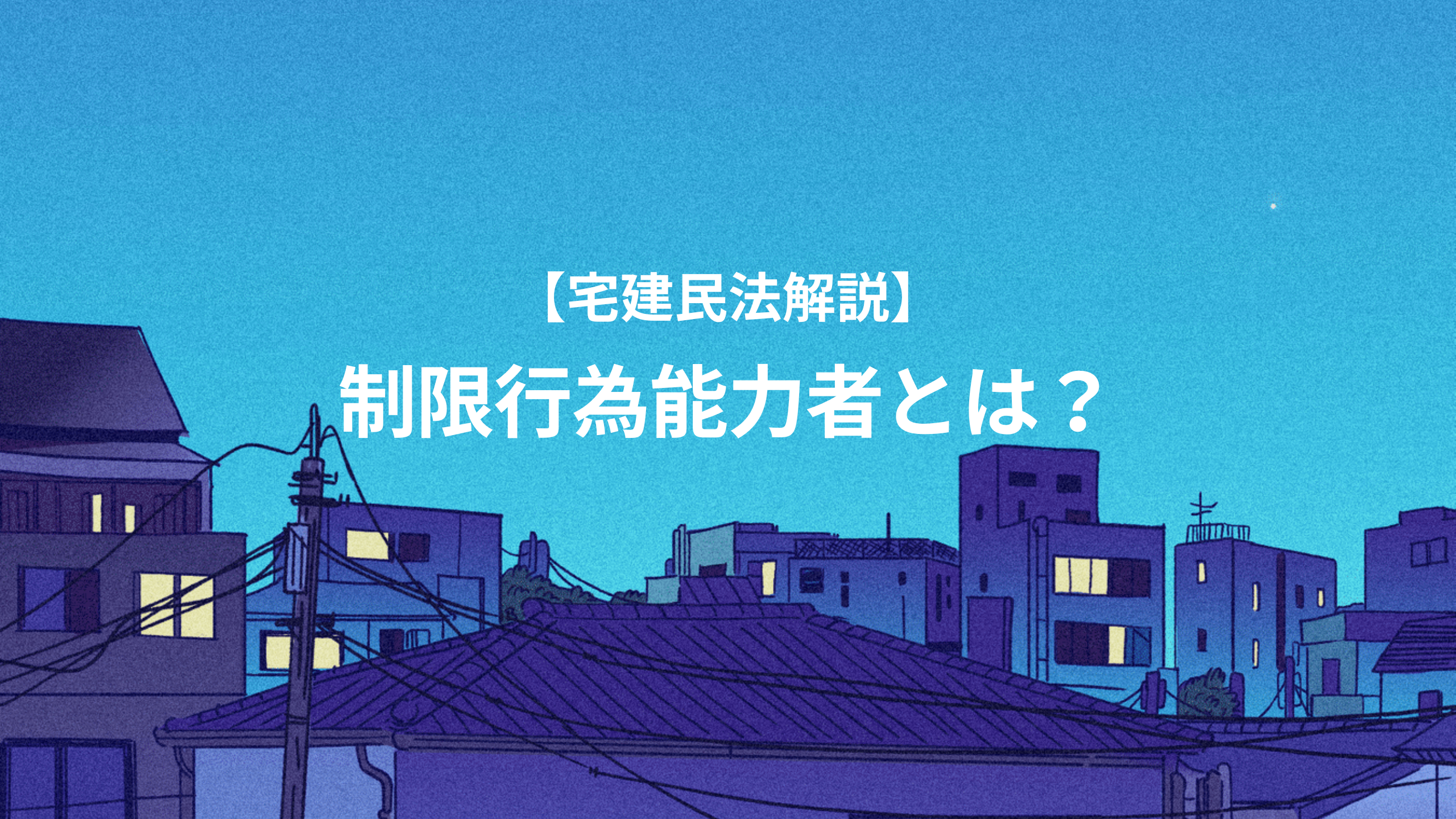


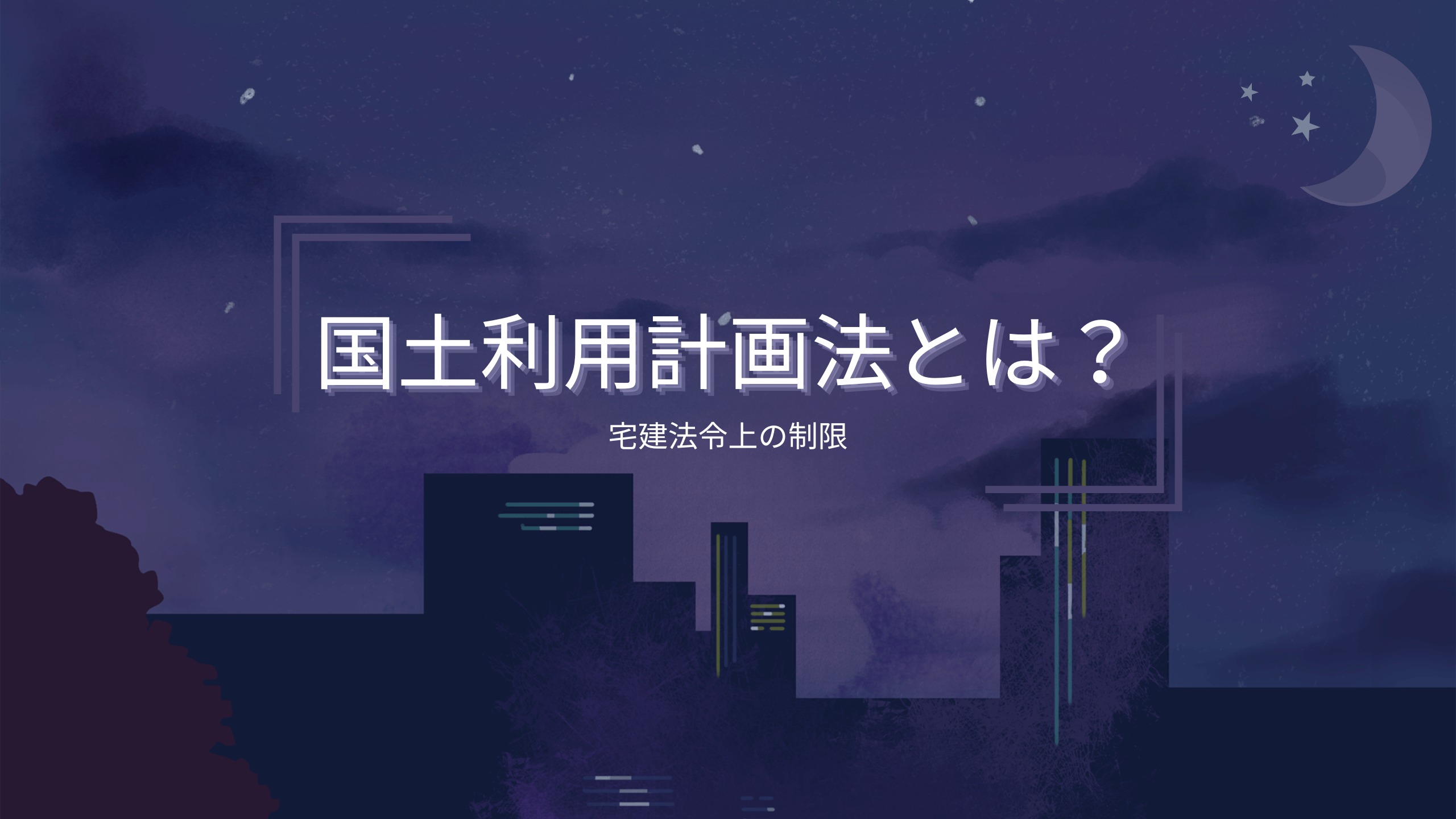

コメント