代理に関する知識の続きとして、「自己契約」や「双方代理」、そして「無権代理」「表見代理」について解説します。これらは試験でも頻出の重要ポイント。やや複雑ですが、ルールと例外、そしてパターンごとの処理を丁寧に整理すれば得点源になります。
📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
自己契約・双方代理の禁止とは
他人の代理人として契約を結ぶとき、自分自身や自分が代理人を務める別の人と契約をしてはいけないというルールです。
これは、当事者の利益が対立する可能性があるため、公平性を保つ目的で禁止されています。
- 自己契約:代理人が本人の代理として、自分自身と契約すること
(例:Aの代理人Bが、自分B個人にAの土地を売る契約を結ぶ) - 双方代理:1人の代理人が、売主と買主の両方の代理人として契約すること
(例:BがAの代理人であり、かつ買主Cの代理人として契約)
🔹例外:
- 本人があらかじめ「同意(許可)」していれば有効です(民法108条但書)。
無権代理とは
代理権がない人が、勝手に他人の名前で契約をすることです。
このような契約は、原則として本人には効力が生じません。
(例)Aの代理人であると偽ってBが土地を売る契約を結んだが、AはBに代理権を与えていなかった。
無権代理のパターン
- 最初から代理権がなかった
- 代理権が消滅していた(死後や解任後)
- 権限の範囲を逸脱していた(例:賃貸の権限で売買)
🔹ただし、本人が後から「追認」すれば有効になります。
追認がない場合は、相手方は「契約を取り消すこと」ができます(民法113条)。
また、代理人だと信じた相手方が損害を受けたとき、無権代理人は「損害賠償責任」を負うこともあります(民法117条)。
無権代理の効果・本人の対応
| 本人の対応 | 効果 |
|---|---|
| 追認する | 契約時にさかのぼって有効となる(遡及効) |
| 拒絶する | 契約は最初から無効のまま |
| 相手方が催告 | 一定期間内に追認するかどうか回答を迫る(無回答は拒絶とみなす) |
無権代理の相手方の救済手段
| 手段 | 内容 |
|---|---|
| 催告権 | 本人に対し、追認するか否かの回答を迫ることができる |
| 取消権 | 相手方が契約時に無権代理と知らなかった場合、契約を取り消すことができる |
| 履行請求・損害賠償請求 | 相手方が「善意無過失」であれば、無権代理人に対して請求が可能(履行か損害賠償) |
表見代理とは
見た目上は代理人に見える人が契約した場合に、本人に契約の効果が及ぶとされる制度です。
相手方が「正当な理由」で代理権があると信じて契約した場合に保護されます。
🔹表見代理の種類:
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 権限授与表示型 | 本人が第三者に「代理権がある」と誤信させた(例:名刺や看板で偽の表示) 代理権の消滅を知らずに契約(民法112条) |
| 権限逸脱型 | 権限の範囲内に見えて、実は逸脱(例:賃貸のつもりが売却までした) 代理権を越えた行為(民法110条) |
| 権限消滅後型 | かつてあった代理権が終了しているが、相手方が気づかず契約をした 無権代理でも、本人が自ら与えた外観に基づく(民法109条) |
(例)AがBに代理権を与えたあと、解除したが、Cがそれを知らずにBと契約した。
この場合、Cを保護するために、Aに契約の効果が及びます。
本人と無権代理人が同一人物になった場合
| ケース | 効果 |
|---|---|
| 本人死亡→無権代理人が単独相続 | 当然に有効(追認とみなされる) |
| 本人死亡→無権代理人が共同相続人の1人 | 追認により有効(全員の意思が必要) |
| 無権代理人死亡→本人が無権代理人を相続 | 当然には有効にならない(拒絶可) |
まとめ:代理は民法上の重要なルールがある
民法においては、他人の代理人として契約を行う際には、当事者間の利益の衝突や混乱を避けるために、いくつかの重要なルールが設けられています。
「自己契約」とは、代理人が自分自身と契約すること、「双方代理」とは、同じ代理人が売主と買主など契約当事者双方を代理して契約することです。これらは利益がぶつかりやすいため、原則として禁止されています。
「無権代理」とは、代理権がない者が勝手に代理人として契約を結ぶことで、原則としてその契約は無効ですが、本人が後から追認すれば有効になります。
「表見代理」とは、外見上は代理権があるように見えるケースで、善意の相手方を保護するために、有効な契約とみなされることがあります(例:代理権が既に消滅していた場合など)。
これらの違いやルールを理解することで、契約トラブルを未然に防ぐことができます。
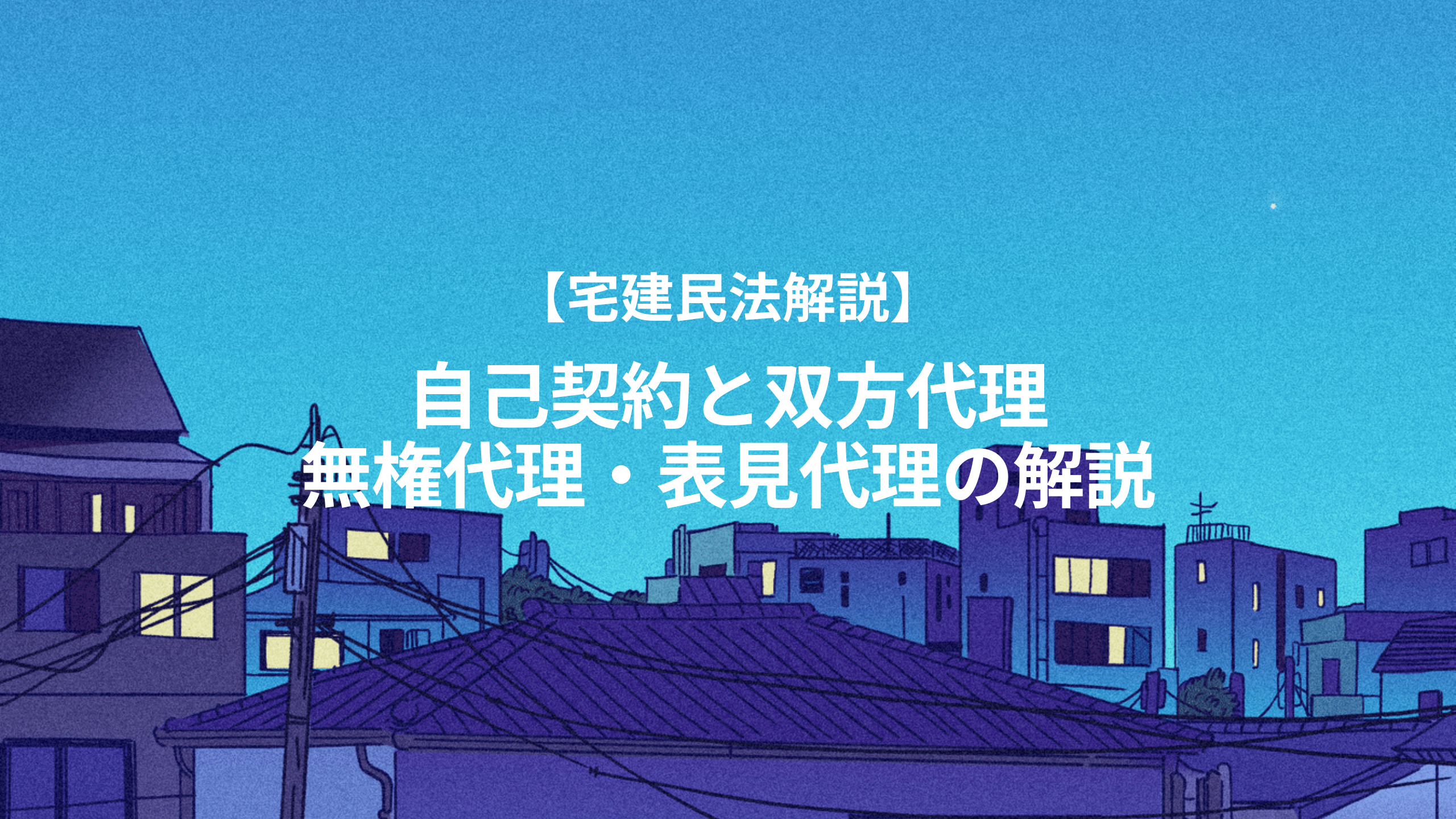

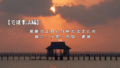


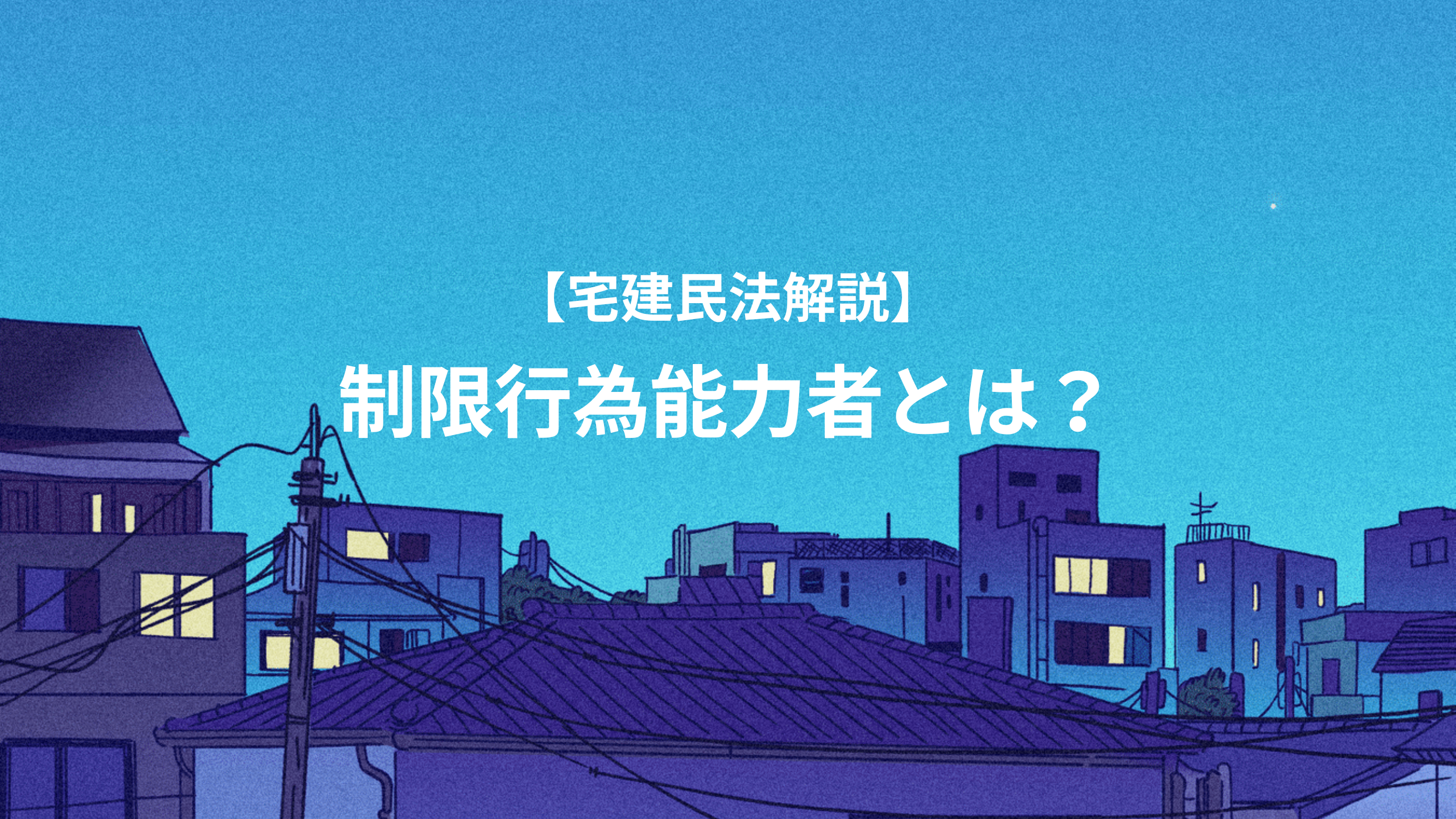


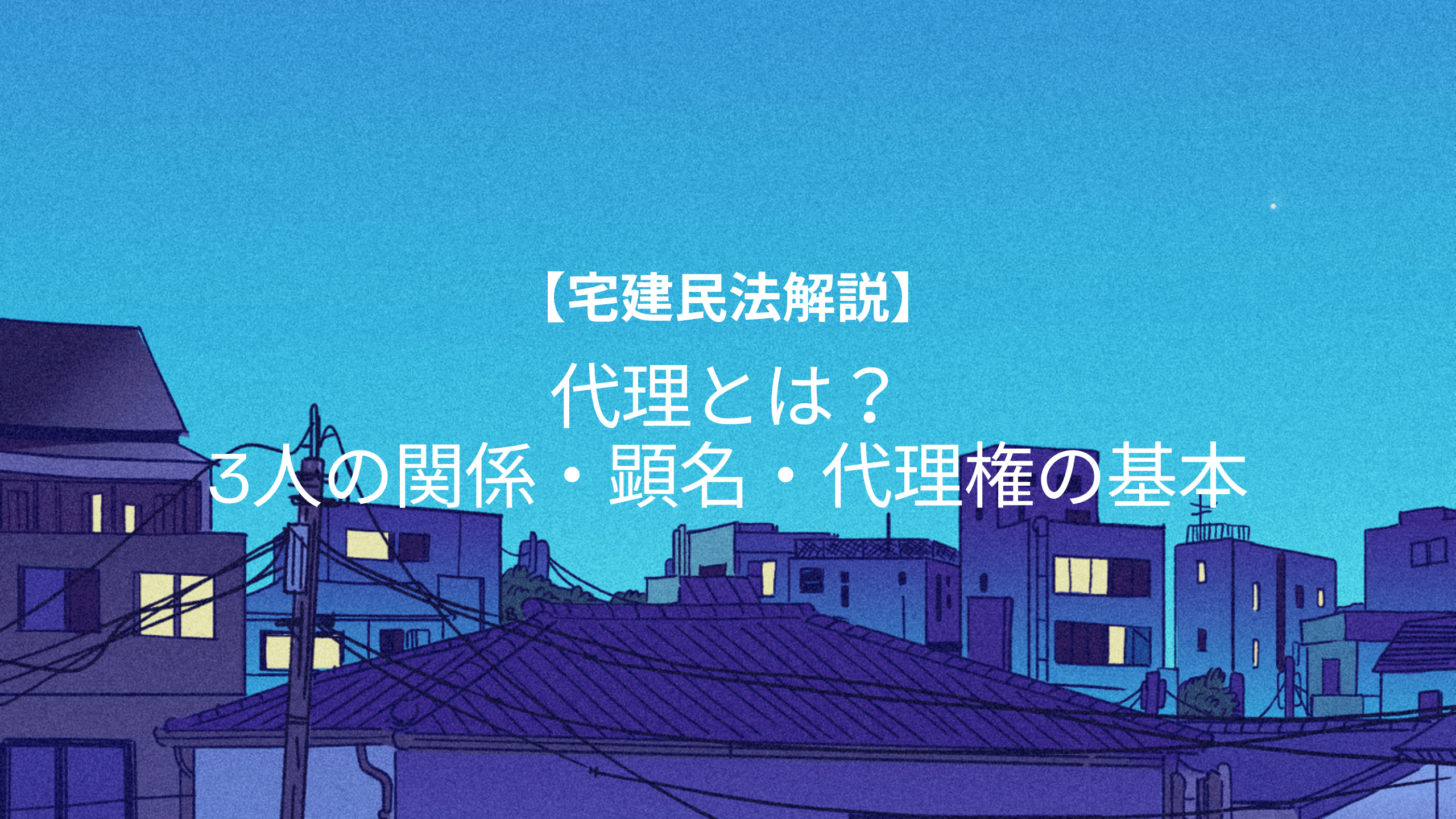
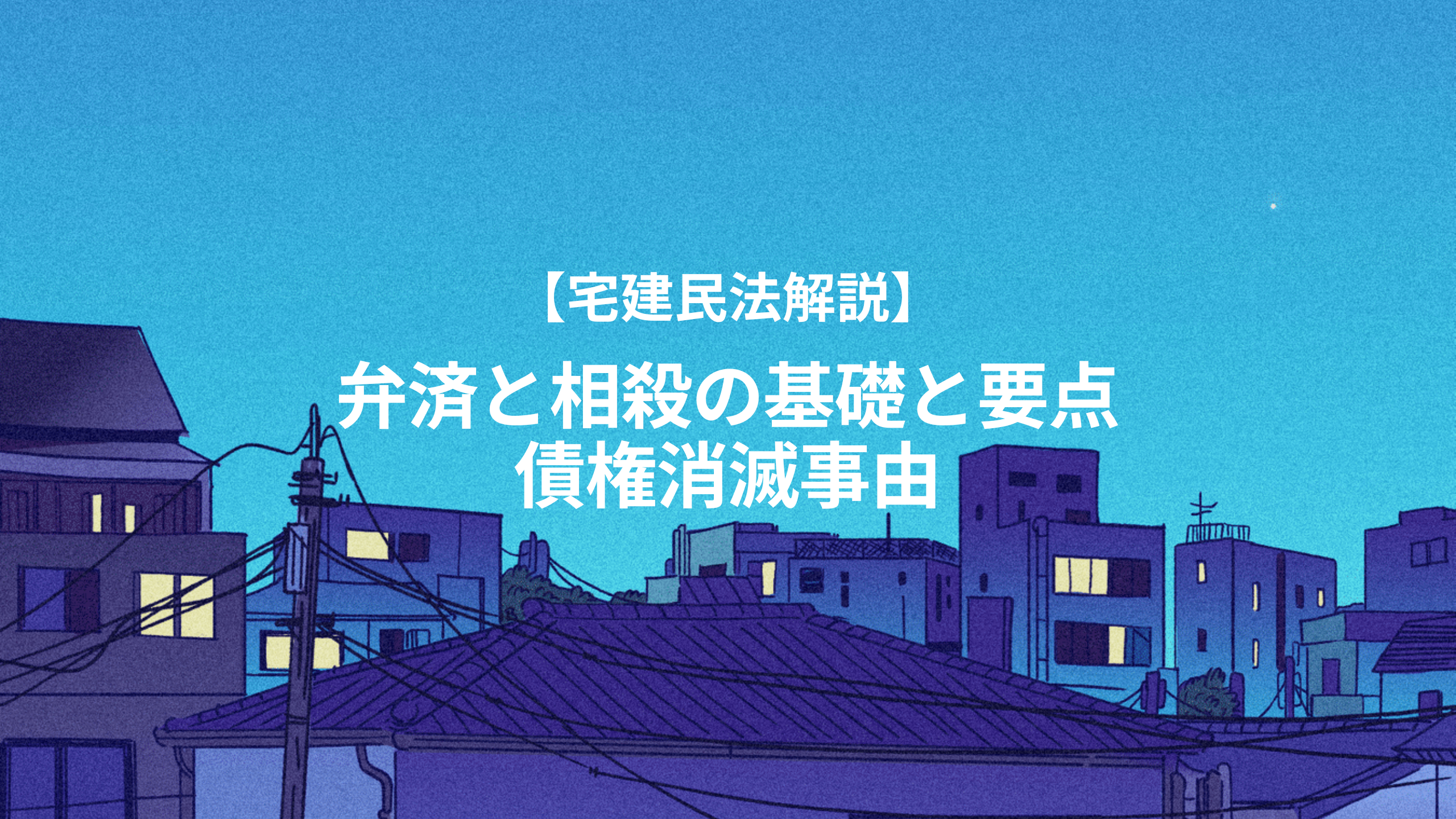
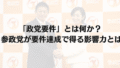
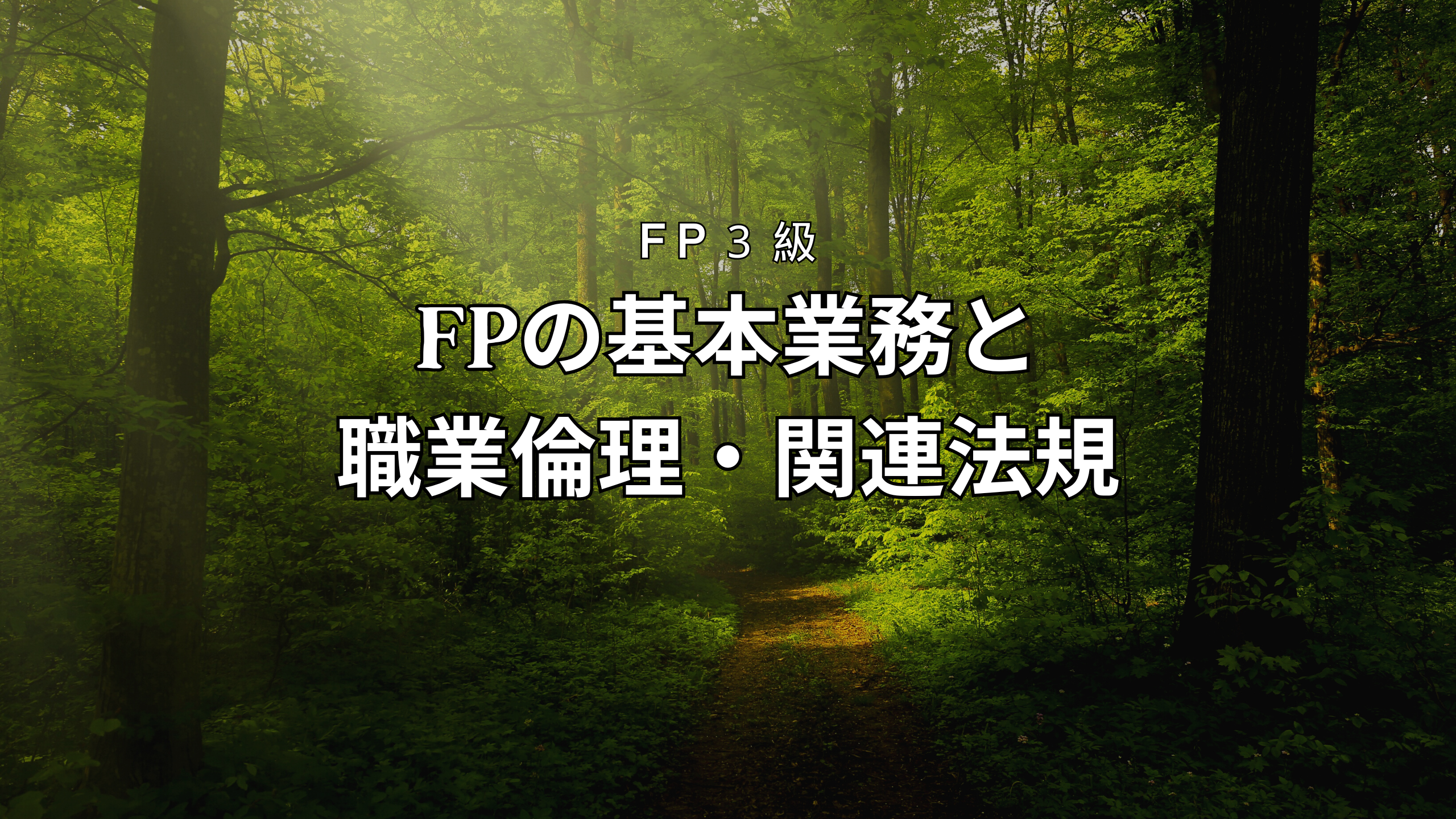
コメント