病気やケガ、出産、介護など、人生のさまざまなリスクに対して備える「社会保険」。
日本は、国民皆保険制度というものがありますので、皆さんも保険証お持ちかと思います。
FP3級では、社会保険の制度ごとの仕組みや給付内容、保険料の負担などが出題されます。
この記事では、医療保険・介護保険を中心に、基本的な知識と計算例を交えて解説していきます。
📘 FP3級の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
社会保険とは?
社会保険とは、公的機関が提供する保険制度で、主に医療・介護・年金に関わる保障を指します。
その中でも、FP3級で特に重要なのが医療保険と公的介護保険です。
医療保険の種類と概要
医療保険は、加入者が病気やケガをした場合に必要な医療費を補償する制度です。
以下のように対象者別に分かれています。
| 種類 | 対象者 |
|---|---|
| 健康保険 | 会社員とその家族 |
| 国民健康保険 | 自営業者など |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上 |
健康保険の主な給付
健康保険からは以下の6つの主な給付があります:
- 療養の給付・家族療養費
- 高額療養費(自己負担限度額超過分の返金)
- 傷病手当金(病気・ケガによる休業補償)
- 出産育児一時金(1児につき50万円)
- 出産手当金(休業中の収入補填)
- 埋葬料(被保険者:5万円/被扶養者:5万円)
高額療養費と傷病手当金
高額療養費
長期的な入院や大掛かりな手術などで月間の医療費が一定額を超えた場合、その超過額について請求をすることで後から返金してもらうことができます。
| 所得区分(標準報酬月額) | 自己負担限度額 |
| 83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
| 53万円~79万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
| 28万円~50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
| 26万円以下 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
- 医療費:2,000,000円
- 標準報酬月額:500,000円
- 自己負担限度額:80,100円+(2,000,000円-267,000円)×1%=97,430円
- 実際に支払った3割:600,000円
- 返金額:600,000円-97,430円=502,570円
傷病手当金
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
- 標準報酬月額:45万円
- 休業日数:20日(3日除外)→18日
- 1日あたりの支給額:10,000円
- 支給額:180,000円
医療保険制度
医療にかかる保険を医療保険と呼び、医療保険にはさらに以下の3つに分けられます。
健康保険
- 全国健康保険協会が保険者となる、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)
- 健康保険組合が保険者となる組合管掌健康保険(組合健保)
- 保険料は被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に保険利率をかけ、その金額を会社と被保険者で半分ずつ負担する労使折半
会社勤めの方(協会けんぽ等に加入)が退職後は、医療保険の選択をする必要があります。
- 任意継続保険(2年間、全額自己負担)
- 国民健康保険(加入制限なし、全額自己負担)
- 家族の被扶養者(保険料負担なし)
国民健康保険
- 自営業者や退職者などが加入
- 保険者:都道府県・市区町村 or 国保組合
- 給付内容は健康保険と同様(ただし出産手当金・傷病手当金はなし)
後期高齢者医療制度
- 対象:75歳以上
- 自己負担:原則1割(現役並み所得者は3割)
- 保険料:年金からの天引き(都道府県が決定)
公的介護保険
介護が必要と認定された場合に必要な額が給付される制度を介護保険と言います。
| 区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 対象者 | 65歳以上 | 40〜64歳 |
| 保険料 | 市区町村が決定(年金天引きなど) | 健康保険料に含まれる(例:1.79%) |
| 給付対象 | 要介護・要支援状態 | 老化が原因の要介護状態 |
| 自己負担 | 原則1割(高所得者は2割または3割) | 原則1割(高所得者は2割または3割) |
まとめ:社会保険の基本をおさえて得点源に!
社会保険は、私たちの生活を支える公的な仕組みです。
FP3級では「高額療養費」「傷病手当金」「介護保険の対象者」など頻出テーマが多いため、計算例も含めて正確に理解しておくことが重要です。
出題傾向としては、語呂合わせや定型パターンで覚えておくと得点しやすい分野なので、ここでしっかりマスターしておきましょう!
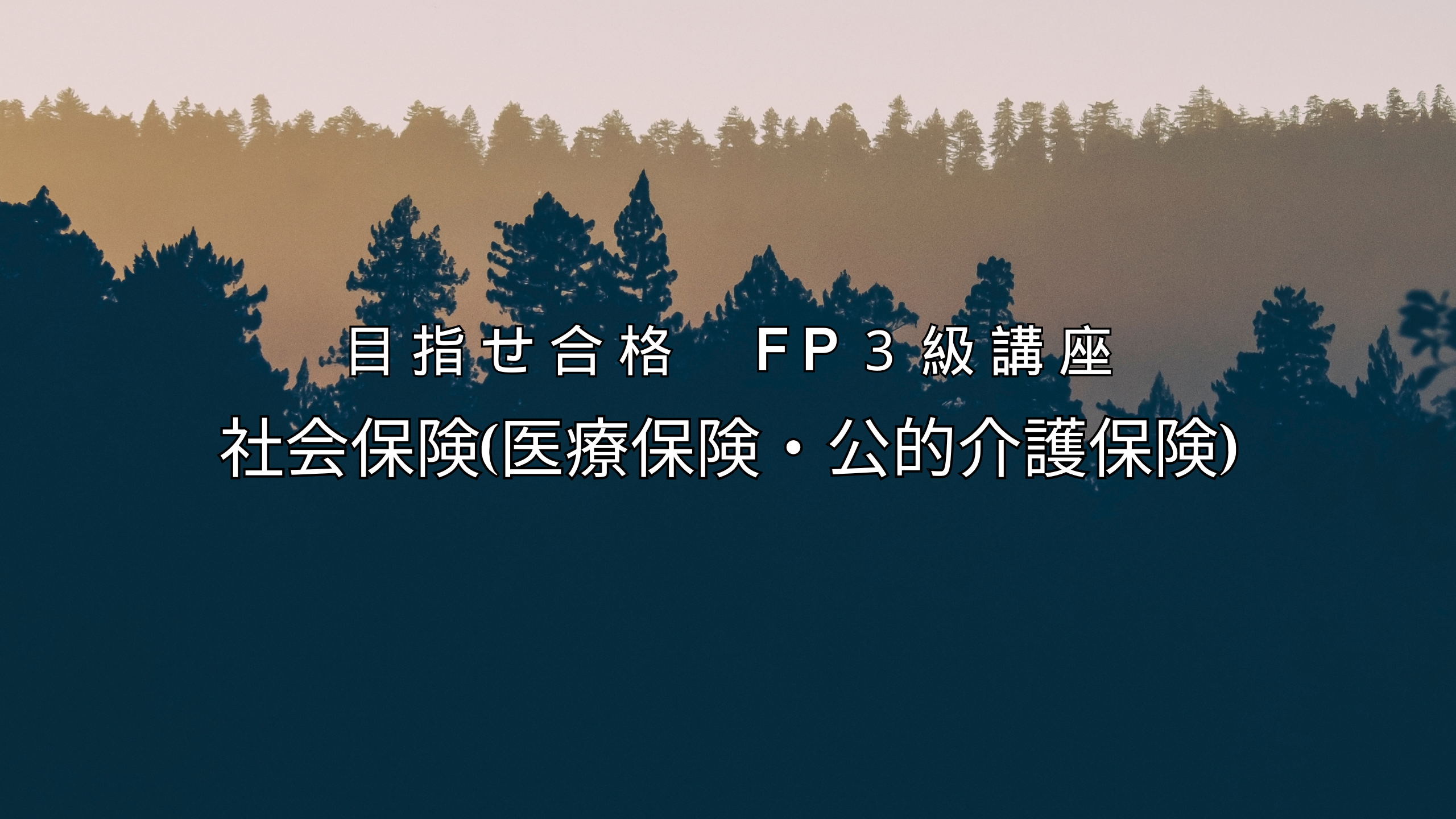


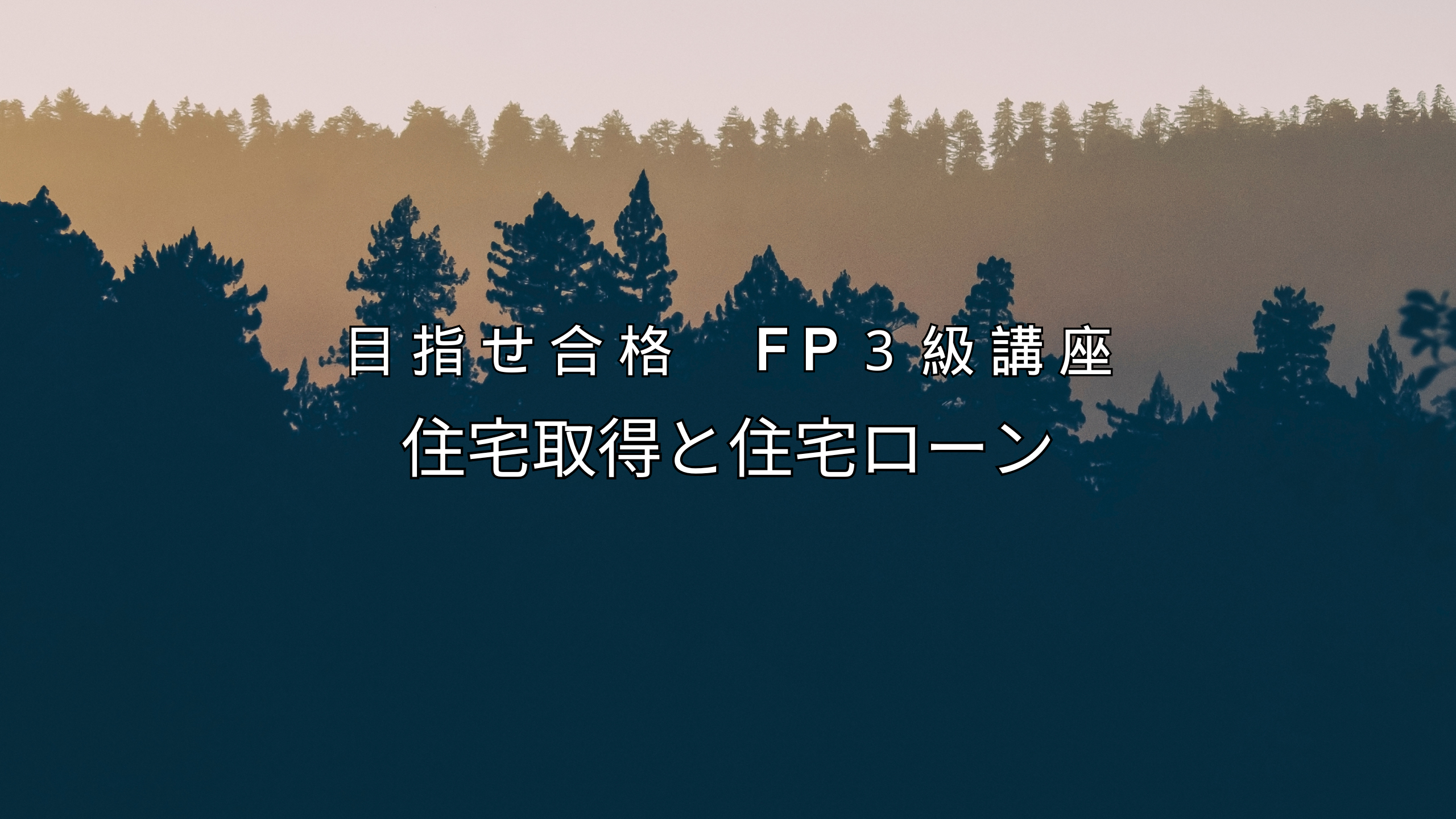

コメント