マイホームの購入は、多くの人にとって人生最大の買い物です。その分、必要な知識も多く、自己資金や住宅ローンの仕組み、公的支援制度などを理解しておくことが大切です。
FP3級では、これらの基本をしっかり押さえておくことが得点アップにつながります。本記事では、住宅取得と住宅ローンに関する基礎知識をやさしく解説します。
📘 FP3級の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
住宅取得にかかる自己資金
住宅を購入する際、物件価格の8割程度まで住宅ローンを組むことができますが、残りの2割は「頭金」として現金で用意する必要があります。
さらに、登記費用・不動産取得税・仲介手数料などの「諸経費」が物件価格の約1割かかるため、合計で約3割の自己資金が必要です。
※4,000万円の新築物件を購入する場合、20%の頭金(800万円)と諸費用(約120万円~200万円)を考慮すると、約1,000万円程度の自己資金が必要になります。
自己資金の準備:財形住宅貯蓄
自己資金の準備方法として、「財形住宅貯蓄」があります。
これは勤労者が毎月給与から積み立てる制度で、一定条件を満たすと利子が非課税になります。
目的は、マイホームの取得や増改築などの費用に限定されます。
- 限度・・・一定要件を満たすことで元利合計が550万円に達するまで、利息に税金がかかることなく貯蓄できます。
- 条件・・・利用できるのは、勤労者財産形成促進法上の勤労者で、契約申し込み時の年齢が55歳未満の人に限られます。
住宅ローン
住宅ローンの金利には、主に次の3種類があります:
- 固定金利型:返済期間中ずっと金利が一定
- 変動金利型:金利が半年ごとに見直される
- 固定金利選択型:一定期間だけ金利が固定され、その後は変動に移行
それぞれ、金利の変動リスクや返済計画に大きく関係するため、理解が必要です。
返済方法:元利均等と元金均等
住宅ローンの返済方法は次の2種類です:
- 元利均等返済:毎月の返済額が一定。返済開始当初は利息の割合が多い
- 元金均等返済:毎月の元金部分は一定で、総返済額が少なく済むが初期負担は大きい
試験では「元利均等は総返済額が多くなる」という点がよく問われます。
公的・民間の住宅ローンの種類
代表的なローンは以下の通りです:
- 財形住宅融資(公的)
財形住宅貯蓄を1年以上している人が利用できる。金利は固定型。 - フラット35(民間連携)
住宅金融支援機構と民間金融機関の連携。全期間固定金利が特徴。
繰上げ返済と借換え
返済途中で一部の借入金を早めに返す「繰上げ返済」には以下の効果があります:
- 期間短縮型:返済期間を短縮して、利息の総額を減らす
- 返済額軽減型:毎月の返済額を軽減する
また、金利が高いローンから低いローンに借り換えることで利息の負担を軽減できます。ただし、公的ローンへの借換えは原則不可です。
団体信用生命保険(団信)
住宅ローンを借りる際には、債務者が死亡した場合に残債を保険金で返済する「団体信用生命保険」に加入するのが一般的です。
遺族がローン返済に困らずにすむというメリットがあります。
まとめ
住宅取得には物件価格の約3割の自己資金が必要であり、ローンの種類・返済方法・金利の選択・繰上げ返済などによって負担が大きく変わります。
FP試験では、財形住宅融資・フラット35・団信などの特徴を正確に理解しておくことが大切です。
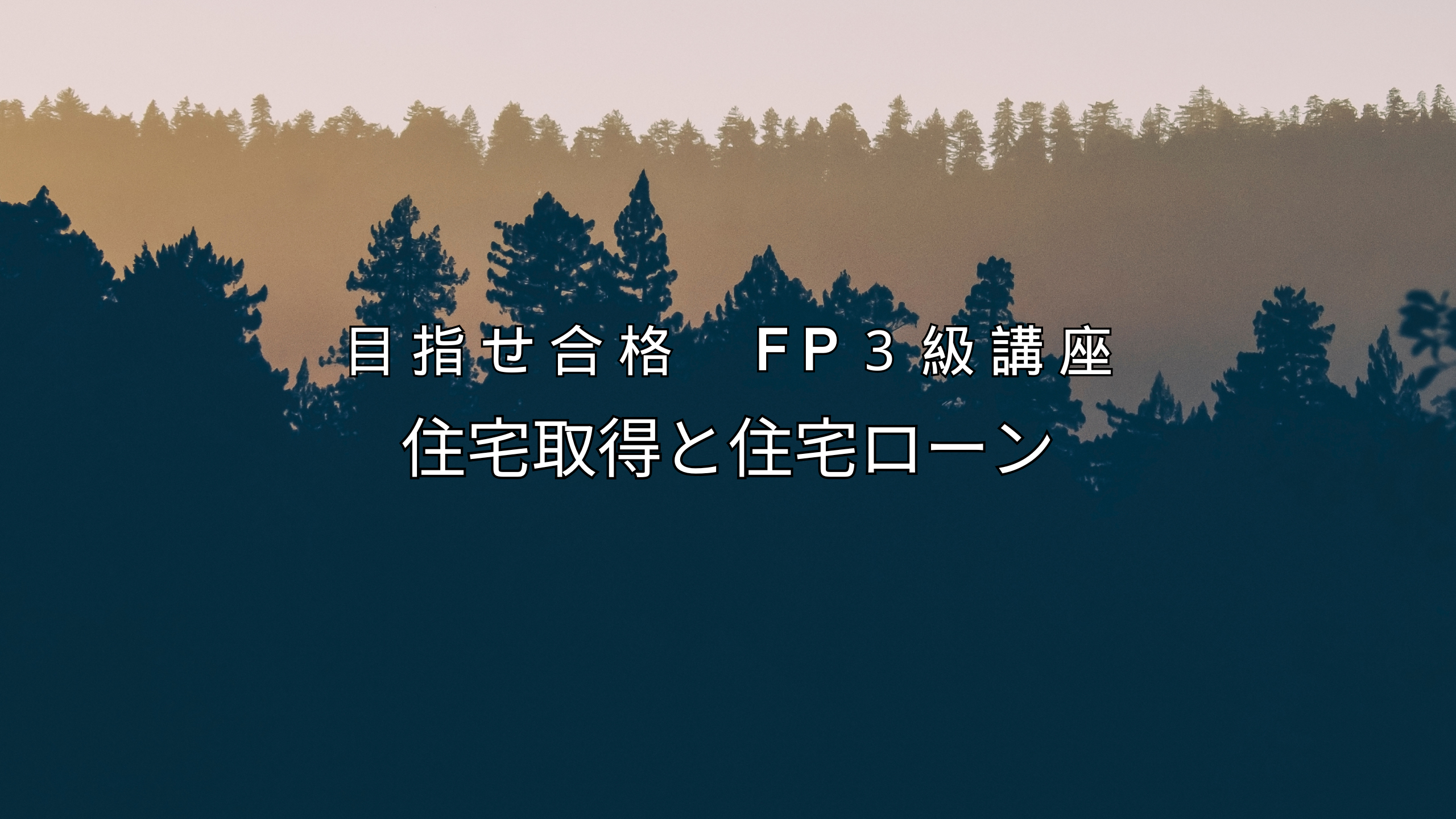


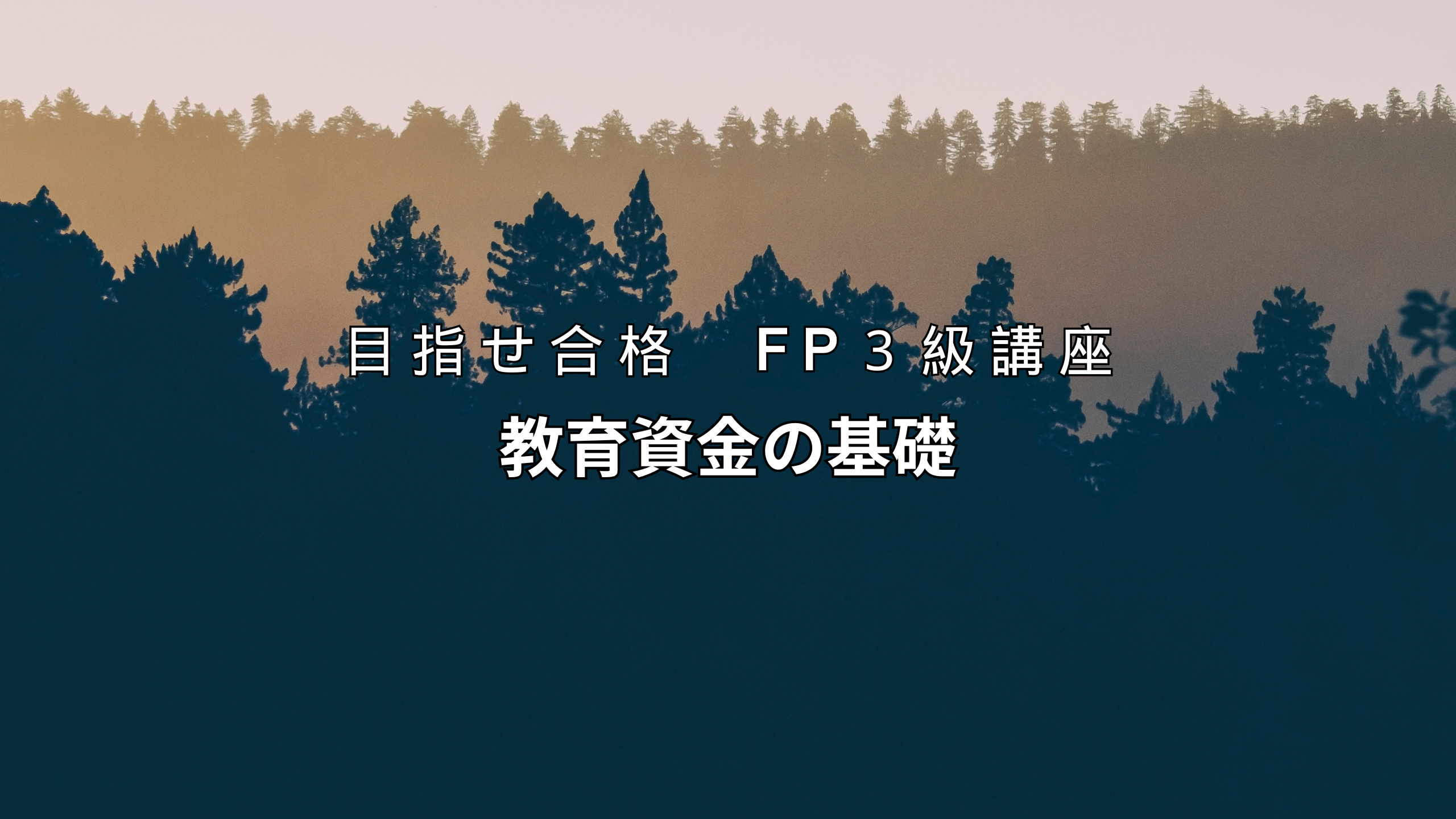
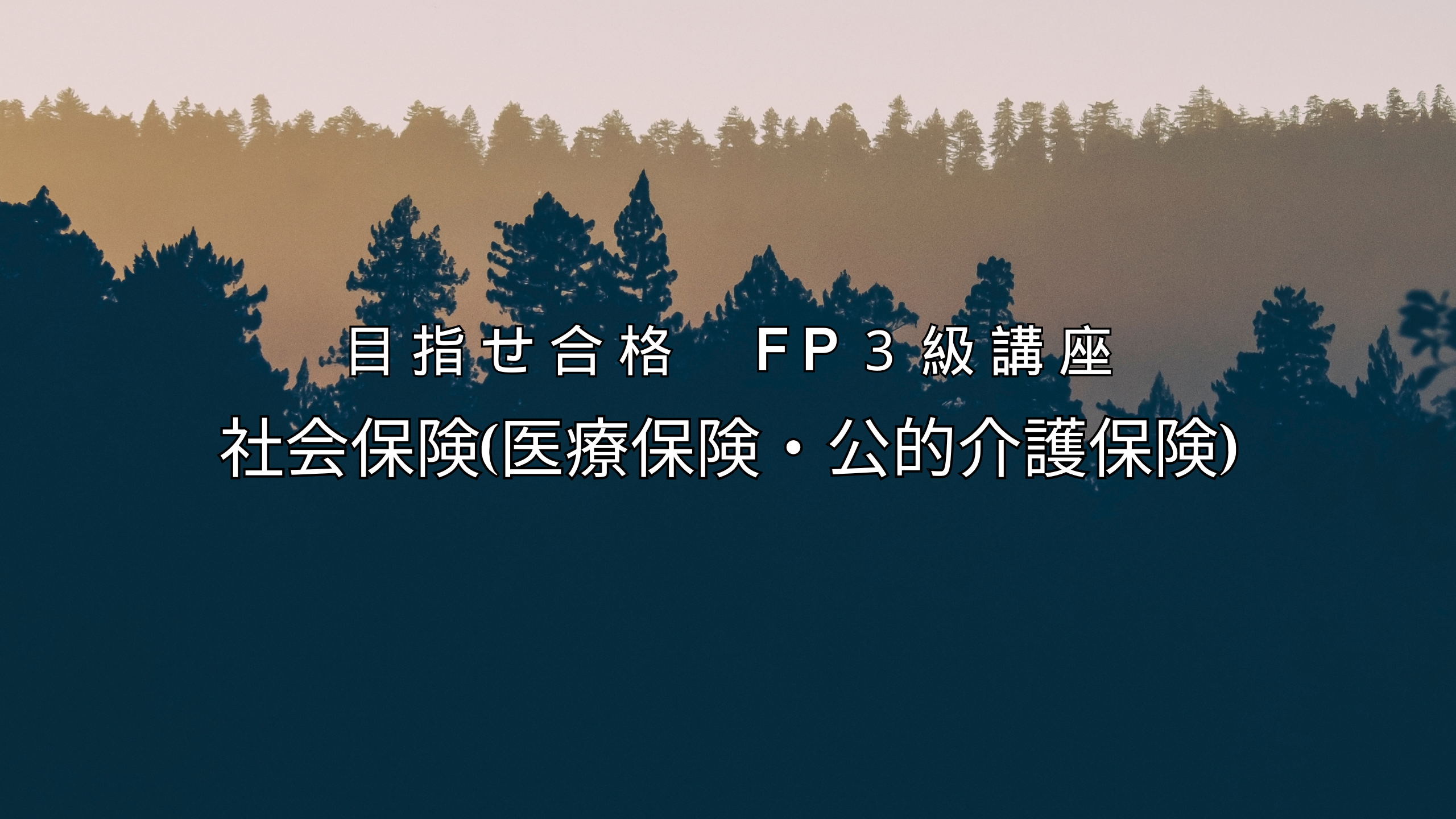
コメント