宅建試験の頻出テーマである「無効」「取消」そして「追認」。本記事では、それぞれの定義・違い・効果・第三者との関係・消滅時効などを体系的にまとめました。学習の基盤を固め、応用問題への対応力を高めましょう。
📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
契約が「無効」「取消可能」なケース
- 公序良俗違反
- 原始的不能
- 意思無能力
- 心裡留保(相手が悪意または有過失の場合)
- 通謀虚偽表示
- 錯誤(要件を満たす場合)
- 行為無能力
- 詐欺
- 強迫
- 錯誤(重要な錯誤で表意者に重過失がない場合)
無効と取消の比較
| 比較項目 | 無効 | 取消 |
| 主張できる者 | 誰でも主張可能 | 取消権者のみ(被害者・代理人・承継人) |
| 効果 | 最初から無効 | 契約時にさかのぼって無効となる |
| 消滅の有無 | 放っておいても無効 | 時効により消滅(追認可時から5年/行為時から20年) |
| 第三者保護 | 原則なし(例:虚偽表示の場合の善意第三者) | 詐欺・錯誤取消では善意無過失の第三者に保護あり |
■ 取消権者とは?
- 制限行為能力者(意思能力があるとき)
- 詐欺・強迫・錯誤の表意者
- 上記の代理人(親権者、後見人など)
- 上記の承継人(相続人など)
無効・取消の効果(履行後) 契約が無効や取消となった場合
すでに履行がなされていたなら、その返還が必要です。この返還義務は同時履行の関係となります(互いに返還しなければならない)。
現存利益の考え方
(行為無能力者) 未成年者などの制限行為能力者が契約を取り消した場合、返還義務は「現に利益を受けている範囲」に限定されます。
例:未成年者が30万円を借りて以下の用途に使った場合
- 借金返済:20万円(利益あり)
- 食費:5万円(利益あり)
- パチンコ:5万円(浪費) → 返還義務は25万円分のみ(現存利益)
※ 善意・悪意を問わず、制限行為能力者にはこのルールが適用されます。
無効と取消の二重効 無効と取消の両方の要件を満たす場合
無効・取消どちらを主張しても構いません。
例:幼稚園児が高額な不動産を親の承諾なく購入した → 意思無能力による無効 or 行為無能力による取消、どちらでもOK。
取消権の消滅時効
- 追認可能な時点から5年
- 行為時から20年
※ いずれか早く経過した時点で取消権は消滅します。
例:5歳児が契約 → 成人後に追認可能な年齢(18歳)+5年 → 23歳で取消権消滅。 途中で代金支払などをすれば、それが法定追認となり即時消滅する点にも注意。
各意思表示の効力と第三者保護
| 類型 | 当事者間の効力 | 第三者保護の可否 |
|---|---|---|
| 心裡留保 | 原則有効、相手が悪意・有過失なら無効 | 無効時:善意第三者に対抗不可 |
| 虚偽表示 | 無効 | 善意第三者に対抗不可(過失は問わない) |
| 錯誤 | 取消可能(重要部分・重過失なし) | 善意無過失の第三者に対抗不可 |
| 詐欺 | 取消可能(相手が善意無過失なら取消不可) | 善意無過失の第三者に対抗不可 |
| 強迫 | 取消可能(相手が善意でも取消可能) | 常に第三者にも対抗可能 |
追認とは?
追認とは、取消可能な法律行為を取り消さずに有効とする意思表示のことです。一度追認すれば、その行為は最初から有効であったものとされ、もはや取り消すことはできません。
追認できる者と要件
- 無能力者本人:能力を回復後、かつ取消原因が消滅し、取消権の存在を認識した状態
- 法定代理人・保佐人・補助人:随時可能(取消原因の消滅を要しない)
法定追認の例(意思表示なしでも追認とみなされる行為)
| 行為内容 | 備考 |
| 一部または全部の履行 | 代金支払・物の受取など |
| 履行の請求 | 相手に「履行せよ」と請求 |
| 担保の提供 | 保証人をつける・抵当権を設定する |
| 権利の譲渡 | 自分の取得権を第三者に譲る |
| 強制執行の実行 | 債権者として執行する |
| 更改(契約内容の変更) | 代替物や条件を変更して支払う等 |
※ 制限行為能力者本人による行為は、無能力を脱していなければ法定追認になりません。
催告による追認の確定
相手方から「1ヶ月以上の期間内に追認の可否を明らかにせよ」と催告されたにも関わらず返答しなかった場合、追認したものとみなされ契約は確定します。
まとめ:無効・取消・追認を正しく理解しよう
無効・取消・追認は宅建試験で頻出する重要論点です。
それぞれの定義や効果、第三者保護との関係、消滅時効、法定追認の具体例までを体系的に整理しました。
宅建に合格するために理解不可欠な分野のため必ず覚えるようにしましょう。また、実務や応用問題にも役立つ基礎力をしっかり身につけていきましょう。


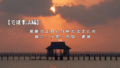


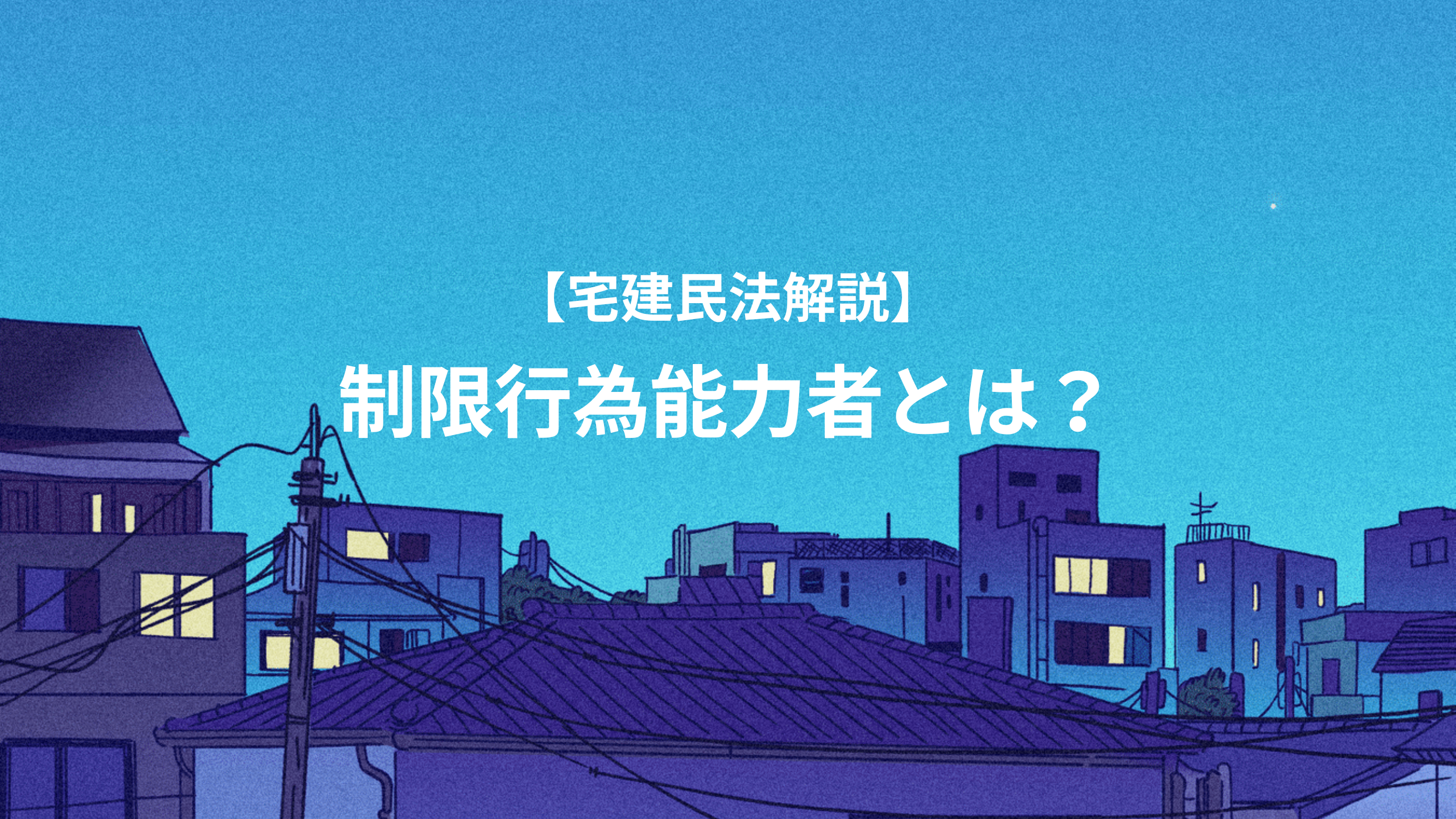


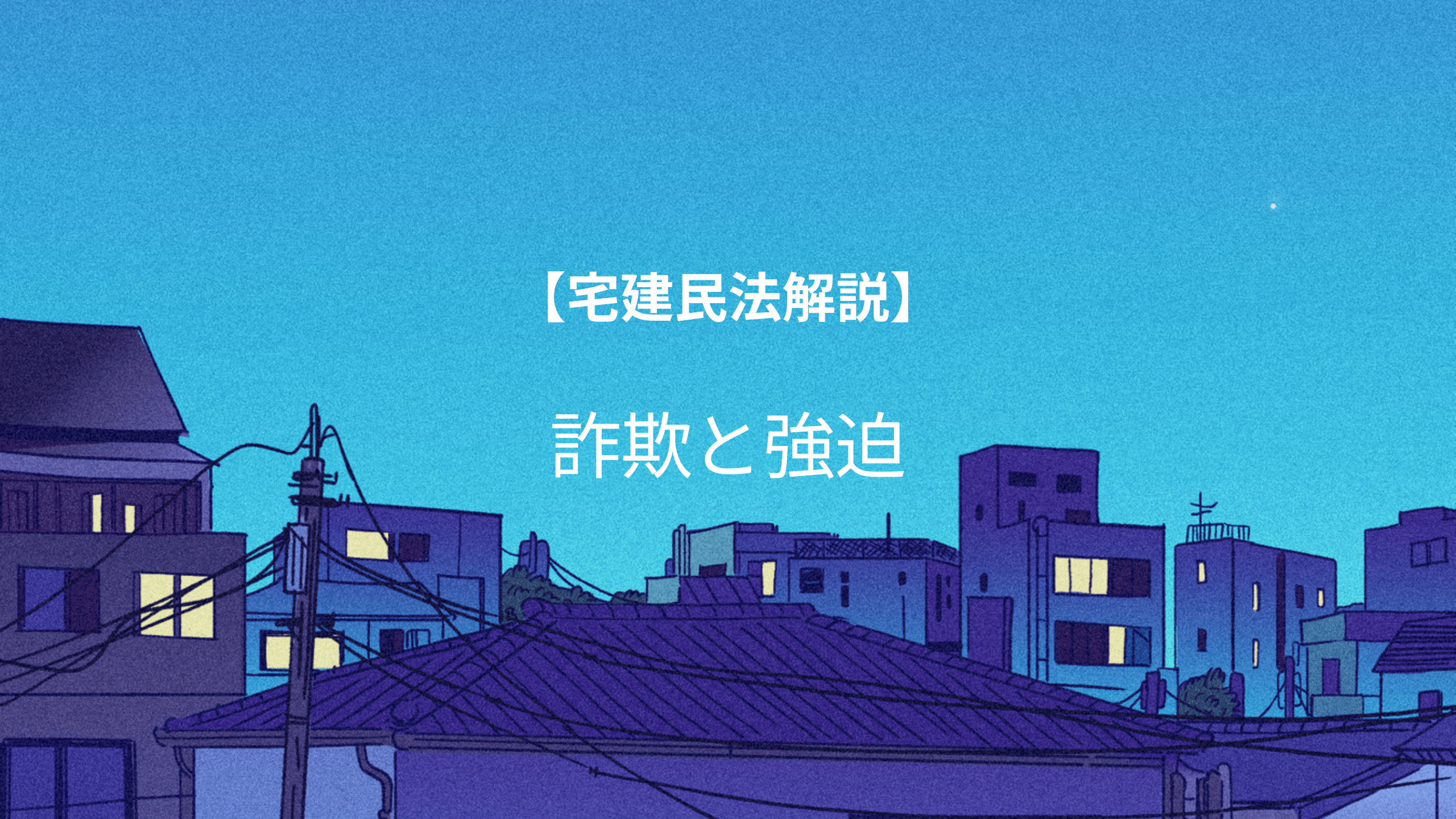
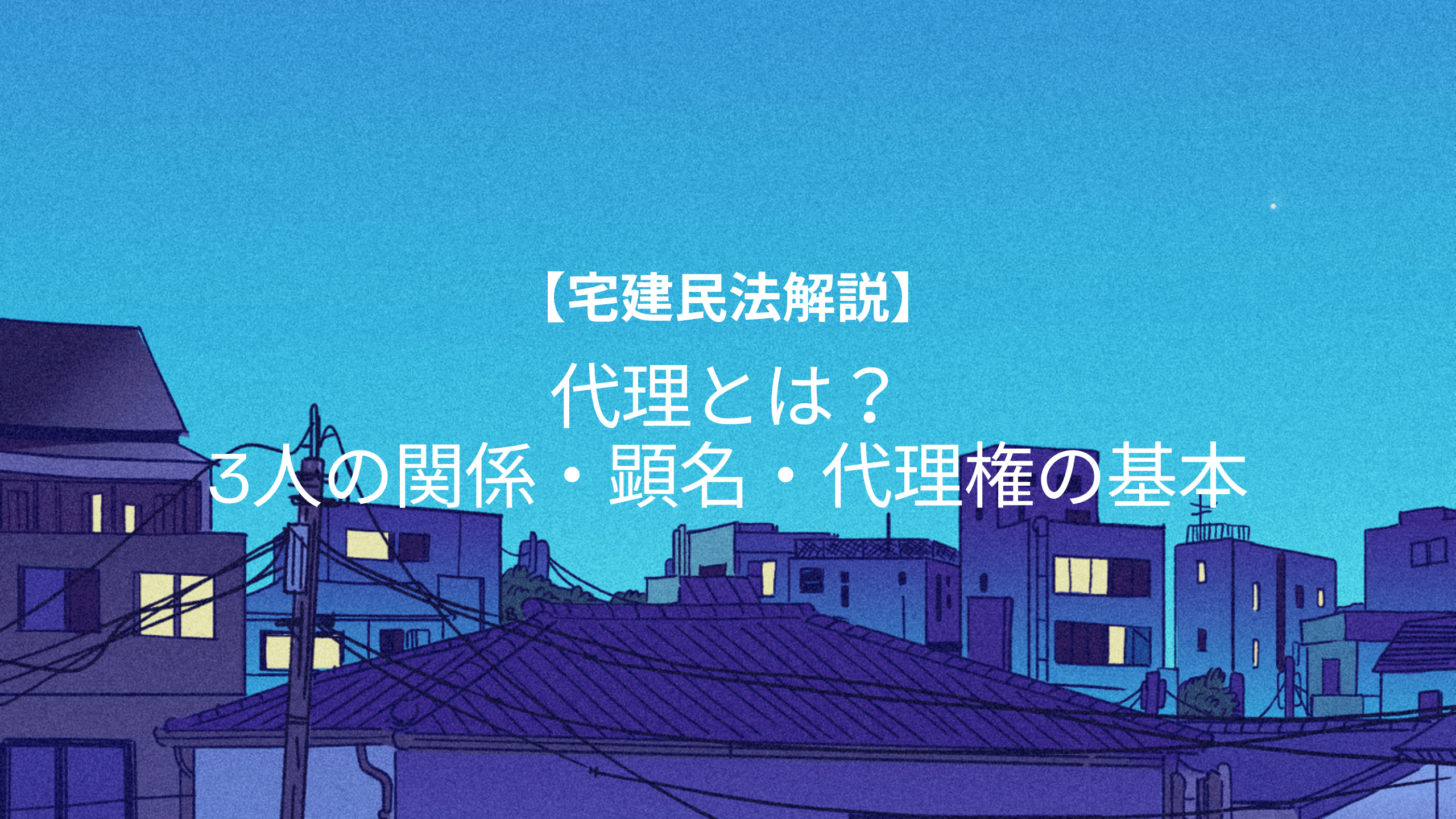

コメント