宅建試験では、契約が「どのように成立し」「どのような場合に無効や取消しとなるのか」がよく問われます。ここでは、契約の成立から有効性の判断、民法上の契約ルールまでをわかりやすく解説します。また、契約は以下の原則があることも理解しておきましょう。
- 契約締結の自由
- 契約内容決定の自由
- 相手方選択の自由
- 契約方式の自由(口頭契約も有効)
📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
契約の成立要件とは?
契約の成立には、原則として、申込みと承諾という2つの意思表示の合致が必要です。つまり、一方からの契約内容の提示(申込み)に対して、相手方がそれに同意する意思表示(承諾)をすることで契約が成立します。この意思表示は、口頭でも書面でも、また電子メールやLINEのような電子的な手段でも有効です。
ただし、契約が有効に成立するには、法律的に適切で妥当な内容であることが必要です。
また、契約当事者の意思表示に問題(瑕疵)がないことも重要です。
もしこれらの条件に反する場合、契約は以下のように扱われます:
- 内容に問題がある → 無効
- 意思表示に問題がある → 取消し可能
特に民法90条では、「公序良俗(公共の秩序や善良な風俗)に反する契約は無効」と定められています。
たとえ契約が自由に結ばれるとしても、社会的に受け入れがたい契約は成立しても無効となります。
無効になるケース
- 公序良俗違反(民法90条)
- 犯罪行為の契約(例:殺人依頼)
- 愛人契約、人身売買、ねずみ講 など
- 原始的不能
- 初めから実現不可能な内容(例:焼失済み建物の売買、生身で空を飛んだら100万円 など)
※改正民法により、原始的不能でも「債務不履行による損害賠償請求」が可能になる場合があります。
契約申込みに関するルール
契約を申し込んだあと、「やっぱりやめたい」と思うこともあるかもしれません。しかし、相手に申込みが届いた時点で、もう契約が成立してしまう可能性があるため、そう簡単に撤回できるとは限りません。
なぜなら、申込みを受けた相手はその内容を信じて準備を進めたり、他の申込みを断ってその契約を選んだりすることがあるからです。もし申込者が簡単に撤回できると、相手に不利益や損害を与えてしまうリスクがあるのです。
そこで民法では、申込みの撤回に関するルールを明確に定め、契約の公平性を保っています。以下でそのルールをわかりやすく解説します。
承諾期間がある場合
- 申込みをした人(申込者)は、その期間中は申込みを撤回できません。
- ただし、「撤回するかもしれない」とあらかじめ言っていた場合は撤回できます。(撤回権の留保)
- 相手から期限内に返事がなければ、申込みは自動的に無効になります。
Aさん(申込者)がBさん(相手方)に「この家を1000万円で売ります。3日以内に返事をください」と言ったとします。その場合Aさんは勝手に撤回できないということです。
承諾期間がない場合
- 明確な期限はないが、相手が返事をするのに必要相当な期間時間が過ぎるまでは撤回できない。
- 改正民法により、「遠くの人(隔地者)」に限らず、すべての申込みにこのルールが適用されます。
- 「撤回するかも」とあらかじめ伝えていた場合は、途中で撤回してOK。
会話で申込みをした場合(口頭など)
- 会話中であればいつでも撤回できます。
- でも、会話が終わった後に返事がなければ、その時点で申込みは失効します。
- ただし、「会話が終わっても申込みは生きてるよ」と伝えていた場合は失効しません。
申込者が死亡・制限行為能力者になった場合
- 申込者が申込みの通知を発したあとに、死亡、意思能力喪失、制限行為能力者となった場合などは、承諾通知を発するまでにその事実が生じたことを被申込者が知ったときに限り、その申込みは効力を生じません。
典型契約13種類(民法上定められた基本契約)
民法では、無数にある契約類型から、日常的に使われることが多い13種類の類型について、規定を設けています。これを典型契約(有名契約)といいます。
それぞれの詳しい内容については別途解説しますので、どのような内容かを簡単に目を通してください。
| 契約名 | 内容(ざっくり説明) |
|---|---|
| 売買 | 財産を売って代金をもらう |
| 贈与 | 無償であげる |
| 交換 | お互いに物を交換 |
| 消費貸借 | 金や物を借りて同じ物を返す |
| 使用貸借 | 無償で借りて返す |
| 賃貸借 | 借りて代金を払う |
| 雇用 | 働いて給料をもらう |
| 請負 | 仕事を完成させて報酬をもらう |
| 委任 | 法律行為を頼む契約 |
| 寄託 | 物を預ける |
| 組合 | 共同で事業を行う |
| 終身定期金 | 死ぬまで定期的にお金をもらう |
| 和解 | お互いに譲り合って争いを終わらせる |
まとめ:「契約の成立と有効性」について確認しよう
宅建試験における契約の成立・有効性の判断は、民法の基本的理解としてとても重要です。契約がどのように成立し、どのような場合に無効または取消しとなるのかを、具体例や条文に基づいてわかりやすく解説しました。
特に、契約自由の原則の4つの要素、無効となるケース(公序良俗違反・原始的不能)、そして申込みの撤回ルールと承諾期間の扱いなどは、試験で頻出のポイントです。
また、民法に規定された13種類の「典型契約」についても、その概要を知っておくことで、今後の学習の土台になります。契約法の理解を深めることで、宅建試験の民法分野を確実に得点源にしていきましょう。
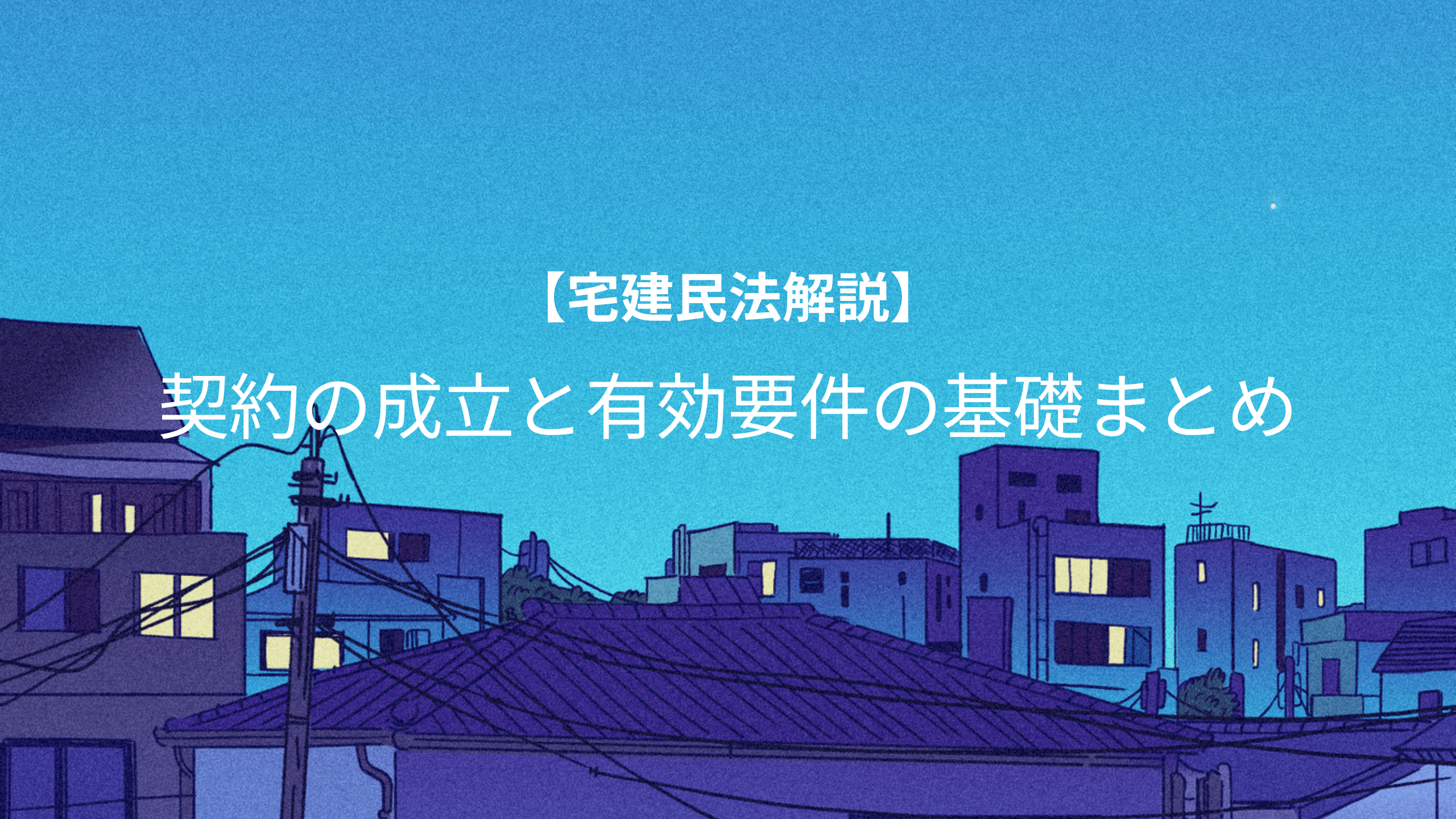

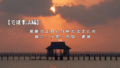


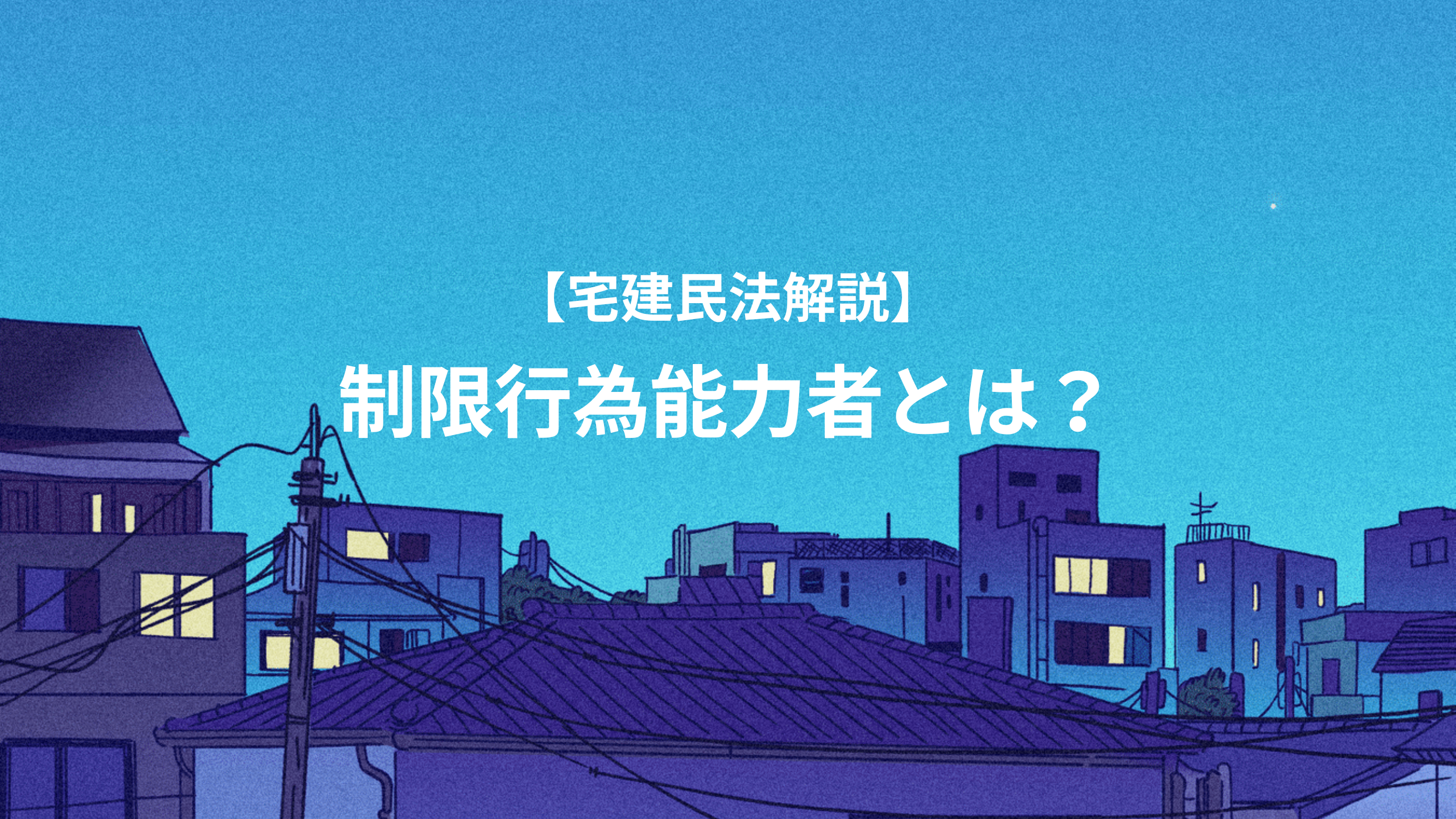


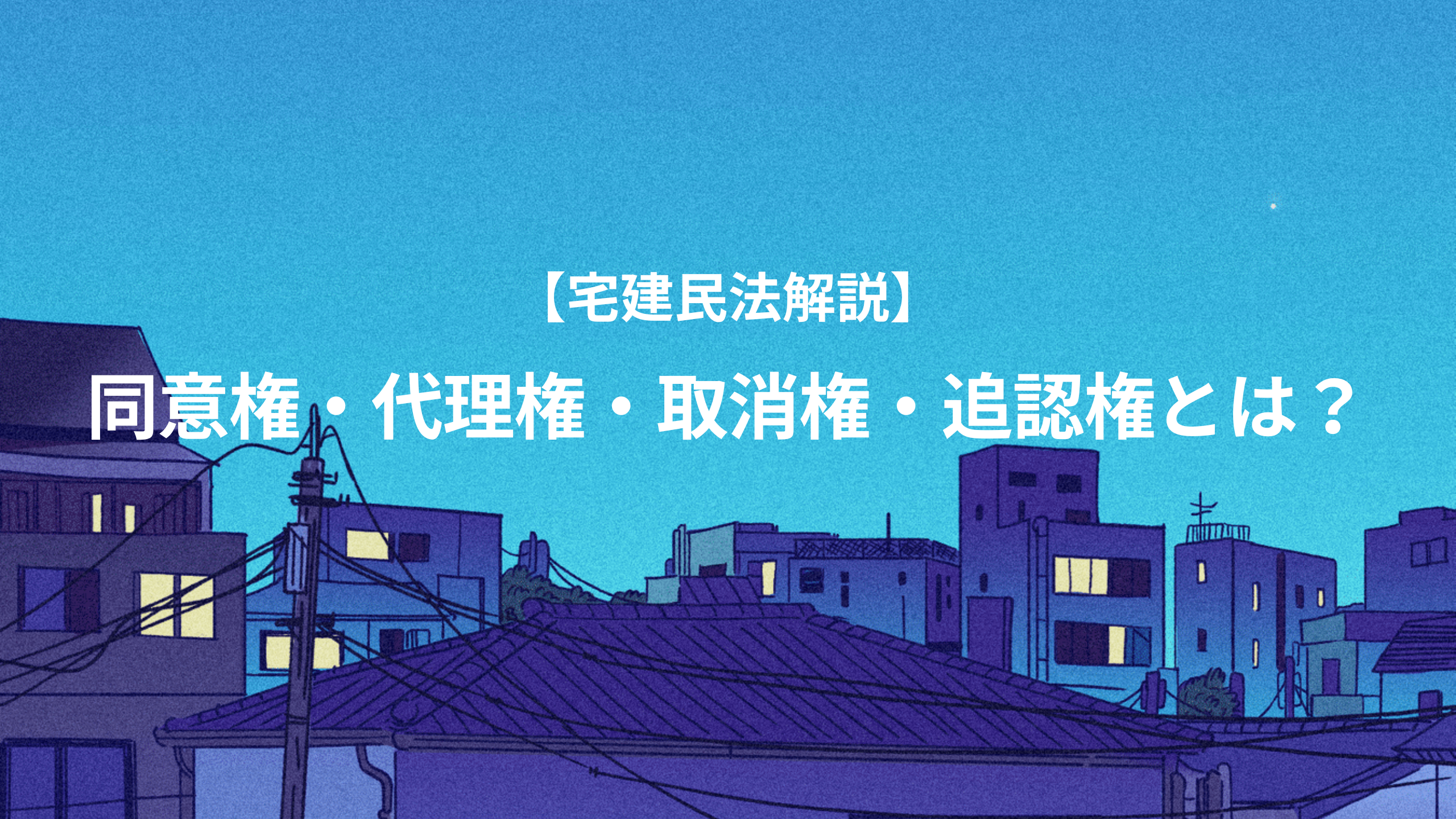
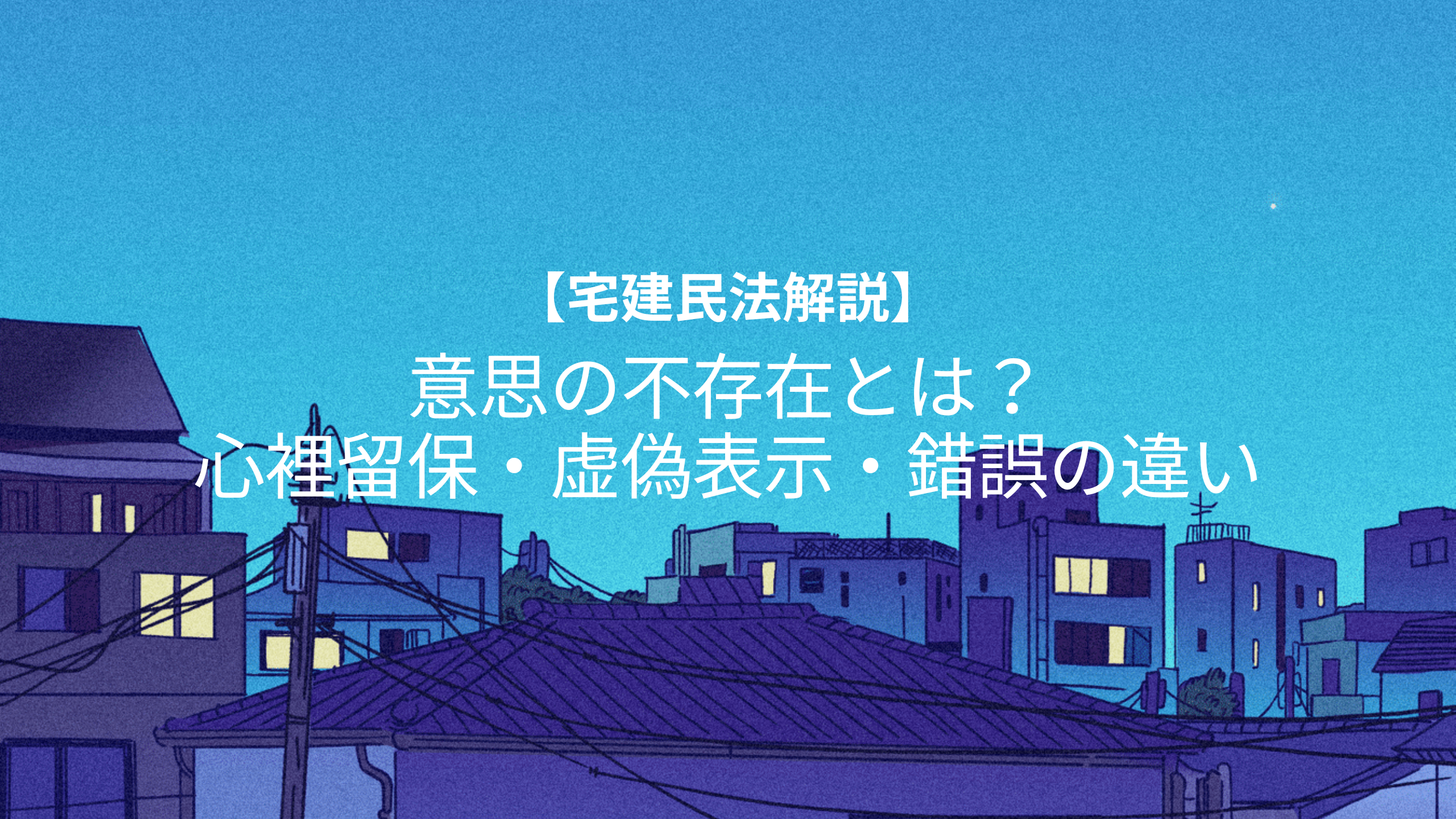
コメント