宅建試験で頻出の「制限行為能力者」について、種類・保護者の権限・契約の取消ルール・相手方の保護など、ポイントを押さえて解説します。
📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
制限行為能力者の種類と定義
制限行為能力者制度は、判断能力が不十分な人々を保護し、不利益な契約などから守ることを目的としています。
また、判断能力の程度は、家庭裁判所の審判によって決定されます。
| 種類 | 内容 | 行為能力の状態 |
|---|---|---|
| 未成年者 | 18歳未満(2022年改正) | 原則として単独で契約不可 |
| 成年被後見人 | 判断能力を欠く人(重度) | 原則として全ての契約が取り消せる |
| 被保佐人 | 判断能力が著しく不十分 | 一部の重要行為は取り消せる |
| 被補助人 | 判断能力がやや不十分 | 家裁の定めた行為のみ取り消せる |
保護者とその権限
制限行為能力者の保護者には、主に同意権、代理権、取消権、追認権があります。保護者は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人などの制限行為能力者の法律行為をサポートし、その権利を守る役割を担います。
| 保護者 | 対象者 | 同意権 | 代理権 | 取消権 | 追認権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代理人(親) | 未成年者 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 成年後見人 | 成年被後見人 | × | ○ | ○ | ○ |
| 保佐人 | 被保佐人 | ○ | 家裁の定めによる | ○ | ○ |
| 補助人 | 被補助人 | 家裁の定めによる | 家裁の定めによる | 家裁の定めによる | 家裁の定めによる |
契約の取消ルールと例外
未成年者
- 原則:単独契約は取り消せる
- 例外:
① お小遣いの範囲内での契約は取り消せない
未成年者が、自分の小遣いなど親から自由に使ってよいとされた財産で契約をした場合は、原則として取り消すことができません。これは、日常生活での少額な取引まで取り消されると混乱が生じるためです。
② 成年と偽って契約した場合も取り消せない(詐術)
未成年者が、自分はもう成人していると嘘をついて契約を結んだ場合、その行為は「詐欺」とみなされ、原則として未成年者取消権を行使することはできません。自分で嘘をついて契約した責任を負うべきという考え方です。
③ 成年後の追認があれば取り消せない
未成年時に結んだ契約でも、成人した後に自らその契約内容を認める行為(追認)をすれば、その契約は有効になります。
④ 未成年者取消権には消滅時効がある
未成年者本人が契約を取り消せる期間は、「成年に達してから5年以内」です。また、法定代理人(多くは親)が取り消せるのは、「追認が可能になってから5年」または「契約が行われたことを知ってから20年」の、どちらか早い方で消滅します。これを過ぎると、取り消しができなくなります。
⑤ 法定代理人の同意があった契約は取り消せない
未成年者が契約を結ぶときに、法定代理人(親など)の同意があった場合は、その契約は有効となり、後から未成年者取消権を使うことはできません。つまり、親の許可を得ていたなら、取り消す権利はないということです。
成年被後見人
- 原則:取り消せる
- 例外:日常生活の行為のみ有効
被保佐人
- 原則:有効(取り消せない)
- 例外:以下のような重要行為は取り消せる
・不動産等の重要財産の売買
・5年超の土地賃貸借
・3年超の建物賃貸借
・大規模な建築請負
相手方を守る「催告権」
制限行為能力者との契約相手は「取り消されるか不安」。そこで、催告により取り消しか追認かを明確にできる制度があります。それが「催告権」。一定期間内(通常は1か月以上)に契約を追認するかどうかを回答するよう求める権利で返事がない場合には原則追認されたものとみなされます。
法律行為を後から認めることで、その行為を有効なものとする意思表示のことです。追認すると契約は遡及的に有効(遡及効)となります。契約の取消しをした場合は、遡及的に無効です。
| 相手 | 催告の宛先 | 返事がない場合 |
|---|---|---|
| 未成年者 | 法定代理人 | 追認とみなす |
| 成年被後見人 | 成年後見人 | 追認とみなす |
| 被保佐人/被補助人 | 保佐人/補助人 | 追認とみなす |
| 被保佐人/被補助人 | 本人 | 取消しとみなす |
その他チェックポイント
- 制限行為能力者が自分を能力者だと偽った場合は取消不可
- 意思無能力者(泥酔・重病等)も保護される
- 意思表示は、相手が意思無能力者であれば効力なし
まとめ:制限行為能力者の制度を正しく理解しよう
制限行為能力者制度は、判断能力が不十分な人を法律上のトラブルから守るための大切な制度です。未成年者や成年被後見人、被保佐人、被補助人など、それぞれに応じた保護者(法定代理人、後見人、保佐人、補助人)が付き、同意権・代理権・取消権・追認権といった権限でサポートされます。
契約は原則として自由に行えますが、未成年者などの制限行為能力者が行った契約には「取消権」があり、無効になることがあります。ただし、「お小遣いの範囲」「成年と偽った場合」「同意があった場合」など、取消しができない例外もある点に注意しましょう。
また、契約相手にとっても不確実性を避けるため、「催告権」によって追認を促す制度が用意されており、返事がない場合は原則「追認」とみなされるケースもあります(本人宛の催告を除く)。
契約が「取消された場合」は最初にさかのぼって無効、「追認された場合」は遡って有効になります。
これらの知識は、宅建試験の頻出ポイントであると同時に、実社会でも非常に役立ちます。基本をしっかり理解し、条文や判例にも慣れながら、確実に得点できるようにしましょう。
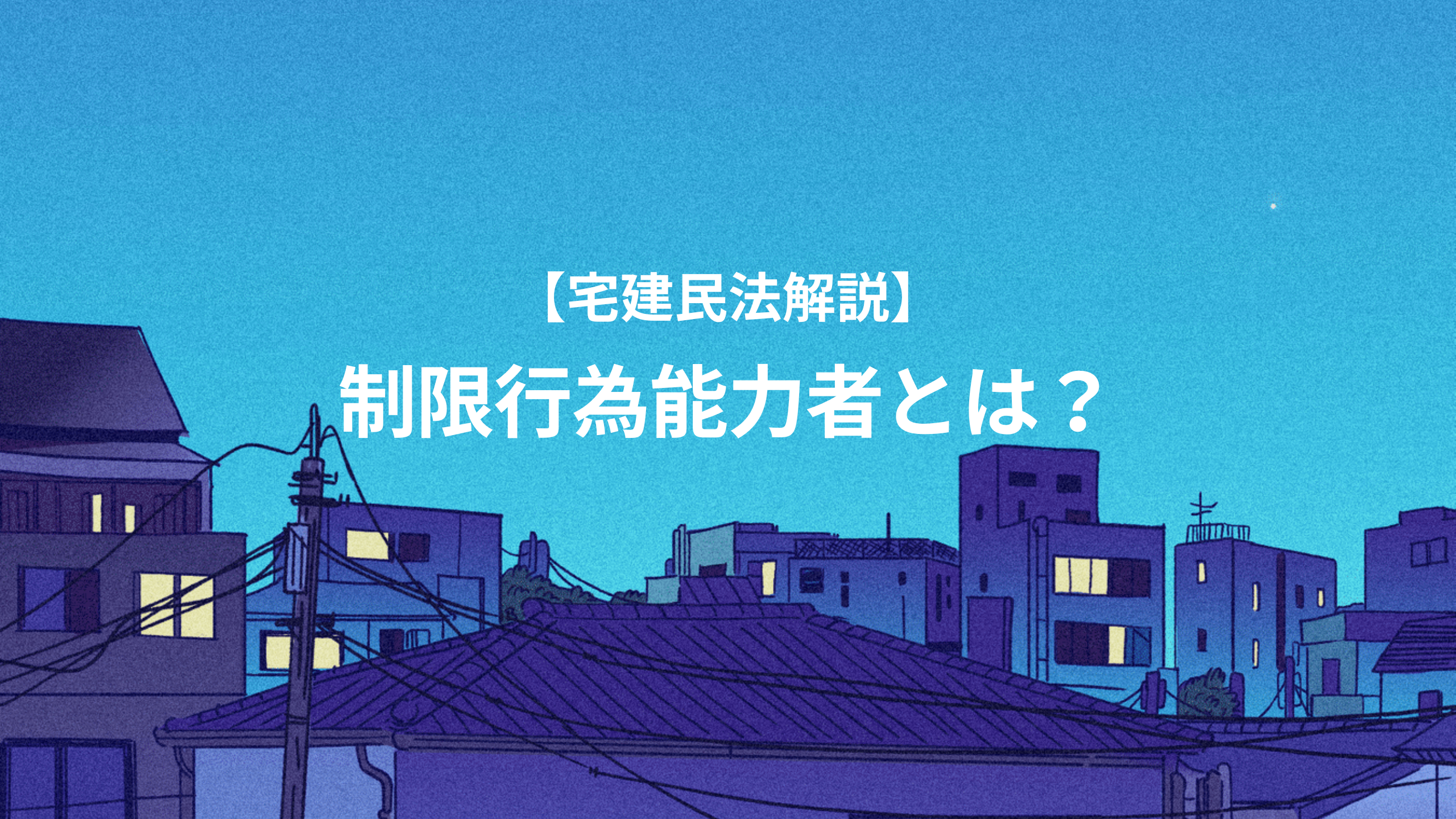

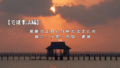





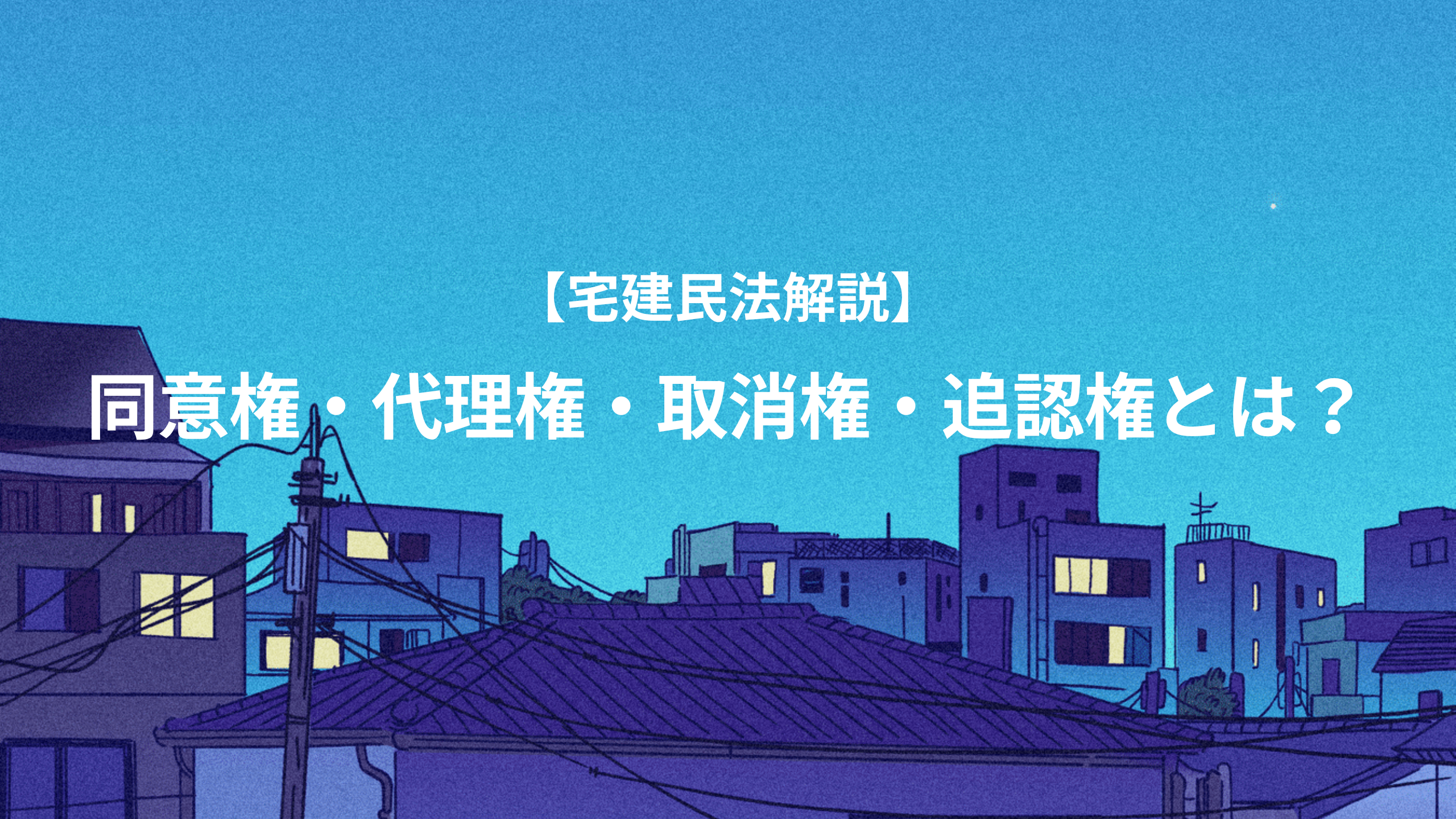
コメント