宅建試験の民法で頻出の「胎児の権利能力」と「未成年者の行為能力」について、ポイントと例を交えて分かりやすく解説します。
📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
¥3,300 (2025/06/19 14:22時点 | Amazon調べ)
胎児の権利能力
原則:権利能力は出生から
- 自然人(=生きている人間)の権利能力は「出生により始まり、死亡により終わる」。
- 出生の定義:母体から完全に分離されたとき(生きて出た瞬間)
胎児の例外的権利能力(民法第886条等)
胎児は原則として権利能力がないが、以下の3つのケースでは「生まれたものとみなされる」。
| ケース | 胎児が権利を持つ理由 |
|---|---|
| 相続 | 父親が死亡した場合、胎児にも相続権が認められる |
| 遺贈 | 遺言により財産をもらえる対象になれる |
| 不法行為による損害賠償請求 | 胎児が事故などの被害者になった場合に損害賠償請求ができる |
📌 「みなす」は反証不可能、「推定する」は反証可能。胎児の権利能力は「みなす」=絶対的効力。
未成年者の権利能力と行為能力
未成年の定義
民法改正により、2022年4月1日から18歳未満が未成年者
改正前は成年擬制(せいねんぎせい)というものがあり、未成年者が婚姻をした場合に、法律上、成年とみなされる制度のことです。2022年4月1日の民法改正で成年年齢が18歳に引き下げられるまで、日本では20歳未満の者が婚姻すると、親の同意がなくても、成年と同様に様々な法律行為を単独で行うことができました。
意思能力と行為能力の違い
| 用語 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 意思能力 | 自分の行為の結果を理解する能力 | 小学校高学年~中学生程度 |
| 行為能力 | 単独で有効に契約などを行える法的能力 | 成年(18歳以上) |
意思能力があっても、未成年は原則として行為能力が制限される(制限行為能力者)。
法定代理人の役割
- 未成年者には原則として法定代理人(通常は親)がつく。
- 法定代理人の権利:同意権・取消権・追認権・代理権
未成年者の行為の原則と例外
原則:法定代理人の同意がない法律行為は取り消せる
未成年者が単独で行った法律行為(契約など)は、原則として取り消すことができます。
これは、未成年者が不利益な契約を結んでしまうことを防ぐための規定です
例外:同意がなくても取消できない行為(=試験頻出!)
| パターン | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| ① 単に権利を得る or 義務を免れる行為 | プレゼントを受け取るなど | 贈与・債務免除 |
| ② 法定代理人が処分を許した財産の処分 | 小遣い等 | 1,000円でお菓子を買う |
| ③ 法定代理人が許可した営業に関する行為 | ビジネス | 宅建業を営む(未成年だが許可あり) |
取消できる人
- 未成年者本人
- 法定代理人(親)
- 成年に達した元未成年者
✅ まとめポイント
- 胎児には特定の3つの権利(相続・遺贈・損害賠償)が認められる
- 「出生により権利能力を得る」が原則、胎児は例外的にみなされる
- 未成年者の行為能力は制限されているが、特定の行為は取消不可
- 法定代理人の権限や取消できる人の範囲もよく出題される


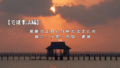


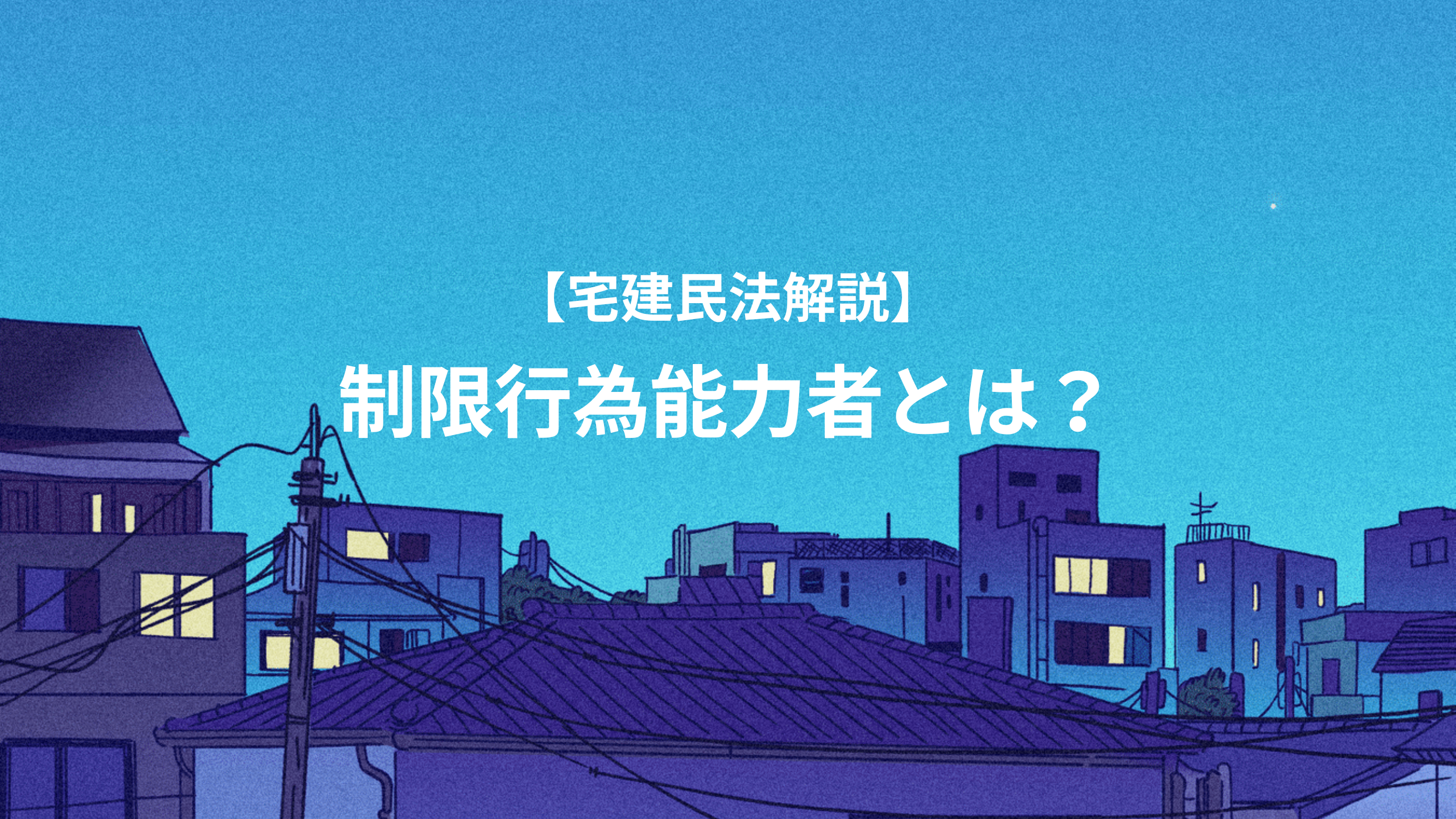



コメント