宅建試験では、「事務所」「案内所」「標識」「帳簿」「従業者名簿」など、宅建業者の営業拠点に関する知識が頻出です。この記事では、出題されやすいポイントを対比表や語呂で覚えやすく整理しました。
📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
¥3,300 (2025/06/19 14:22時点 | Amazon調べ)
事務所の定義と種類
事務所とは:宅建業を営むための拠点の総称。継続的に業務が行える施設が該当します。
事務所の種類
- 本店:
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に本店として記載されている場所。
- 宅建業の主たる拠点となる場所。
- 登記が必要です。
- 支店:
- 営業活動のほか、人材採用や契約締結などの権限を持つ場所。
- 登記が必要で、設置には手続きと費用がかかります。
- 宅建業を営む場合は、本店と同様に営業保証金の供託や専任の宅地建物取引士の設置が必要です。
- 本店で宅建業を営んでいなくても、支店で宅建業を営む場合は、当然本店も事務所となります。
- 営業所:
- 宅建業の営業活動を行う場所。
- 登記は不要で、比較的簡単に設置できます。
- 宅建業を営む場合は、本店と同様に営業保証金の供託や専任の宅地建物取引士の設置が必要です。
案内所とは?
モデルルームや現地販売センターなど、事務所以外で宅建業の営業活動が行われる場所を指します。以下の5つのような形態がありますが、細かく覚えなくても「モデルルームや現地案内所のような場所」とイメージすればOKです。
| 案内所の種類 |
|---|
| ア)営業所以外で継続的に業務を行う施設 |
| イ)自社の一団の分譲に関する案内所 |
| ウ)他社分譲の代理・媒介を行う案内所 |
| エ)展示会などの催し物会場 |
| オ)分譲地そのものの場所に設置される案内所 |
案内所設置の届出義務
| 届出先 | 免許権者 + 所在地の都道府県知事 |
|---|---|
| 届出時期 | 業務開始の10日前まで |
| 届出が必要な案内所 | 契約締結・申込受付を行う案内所 |
| 届出事項 | 所在地/内容/期間/専任の宅建士の氏名 |
📌 例)東京都知事免許業者が神奈川に案内所設置
➡ 東京都知事+神奈川県知事に届出
事務所・案内所での義務
標識の設置義務
- 契約行為の有無に関係なく設置が必要
- 公衆の見やすい場所に掲示
- 記載内容例:免許番号/有効期間/商号/代表者/専任宅建士の数など
報酬額の掲示(事務所のみ)
- 宅建業者は事務所ごとに報酬額の掲示が義務
- 案内所等には義務なし
従業者名簿(事務所のみ)
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 記載内容 | 氏名・勤務開始日・退職日・宅建士か否か など |
| 保存期間 | 最終記載から10年間 |
| 閲覧義務 | 関係者から請求があれば閲覧させる義務あり(PC画面でも可) |
| 名簿の用途 | 従業者証明書の発行台帳にもなる |
帳簿:取引台帳(事務所のみ)
- 事務所ごとに設置
- 取引の都度記載が必要
- 閲覧義務はなし
- 住宅瑕疵担保履行法に該当する帳簿は10年保存、それ以外は5年保存
宅建士の設置義務
| 設置場所 | 必要人数 | 備考 |
|---|---|---|
| 事務所 | 業務従事者5人に1人以上 | 常勤の専任者 |
| 契約等を行う案内所 | 1人以上 | 専任者が必要 |
| 契約を行わない案内所 | 不要 | 設置義務なし |
📌 注意
複数業者が共同で案内所を使う場合:
→ 同一物件・同一場所なら1人でOK
→ 異なる物件を取り扱うなら各社1人ずつ必要
従業者証明書
- 従業者は、証明書の携帯が義務
- 請求されたら提示義務あり(名簿や宅建士証では代用不可)
- 氏名・生年月日・免許番号・本店所在地などを記載
事務所・案内所に設置すべきこと
| 項目 | 事務所 | 案内所(契約締結等を行う場合) |
|---|---|---|
| 専任の宅建士 | 必要(5人に1人以上) | 1名以上必要 |
| 宅建士の要件 | 成年者・常勤・専従 | 成年者であればOK |
| 標識の掲示 | 必要 | 必要 |
| 報酬額の掲示 | 必要 | 不要 |
| 帳簿の備付け | 必要 | 不要 |
| 従業員名簿の備付け | 必要 | 不要 |
案内所では、標識の掲示以外は不要となっています。
まとめ:試験で狙われやすいポイント
- 事務所は宅建業を営んでいなくても本店は「事務所」扱い
- 契約等を行う案内所は届出・宅建士設置が必要
- 帳簿・従業者名簿・報酬額掲示は「事務所のみ」
- 数字(保存期間・届出期限・補充期限)を要暗記!


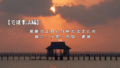


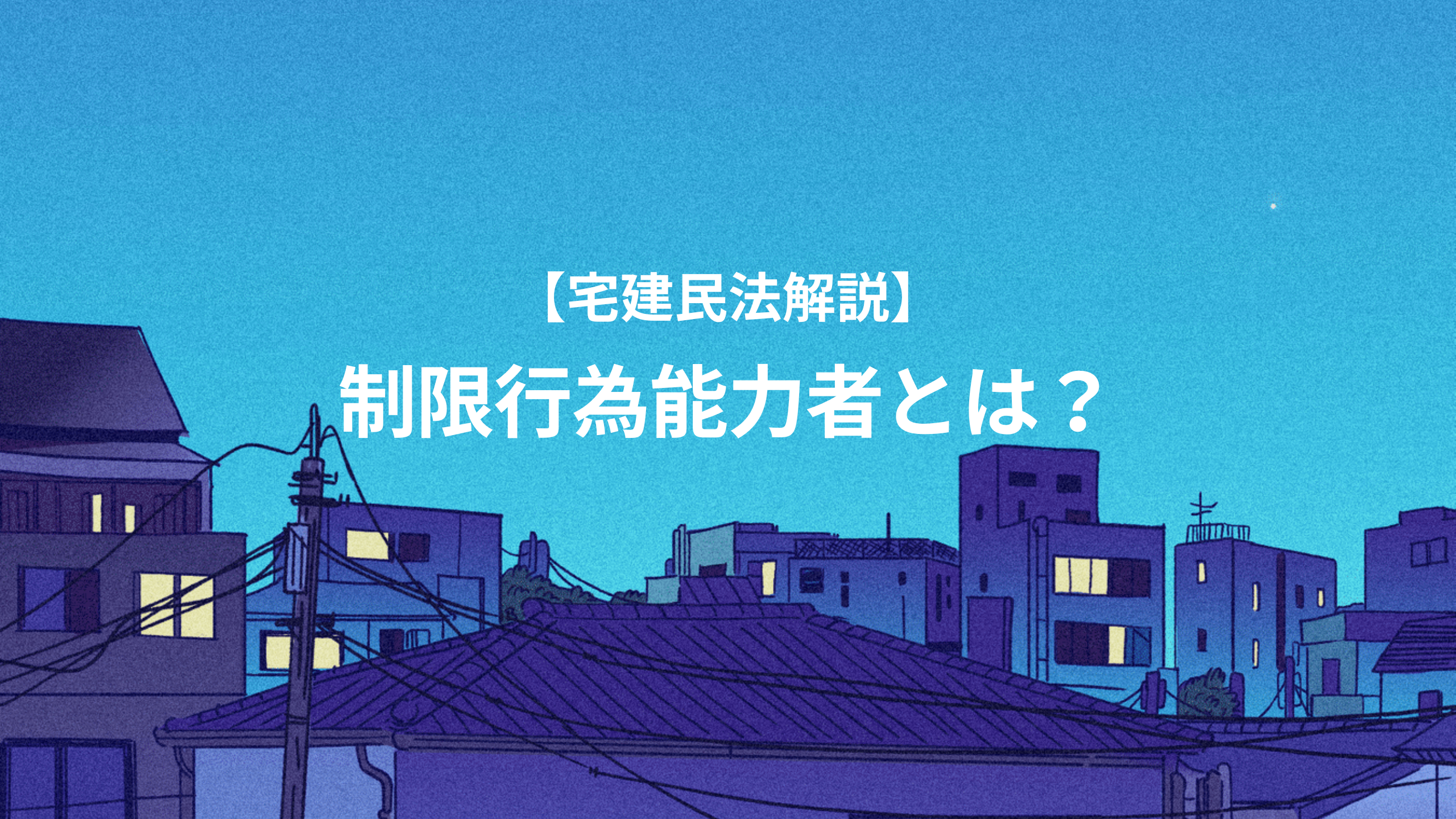






コメント