クーリング・オフ制度とは、宅建業者が売主となる取引において、買主(非業者)に一方的な契約解除の権利を認める制度です。宅建試験ではひっかけが多いため、出題ポイントを正確に押さえておくことが重要です。
📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
¥3,300 (2025/06/19 14:22時点 | Amazon調べ)
クーリング・オフの基本ルール
- 対象取引:宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合
- 対象物件:宅地・建物
- 根拠:民法の原則を修正する宅建業法上の特別ルール(消費者保護)
クーリング・オフができない場所(=事務所等)
宅建業者と不動産の売買契約を結んだ場合でも、以下のいずれかの場所で契約した場合は、クーリング・オフ制度の対象外となります。
① 事務所
- 宅建業者の本店・支店・営業所など
- 専任の宅建士の設置義務がある場所
② 継続的に業務を行える施設以外のもの
(例:案内所・モデルルームなど)であっても、以下に該当する場合は「事務所等」とみなされ、クーリング・オフ不可
- 土地に定着した一団の宅地建物の分譲を行う案内所
- 説明をした後に展示会などを行う施設
③ 他の宅建業者の事務所や案内所
- 宅建業者が媒介や代理を依頼した別の宅建業者の「事務所」や「モデルルーム」なども含まれる
④ 買主自身の申出による契約場所
- 買主の自宅や勤務先であっても、買主が自ら申し出て選んだ場合はクーリング・オフの対象外
※ 上記以外の場所で申込みを行った場合は、クーリング・オフ可能。
判断の基準は「申込みの場所」
- 「契約を締結した場所」ではなく、「申込みをした場所」で判断する。
- 例:申込みが事務所等外 → クーリング・オフOK
申込みが事務所 → 契約が事務所等外でもNG
📌 事務所以外での案内所には「クーリング・オフ可能」の標識表示が必要
クーリング・オフができる期間
- 宅建業者から「クーリング・オフできる旨と方法」を書面で告知された日から8日以内
- 書面で告げられていなければ、いつまでもクーリング・オフ可能
クーリング・オフできなくなるタイミング(2つの条件)
以下両方を満たすとクーリング・オフ不可になります:
- 宅地・建物の引渡しが完了している
- 代金の全額を支払っている
❌どちらか一方だけではクーリング・オフの権利は残る!
- 引渡し済&一部入金 → ○可能
- 登記のみ完了 → ○可能(引渡しではない)
クーリング・オフの方法
- 書面で通知すること(メール・口頭は無効)
- 発信主義が適用される(ポスト投函時点で効力発生)
📌 意思表示の効力が相手方に到達したときに発生するという原則(到達主義)に対するあくまで例外です。
クーリング・オフの効果
- 宅建業者は、受け取った金銭を全額返還しなければならない
- 損害賠償や違約金の請求は不可
- クーリング・オフに反する買主不利な特約は無効
- 買主に有利な特約(例:10日以内OK)は有効
試験対策ポイントまとめ
| 項目 | 要点 |
|---|---|
| 適用対象 | 売主:宅建業者、買主:非業者 |
| 適用されない場所 | 事務所・モデルルーム・自宅希望など |
| 判断基準 | 申込みをした場所 |
| 期間 | 書面通知から8日以内 |
| 除外条件 | 引渡し+代金全額支払い済み |
| 方法 | 書面+発信主義 |
| 効果 | 全額返還・違約金請求不可 |
| 特約の扱い | 買主不利:無効/有利:有効 |
クーリング・オフは基本的な制度ですが、場所・タイミング・方法の細かい条件でよく出題されます。表で整理し、過去問演習で反射的に判断できる力をつけましょう。
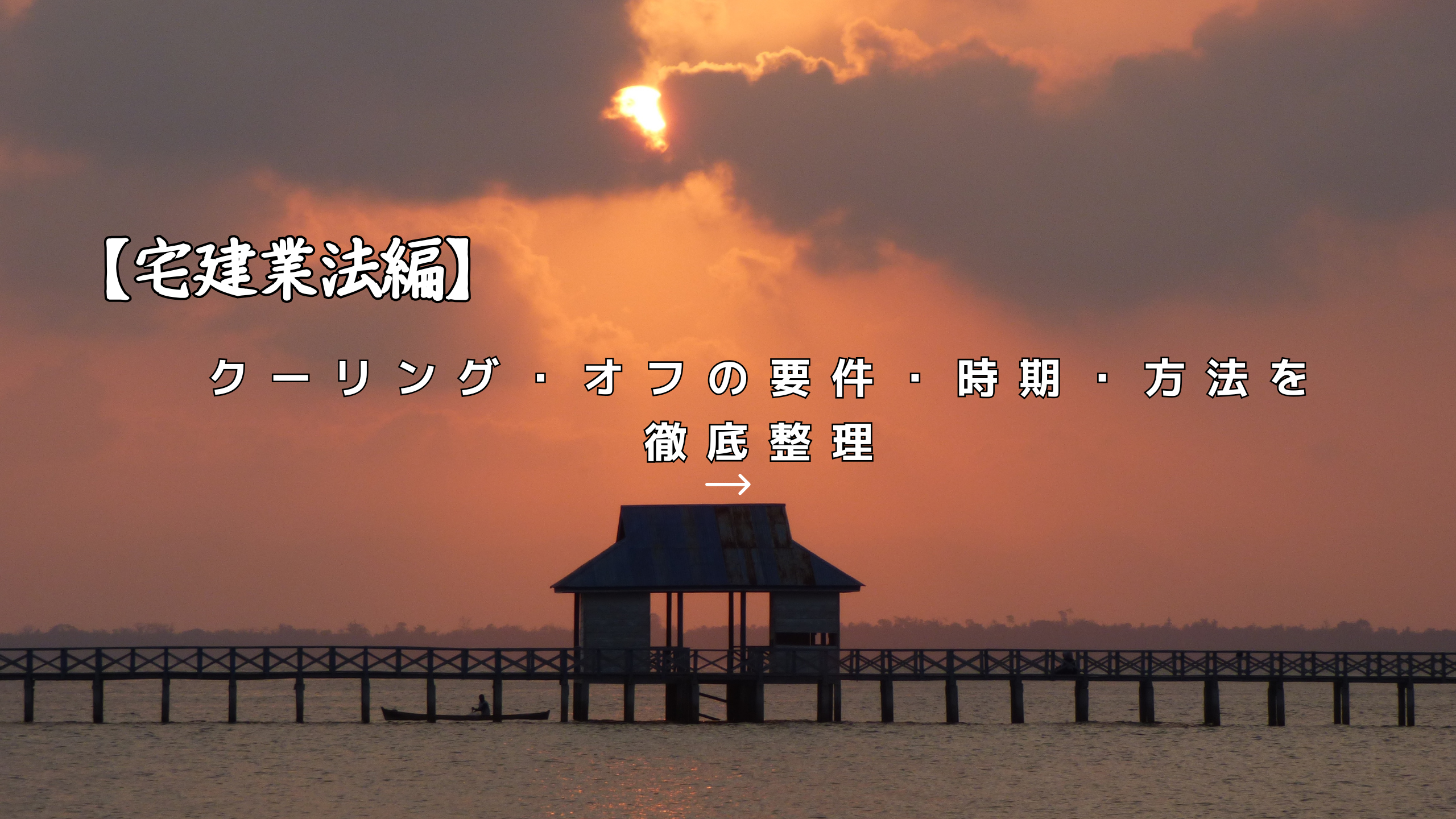
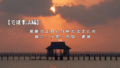









コメント