宅建士として業務を行うには、まず宅建試験に合格し、その後、都道府県知事への登録と宅建士証の交付を受ける必要があります。
登録の際、実務経験が2年以上ある場合は直接登録申請ができますが、2年未満の場合は登録実務講習を受講する必要があります。その流れを確認していきましょう。
📘 宅建の勉強をこれから始めるなら、まずは信頼できるテキストを1冊持っておくことが最優先です。
この記事は、そのテキストと併用することで理解が一気に深まります。独学でもつまずかず、最短で合格を狙うには「参考書+実践解説」の組み合わせが効果的です。
宅建士になるまでの流れ
宅建試験に合格しただけでは、実はまだ「宅地建物取引士」と名乗ることはできません。
以下の3ステップを経て、はじめて「宅建士」として業務に従事できます。
宅建士になるまでの3ステップ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 試験合格 | 年1回の国家試験に合格(合格率15%前後) |
| ② 登録申請 | 住所地の都道府県で「資格登録簿」への登録申請を行う |
| ③ 登録完了 | 登録が完了すると「取引士証」が交付 |
免許取得後は、宅建士証の更新を5年ごとに必要です。
宅建士にしかできない業務(業務独占)
宅建士は、法律上独占的に認められた重要な業務があります。
宅地建物取引士の「3つの独占業務」
- 重要事項の説明(35条書面)
…不動産取引を行う際に、購入者や賃借人に対して、物件に関する重要な情報を説明する業務です。この説明は、契約締結前に行う必要があり、書面交付による方法で行われます。 - 重要事項説明書への記名押印
…重要事項の説明内容を記載した書面である「重要事項説明書(35条書面)」に、宅建士が記名する業務です。 - 契約書(37条書面)への記名押印
…不動産売買契約や賃貸借契約などの契約内容を記載した書面である「契約書面(37条書面)」に、宅建士が記名する業務です。
💡 この3つの業務は、宅建士でなければ絶対にできない「業務独占」行為です!
ちなみに、試験問題では「専任の宅建士」でなければならないと問われる場合がありますが、「専任」である必要はありません。
資格登録簿とは?
宅建士試験に合格した後、「資格登録簿」への登録を行います。
- 管理は住所地の都道府県
- 登録には、実務経験2年以上または国土交通大臣の登録実務講習の修了が必要
- 登録後、晴れて「宅地建物取引士資格者」となります
📌 資格登録簿に記載される情報は、氏名・生年月日・住所・合格年など。
取引士証とは?

宅建士として実際に働くには、「取引士証」が必要です。
- 有効期間は 5年
- 顔写真付きのプラスチックカードで交付される
- 交付申請は「勤務先が決まり、業務に従事する段階」で行うのが一般的
✏️ 取引士証がなければ、たとえ資格者でも「重要事項説明」などの業務はできません。
宅建士の登録基準(欠格事由)
取引士(宅建士)の欠格事由については免許の欠格事由とかぶる部分があるので、免許欠格事由と異なる部分を中心に覚えていくと効率的でしょう。
- 心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない一定の者
- 復権を得ていない破産者
- 免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者
- 免許取消処分前に廃業し、廃業届から5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などに
より刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 - 一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などに
より刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 - 免許申請前5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者
- 宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- 事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録の消除がなされ、まだ禁止期間が満了していない者
- 宅建業の営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
宅建業者の「免許欠格事由」と宅建士の「登録欠格事由」の違い
前回学習は、宅建業者の免許欠格事由を学習しましたが、宅建士にも登録の欠格事由がありますので違いを確認しましょう。
| 欠格事由項目 | 宅建士登録 | 宅建業免許 |
|---|---|---|
| 心身の故障により業務が困難な者 | × | × |
| 復権を得ていない破産者 | × | × |
| 免許取消処分から5年以内の者 | ×(本人) | ×(個人・法人・役員等) |
| 廃業届出から5年以内の者 | × | × |
| 禁錮以上の刑から5年以内の者 | × | × |
| 一定の罰金刑から5年以内の者 | × | × |
| 宅建業で不正・不当行為をした者(過去5年) | × | × |
| 不正・不誠実な行為をするおそれがある者 | × | × |
| 成年と同一の行為能力を有しない未成年者 | × | △(法定代理人の条件により) |
| 暴力団員および5年以内の元暴力団員 | × | × |
| 暴力団に支配される者・会社 | × | – |
| 専任宅建士が5人に1人未満の者・会社 | × | – |
| 事務禁止処分中に登録消除した者 | – | ✕ |
事務禁止処分とは:宅建士が、名義貸しや不正行為などによって指示処分を受けたにもかかわらず、それに違反した場合に、1年以内の期間を定めて宅建士としての業務を禁止される処分です 。
上記のいずれかに該当すると、都道府県知事によって登録は抹消されます。
取引士証を持っている場合は、速やかに返納義務あり
ポイント解説
宅建業者(免許の欠格)
- 法人・個人の両方が対象であり、法人では役員全員の適格性が問われる。
- 社会的信用にかかわる事由(暴力団、禁錮刑、破産など)に加え、過去の行政処分歴や不正な業務経験も判断材料。
- 欠格に該当すれば、免許が交付されない or 更新できない。
宅建士(登録の欠格)
- 個人資格に対する審査であり、業者としての過去ではなく、人格的・法的な資格保持の可否が重視される。
- 登録後でも、該当すれば登録抹消・取引士証返納となる。
- 業者の免許とは異なり、法人の役員構成は無関係。
試験対策アドバイス
- 「免許=業者(法人含む)」「登録=取引士(個人)」と覚える。
- 法人の役員の欠格が影響するのは「免許」だけ。
- 暴力団・破産・禁錮刑などは共通の欠格事由として重要。
- 出題では「宅建業者は◯で宅建士は×」といったひっかけが多いため、対比表で覚えるのが効果的です。
宅建士の更新 と 宅建業の免許更新
| 項目 | 宅建士(取引士証の更新) | 宅建業者(免許の更新) |
|---|---|---|
| 更新対象 | 取引士証(資格証明書) | 宅建業免許(事業を行う許可) |
| 根拠法令 | 宅建業法 第22条 | 宅建業法 第6条 |
| 有効期間 | 5年 | 5年 |
| 更新時期 | 有効期限の満了前に申請 | 有効期限満了の 90日前から30日前まで に申請 |
| 更新に必要なこと | 指定の「法定講習」の受講が必要 | 欠格事由の再審査、事務所の状況などの確認 |
| 提出先 | 取引士証の交付を受けた 都道府県知事 | 免許権者(知事または国土交通大臣) |
| 更新しないとどうなるか | 取引士証が失効(資格そのものは消えない) | 宅建業の営業ができなくなる(無免許営業になり違法) |
| 特徴 | あくまで「証明書」の更新。登録自体は継続される | 営業を続けるために必ず必要。失効すると営業停止になる。 |
宅建士(取引士証の更新)
- 宅建試験に合格し、登録後に発行される「取引士証」の更新です。
- 更新には5年ごとに「法定講習」の受講が必須。
- 更新しなくても登録は残るため、再交付の手続きで再取得は可能。
- 試験では「資格が消えるわけではない」と問われることも。
宅建業者(免許の更新)
- 宅建業を営むための「免許」の更新。法人も個人も対象。
- 有効期間は同じく5年だが、期限内に更新申請しないと営業できなくなる。
- 更新手続きは、業者の所在地が1都道府県内なら知事免許、それ以上なら大臣免許。
- 「欠格事由の確認」や「事務所の状況チェック」がある。
試験対策ワンポイント
- 「取引士証の更新は講習」「免許の更新は営業継続に必須」と覚える。
- 「更新しなくても登録が消えない」のは宅建士だけ。
- 宅建業者は「更新忘れ=無免許営業」で重い違反になる。
※運転免許証も同じく更新を忘れると大変なことになりますよね。

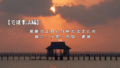






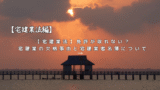



コメント